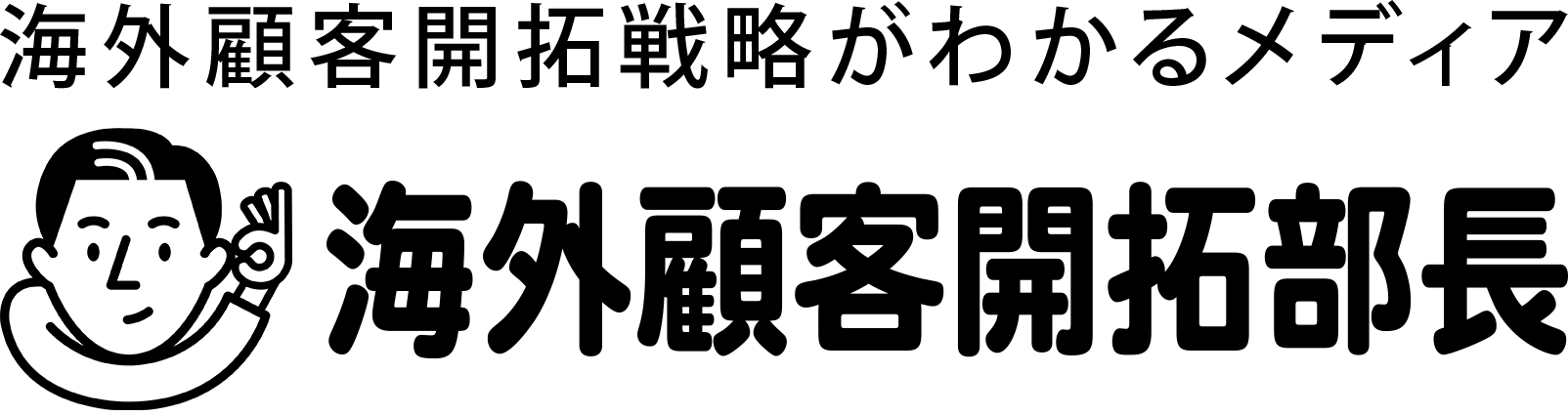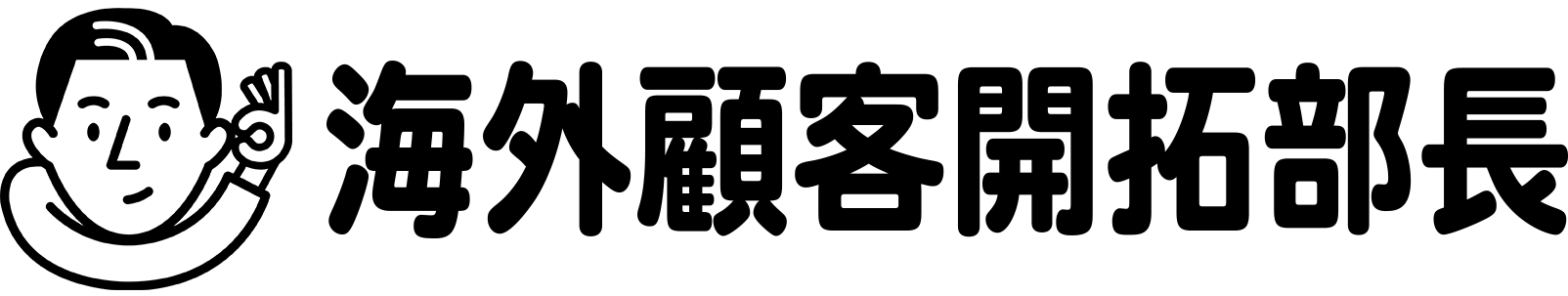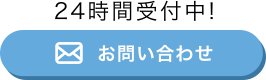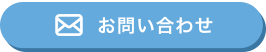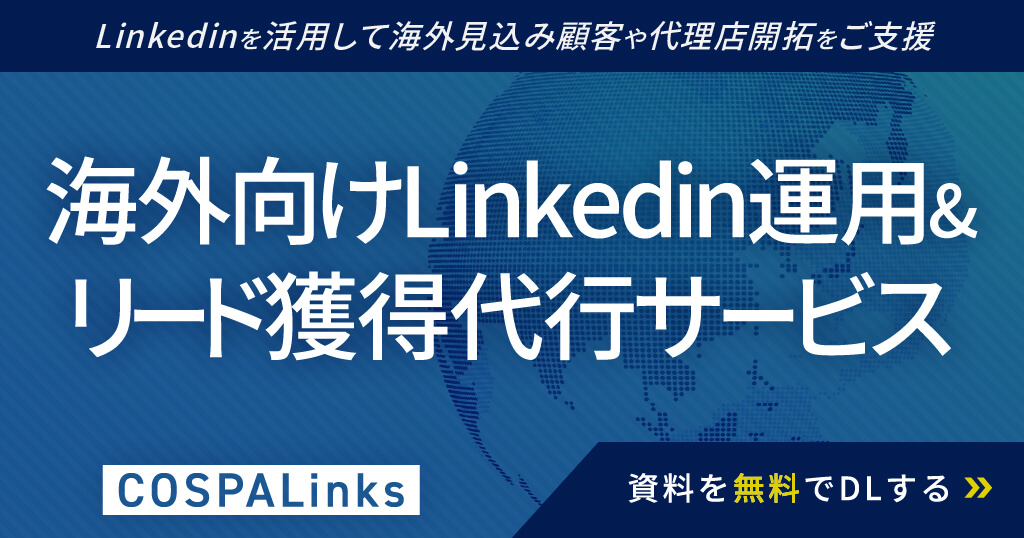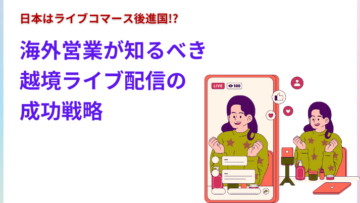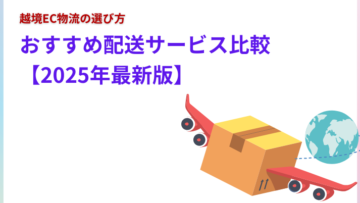京都市の海外展開補助金まとめ|最大240万円支援「グローバル・ニッチ・トップ企業創出プロジェクト
目次
1. 「最大240万円」補助で海外展開を後押し!制度の全貌とは?

京都市が目指す「ニッチ・トップ企業」とは
京都市が支援する「グローバル・ニッチ・トップ企業創出プロジェクト」は、独自技術や専門性を武器に、特定分野で世界をリードする可能性のある中小企業を対象としています。大手と真っ向勝負せず、ニッチな分野で高い競争力を持つ企業を「ニッチ・トップ企業」と定義し、その海外展開を後押しするために、資金・ノウハウの両面から支援します。
製造業だけじゃない!支援対象となる業種
補助金の対象は製造業に限らず、伝統工芸、食品、化粧品、IT、バイオなど多様な業種に及びます。要件は「京都市内に主たる事業所を持つ中小企業」であること。海外販路開拓を目指す企業であれば、BtoB・BtoC問わず対象となり、個人事業主でも申請可能です。特に海外志向を持ちながら一歩踏み出せていない企業に適した制度です。
公的支援だから安心。ASTEMの伴走体制も魅力
制度の実施主体は京都市と公益財団法人京都高度技術研究所(ASTEM)。採択された企業には、ASTEMの専門コーディネーターが伴走し、海外展開計画の策定から市場調査、展示会準備、製品開発に至るまで継続的にサポートします。初めて海外展開に挑戦する企業にも、安心して取り組める体制が整っています。
2. 3つの取り組みを資金でサポート!補助対象の使い方ガイド

海外市場調査・展示会出展・製品開発が対象
補助金は、(1)海外市場のニーズ調査、(2)海外展示会出展、(3)海外規格対応の製品改良・開発の3つの取組みに対して支給されます。単独申請で最大160万円、グループ申請(2社以上)で最大240万円が支給され、補助率は経費の2分の1以内です。複数項目を組み合わせて申請することも可能で、海外展開の段階に応じた柔軟な活用ができます。
グループ申請と単独申請、どう選ぶべき?
1社で申請する単独型はスピーディに進めやすい一方、複数企業が連携するグループ申請は補助上限額が高くなります。連携によって技術・販路・資源を補完し合える企業にはグループ申請がおすすめです。ただし、代表企業が京都市内である必要があり、申請時に合意書の用意も必要です。自社の強みと連携体制を踏まえて判断しましょう。
対象経費はどこまで?使える支出・使えない支出
補助対象経費には、渡航費、通訳・翻訳費、展示会出展料、製品試作費、規格取得費などが含まれます。反対に、日常的な光熱費や事務所家賃、製品の原材料費、機械購入などは対象外です。また、補助対象外の支出が含まれていると減額や不採択のリスクもあるため、経費区分はASTEMの公開資料でよく確認しましょう。
3. 申請の流れと提出書類を完全チェック!成功のコツも紹介

申請タイミング・スケジュール感を押さえよう
2025年度の受付は4月10日から5月8日まで。例年4月上旬に公募が始まり、約1か月間の申請期間があります。6月上旬に採択結果が通知され、交付決定後すぐに事業着手が可能。補助対象期間は翌年2月末までと定められているため、スケジュールを逆算して計画を立てましょう。特に展示会出展など期日が決まっているものは早めの準備が肝心です。
書類で差がつく!審査で見られるポイント
審査では、海外展開の必要性や実現可能性、計画の具体性、経費の妥当性などが評価されます。事業計画書では「なぜ海外か」「ターゲット市場はどこか」「事業終了後の展開イメージ」までを明確に。ASTEMの記入例を参考にしつつ、自社の強みを客観的に伝えられるよう丁寧に作成することが、採択への近道です。
よくあるミスと事前準備で防げるトラブル
書類不備や添付漏れ、締切遅れなど形式的なミスは不採択の大きな原因になります。特にグループ申請では、合意書の未提出や、構成企業の資格不備に注意が必要です。ASTEMが提供するチェックリストを活用し、提出前に必ず再確認を。可能であれば早めに担当窓口に相談することでトラブルを未然に防げます。
4. 実際に活用した企業の事例から学ぶ、補助金のリアルな効果

技術系中小企業が海外展示会で販路開拓
京都市南区のめっき加工企業・旭プレシジョンは、本制度を活用して欧米の製造業向けに展示会出展と市場調査を実施。補助金により高額な渡航費とブース出展料をカバーし、現地商談で新規引き合いを獲得。海外販路のきっかけを掴んだ好例です。製造業BtoB企業にとって現地展示は信頼獲得の第一歩です。
伝統産業がグローバルニッチ市場に挑戦
金箔押しの老舗「金箔押山村」は、伝統技術を生かしたインテリア商品を海外展開すべく、現地ニーズ調査と販促素材の整備に補助金を活用。京都の伝統工芸をグローバル市場に届ける事例として注目され、展示会後には海外バイヤーからの発注にもつながりました。独自性ある技術や文化は海外で強みになります。
補助金を追い風に、海外パートナーとの協業へ
創薬支援ベンチャー「イクスフォレスト・セラピューティクス」は、補助金を用いて海外共同開発のための技術資料作成・規格対応・現地協議に着手。補助金なしでは実行が難しかった初期の連携準備を公的支援で実現し、国際提携の足がかりとしました。資金と信頼の両面で、補助制度の活用が成長を支えています。
5. 【まとめ】補助制度をうまく活かして海外展開を成功させるには

京都府・国の補助金との比較とすみ分け
京都市の制度は補助額の上限が高く、より実践的な支出に対応しているのが特徴。京都府の補助金(上限50万円)や国の事業再構築補助金等と比べ、ニッチ分野特化・中小企業密着型である点が強みです。用途やタイミングによって併用も視野に入れ、最適な資金調達プランを描くことが重要です。
JETROや中小機構との連携で支援を広げる
制度単体で完結させず、JETROや中小機構と連携することで、販路開拓や海外ビジネス人材の紹介、現地情報の取得など支援の幅が広がります。京都市の制度は、こうした外部リソースと組み合わせることでより効果を発揮します。BtoB企業にとっては情報ネットワークの拡充も海外進出の重要な一歩です。
製造業BtoB企業が制度を使いこなすコツ
最大240万円の補助を得られるこの制度は、使い方次第で「輸出の足がかり」から「海外市場の本格参入」まで道を開いてくれます。大事なのは、単なる費用補填にとどまらず、将来の展開を見据えた活用を設計すること。製造業の強みを翻訳して伝える準備を、この制度で始めてみてはいかがでしょうか。
監修者紹介
中島 嘉一 代表取締役
SNSリンク:https://linktr.ee/nakajima
株式会社コスパ・テクノロジーズ 代表取締役。
愛媛大学情報工学部卒業後、船井電機にて中国駐在し5,000人規模の組織管理とウォルマート向け海外営業を担当。
上海で起業し通算10年の中国ビジネス経験を持つ。Web制作・デジタルマーケティング歴13年以上で現在は英語圏・中華圏を中心とした海外展開支援のスペシャリストとして活動。
多言語Webサイト構築、越境EC、SNS・広告運用を駆使して企業の海外顧客開拓から、国内向けWebサイト制作・ブランディングまで、戦略立案から実行まで一貫サポート。
海外ビジネスに関するセミナーやイベントに登壇するほか、SNS総フォロワー5万人以上、中小機構海外販路開拓アドバイザーとして中小企業から上場企業まで幅広く支援実績を持つ。