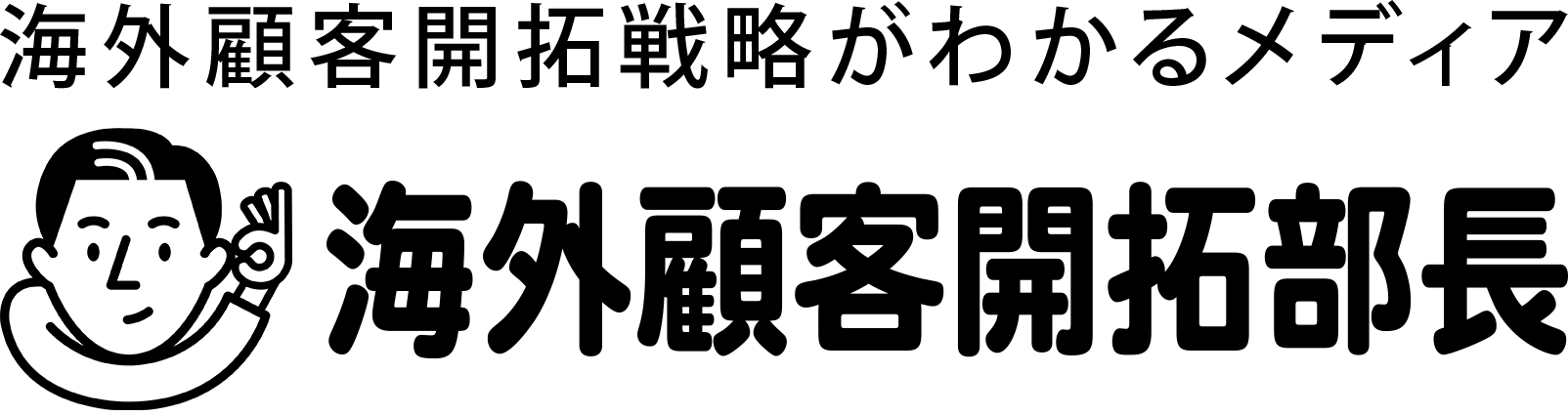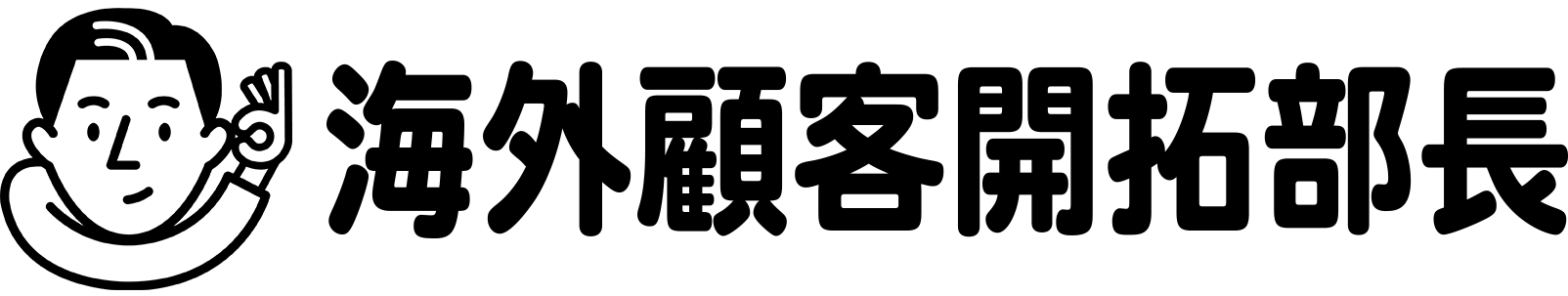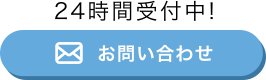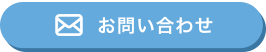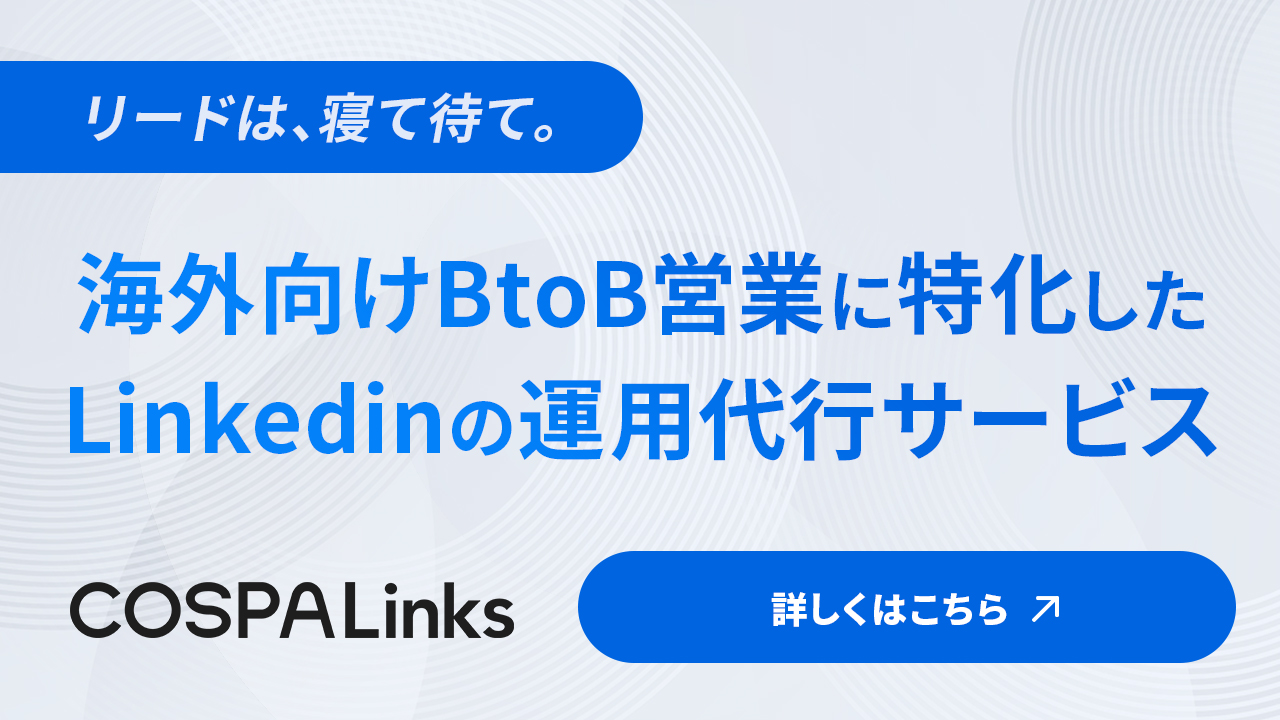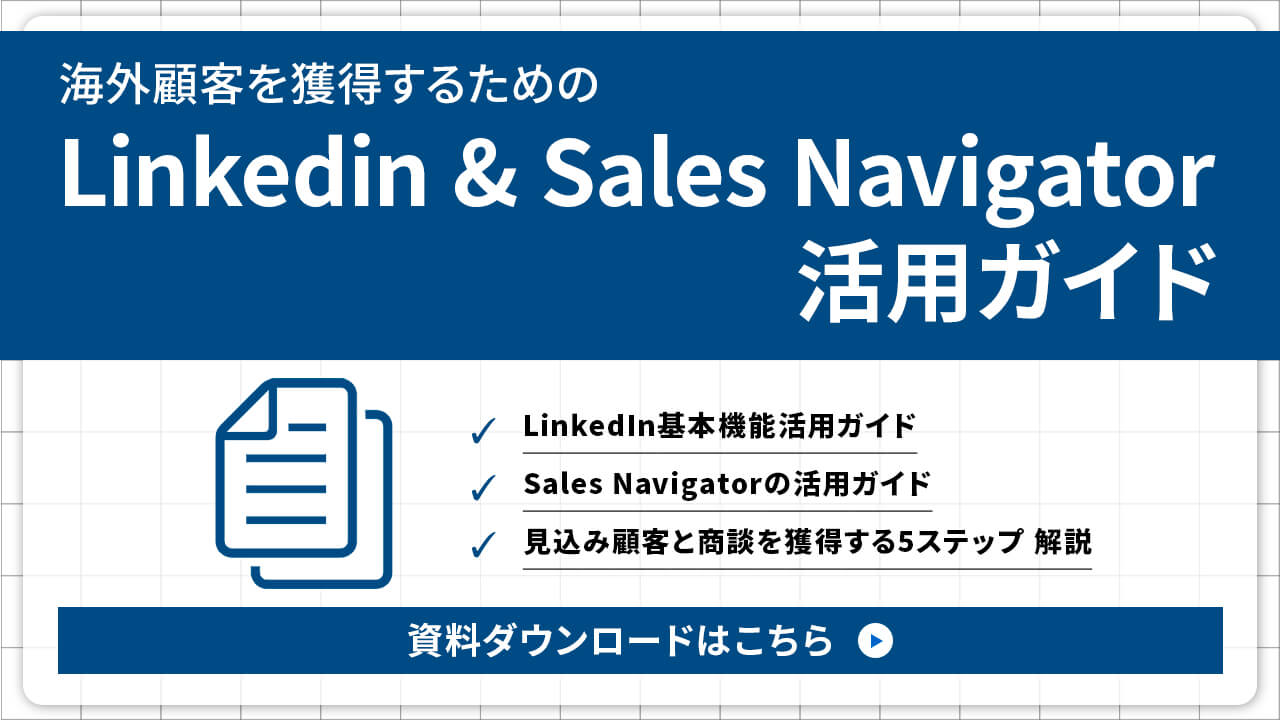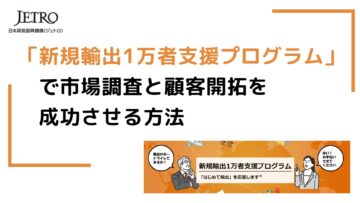人民元ステーブルコイン構想とは何か?その背景と中国の狙い
目次
1.人民元ステーブルコイン構想とは何か?その背景と中国の狙い

中国が注目する「人民元ペッグ型ステーブルコイン」とは?
ドルを使わずに世界と取引する。そんな中国の野望が、ついに現実味を帯びてきました。注目されているのが人民元ペッグ型ステーブルコインです。中国が推進しようとしているこの仕組みは、米ドルに代わる新たな国際決済手段として注目を集めています。これはブロックチェーン技術を活用し、法定通貨である人民元と連動する形で価値が安定した仮想通貨の一種です。上海市の規制当局や複数の国有企業が主導し、JD.comやAnt Groupなどの大手企業も関心を示しており、特にオフショア(香港など)での導入が進められています。
この構想の背景には、米ドル依存からの脱却という中国の国家戦略があります。貿易決済や越境ECにおいて、ドルを介さずに取引できるようにすることで、為替リスクの軽減や送金スピードの向上を狙っています。海外営業やBtoB企業にとっては、こうした新たな決済インフラが営業プロセスや回収スキームに大きく影響を与える可能性があるため、制度設計の動向を注視する必要があります。
デジタル人民元との違いと共存の可能性
中国ではすでに「デジタル人民元(e-CNY)」が一部で実証・運用されていますが、ステーブルコインとは別物です。デジタル人民元は中央銀行(PBOC)が直接管理する法定通貨のデジタル版であり、国内の小口決済や個人間送金が主な用途です。一方、人民元ペッグ型ステーブルコインは、主に国際取引や越境決済を対象としており、発行主体が国有企業やテック企業になる可能性があります。
両者は競合するものではなく、役割を分担しながら並存するという見方が有力です。たとえば、デジタル人民元は国内市場のキャッシュレス化を推進し、ステーブルコインは輸出入・国際取引の場面で活用される、というように使い分けが進むでしょう。越境ECや海外営業戦略を考えるうえで、「どの場面でどの通貨形式が使われるのか」を把握することは、今後の提案設計や契約交渉の前提条件となります。
国際貿易・決済構造を変える地政学的背景
中国がステーブルコイン構想を進める背景には、経済だけでなく地政学的な意図も含まれています。特に米国の制裁政策やSWIFTネットワークへの依存リスクを回避する動きが加速しており、自国通貨での貿易決済を可能にするインフラ整備は、外交政策の一環としても捉えられています。これは「金融の武器化」への対応とされ、近年の米中対立の流れとも深く関連しています。
このような流れの中で、人民元建てステーブルコインは中国企業にとって国際決済の選択肢を広げ、取引の自由度を高めるものとなる可能性があります。海外btob営業を行う企業にとっては、支払い方法の多様化に備えた柔軟な対応力が求められる場面が今後増えるでしょう。営業活動の初期段階で、どのような通貨・決済方法を相手が希望しているかを確認することも、信頼構築における重要な一手となりそうです。
2.中国ビジネスに与える実務影響とは?海外営業の視点で見る変化

海外営業における送金・決済フローの変化
人民元ペッグ型ステーブルコインの実現により、海外営業の現場では送金・決済の在り方が大きく変わる可能性があります。現在、日本企業が中国の取引先とやり取りする際には、人民元口座や外貨建ての送金処理、仲介銀行を挟んだ複雑なフローが一般的です。こうした手間とコストは営業活動のスピードと利益率を圧迫しており、特に中小企業にとっては大きなハードルとなっていました。
ステーブルコインの導入によって、ブロックチェーンベースのリアルタイム決済が可能になれば、こうした課題は大きく改善されると期待されています。越境取引の支払い処理がよりスムーズかつ安価になり、営業提案時にも「決済のしやすさ」という新たな付加価値を提示できるようになるでしょう。中国市場における営業戦略を見直す上で、決済面の進化は見逃せない重要要素です。
ステーブルコイン導入による信用・リスク管理の新たな課題
一方で、ステーブルコイン導入には新たなリスク管理の課題も伴います。特に中国のように政府と企業の関係が密接な国では、発行体の信用や通貨の裏付け体制が営業活動に直結するリスク要因となり得ます。仮に民間発行のステーブルコインを介して取引を行った場合、その通貨の価値維持や透明性について十分な理解とリスク評価が求められます。
また、相手企業がステーブルコインでの支払いを希望するケースも今後増えると想定されますが、日本企業側にその受け入れ体制が整っていなければ、せっかくの商談が停滞するリスクもあります。海外営業の現場では、こうした新しい通貨の取扱いに関して法務や経理部門と連携し、事前に運用ルールを整えておくことが重要です。制度の進展を見ながら柔軟に対応することが、今後の中国ビジネスの信頼構築にもつながります。
中国企業側の購買行動や支払いスタイルの変化
中国側の購買担当者の視点から見ると、ステーブルコインの導入は“支払いやすさ”の観点で大きな変化をもたらす可能性があります。特にスタートアップや中小企業では、外貨建ての送金よりも人民元ベースで完結できる決済手段を好む傾向が強く、今後は取引通貨の指定や支払いサイクルの変化に注意が必要です。
営業現場では「円 or ドルでの請求」が前提だった従来のスタイルから、「人民元建てで、ステーブルコイン対応可能か?」といった相談を受ける機会が増えるかもしれません。中国市場における海外営業では、金融インフラの変化が“営業条件”の一部になることを想定し、事前に受け入れ体制や価格調整の選択肢を用意しておくことが望まれます。こうした小さな対応の積み重ねが、海外btob営業における信頼の差となって表れます。
3.越境EC・BtoBビジネスに広がる新たなチャンスと注意点

中小企業が中国市場に参入しやすくなる理由
これまで中国市場への参入は、言語や法制度、複雑な決済手続きが障壁となっていました。特に中小企業にとっては、外貨建て送金や人民元口座の開設、為替手数料などのハードルが高く、越境ECやBtoB営業を諦めざるを得ないケースも多く見られました。しかし、人民元ペッグ型ステーブルコインが実用化すれば、そうした課題が一気に解消される可能性があります。
ブロックチェーンを利用した安定した通貨で即時決済が可能となれば、中国の小規模な企業とも直接取引ができるようになります。また、第三者決済業者を介さずに支払いが完了することで、取引コストも大幅に削減されるでしょう。これは、初期投資を抑えて中国市場に挑戦したい企業にとって大きなメリットです。今後は中小企業でも「自社越境EC+直販型海外営業戦略」が現実的な選択肢となり得ます。
価格競争から信頼性競争へ?営業資料に求められるもの
決済インフラが整えば整うほど、競合との差別化要素は「価格」以外の部分に移っていきます。今後の中国向け営業においては、スムーズな取引体験だけでなく、ブランドの信頼性や品質保証、アフターサポートの体制がより重要視されるようになるでしょう。特に越境ECやBtoB営業の初期段階では、「支払いのしやすさ」+「信頼できる相手かどうか」が判断基準になります。
そのため、営業資料やWebサイトでは、製品のスペック以上に「安心感」や「契約後の対応力」を明示することが求められます。たとえば「ステーブルコイン決済に対応しています」と記載することで、相手に柔軟な企業姿勢を伝えることもできます。営業戦略において、こうした細やかな配慮が商談成功のきっかけになる場面は確実に増えるでしょう。
新たな通貨制度下での代理店交渉・契約リスクとは
通貨制度の変化は、営業先との交渉内容や契約条件にも影響を与えます。たとえば、「支払いはステーブルコインで」「決済通貨を人民元建てに」といった要望を現地代理店から受けるケースが想定されます。特に契約書上での通貨表記や支払い方法の明確化は、為替差損リスクや法的トラブルを防ぐために非常に重要です。
また、代理店が第三者発行のステーブルコインを使う場合、その信頼性や価格安定性についてあらかじめリスクを洗い出す必要があります。営業部門だけでなく、法務・経理とも連携し、想定されるリスクに備えた契約テンプレートや確認項目を整備しておくと安心です。中国ビジネスにおける海外営業では、「通貨」に対する基本的な理解と事前準備が、交渉の成否を分ける大きな要因になります。
4.日本企業がとるべき海外営業戦略とは?
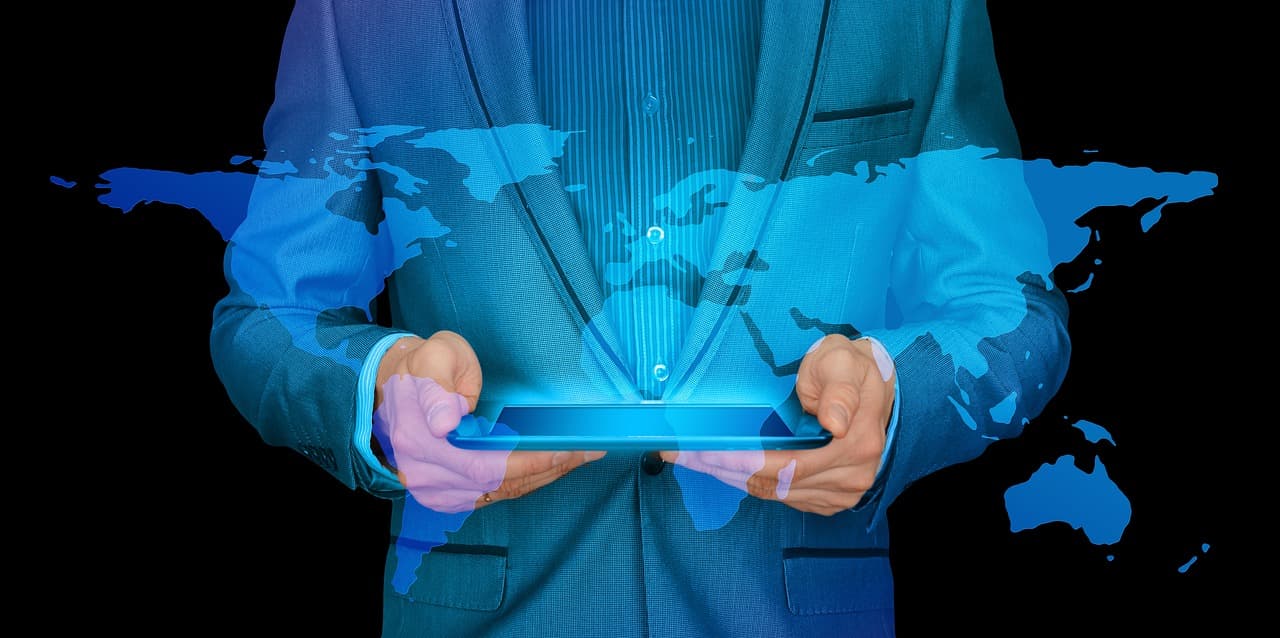
中国市場で成果を出すための営業・調査アプローチ
人民元ステーブルコイン構想の進展を受けて、日本企業に求められるのは「通貨変化を前提にした営業準備」です。従来型の「輸出→銀行送金→決済」という流れでは対応しきれない場面が出てくる可能性があるため、中国企業の購買スタイルや決済インフラに合わせた提案設計が重要になります。
まずは、海外市場調査を通じて「どの地域で、どの業界がステーブルコインを使い始めているのか」「どんな企業が先進的な決済手段に対応しているのか」を把握することが第一歩です。競合企業の動向や、現地の法律・会計基準も含めて情報収集を行い、自社製品や営業体制が対応できるかを点検しましょう。決済は単なる手段ではなく、顧客との信頼関係構築にも直結する「営業戦略の一部」として位置づけることが大切です。
LinkedIn営業・オンライン接点づくりの活用法
中国国内ではLinkedInの利用制限がある一方で、香港・東南アジアに拠点を持つ中国企業やバイヤーは、LinkedInを積極的に活用しています。特に人民元ステーブルコインの活用が進むオフショア拠点(例:香港)とのやり取りにおいては、LinkedIn営業は非常に有効なチャネルです。キーマンに直接アプローチし、提案内容や支払い条件に関する事前のすり合わせを行うことで、商談の精度が格段に高まります。
LinkedIn Sales Navigator(リンクトインセールスナビゲーター)を使えば、決済や国際取引に関心を持っている層をフィルター検索で見つけることも可能です。営業担当者は「通貨や送金方法の柔軟性」「越境ECへの対応状況」などに言及したメッセージを送ることで、信頼感と興味を引くことができるでしょう。海外営業の入口として、オンライン接点は今後ますます重要になります。
社内説得とリスク分散を両立する戦略設計
新たな通貨制度に関連する営業活動を社内で推進するには、リスクとチャンスをバランスよく伝える戦略設計が不可欠です。特に経営層や経理・法務部門からは、「ステーブルコインって安全なのか?」「会計処理はどうするのか?」といった疑問が出ることが予想されます。そこで、営業担当者はリスクを正しく把握したうえで、分散的なアプローチを提案することが求められます。
たとえば、「既存のドル決済を軸に据えつつ、一部顧客にはステーブルコイン決済も検討する」といった段階的導入プランを提示することで、社内の納得を得やすくなります。また、海外市場調査や競合事例を元にしたデータ資料を添えると説得力が増します。海外営業戦略は“やるか・やらないか”ではなく、“どの程度、どう進めるか”が重要です。慎重かつ柔軟な姿勢で、新しい市場環境に対応していくことが求められます。
監修者紹介
中島 嘉一 代表取締役
SNSリンク:https://linktr.ee/nakajima
株式会社コスパ・テクノロジーズ 代表取締役。
愛媛大学情報工学部卒業後、船井電機にて中国駐在し5,000人規模の組織管理とウォルマート向け海外営業を担当。
上海で起業し通算10年の中国ビジネス経験を持つ。Web制作・デジタルマーケティング歴13年以上で現在は英語圏・中華圏を中心とした海外展開支援のスペシャリストとして活動。
多言語Webサイト構築、越境EC、SNS・広告運用を駆使して企業の海外顧客開拓から、国内向けWebサイト制作・ブランディングまで、戦略立案から実行まで一貫サポート。
海外ビジネスに関するセミナーやイベントに登壇するほか、SNS総フォロワー5万人以上、中小機構海外販路開拓アドバイザーとして中小企業から上場企業まで幅広く支援実績を持つ。