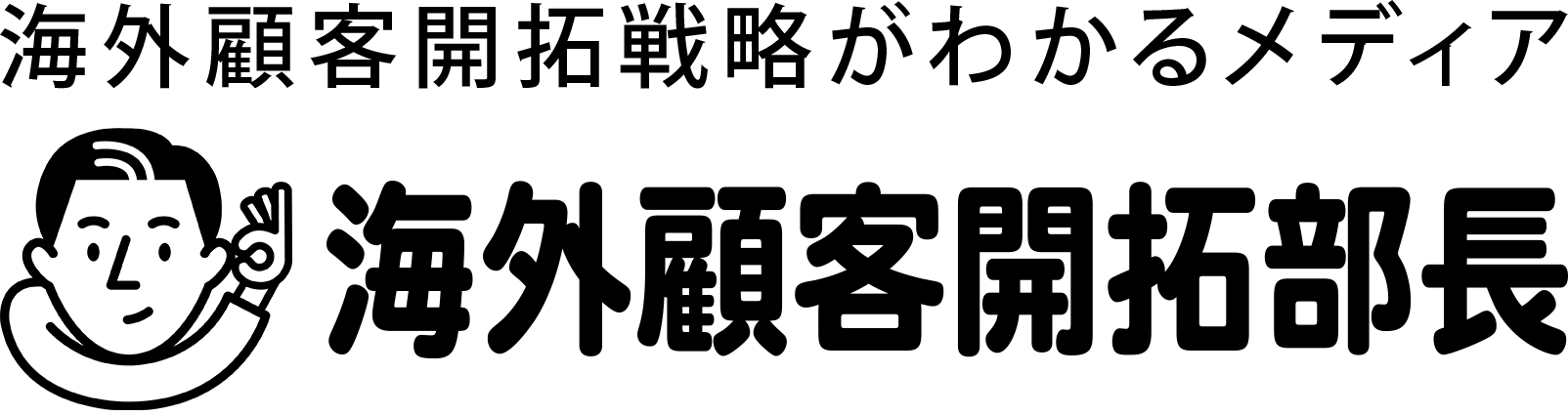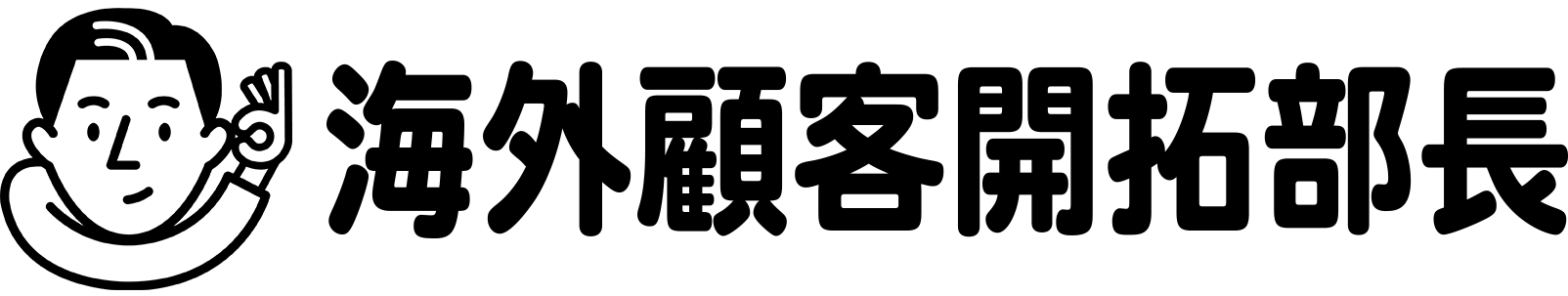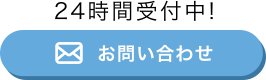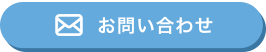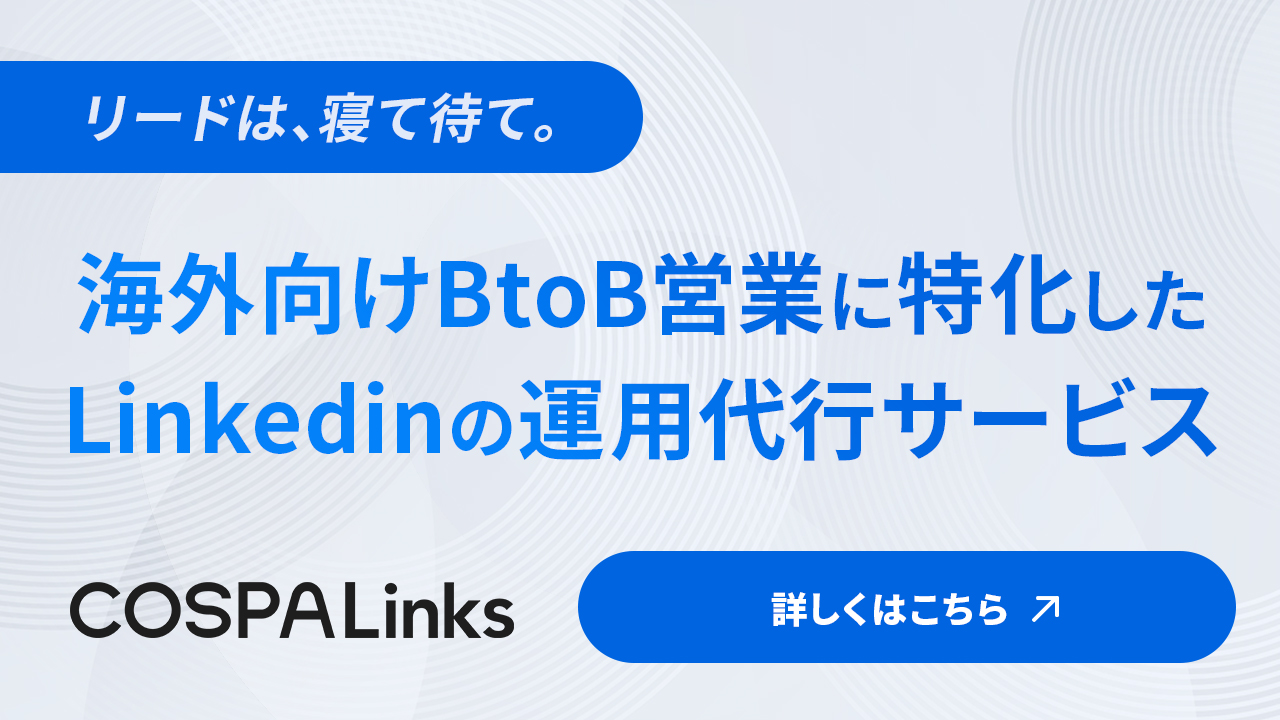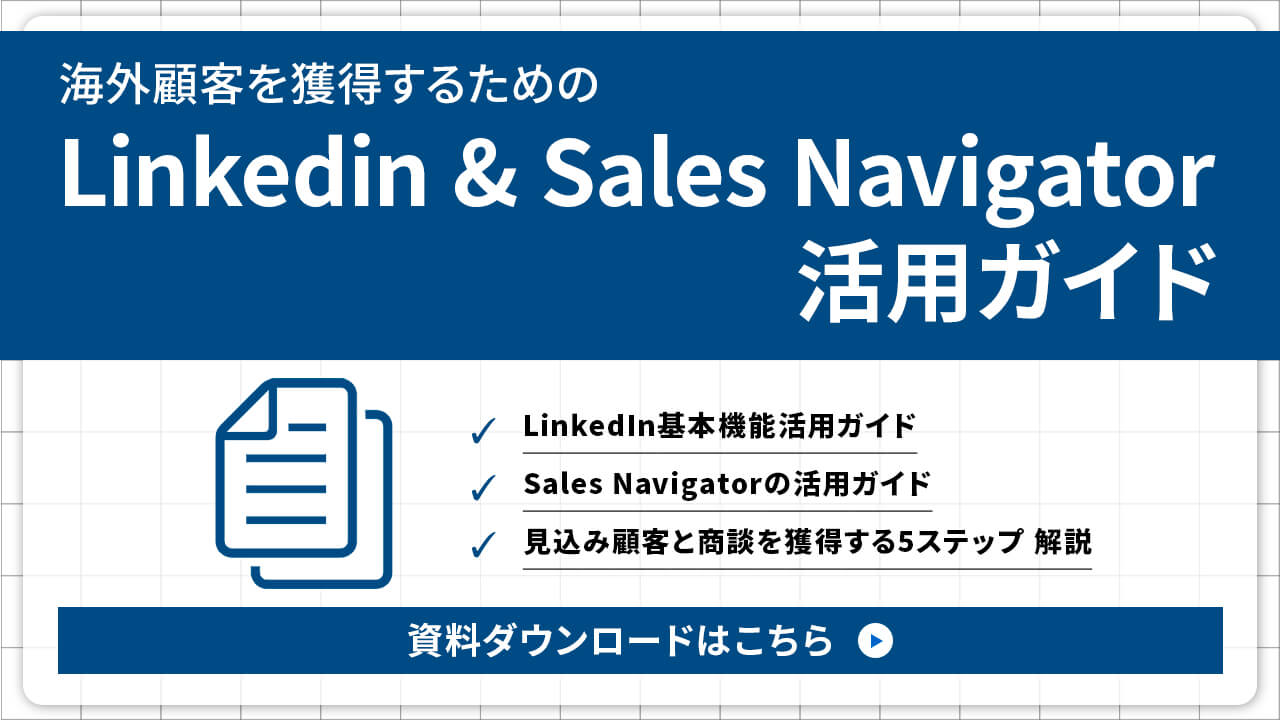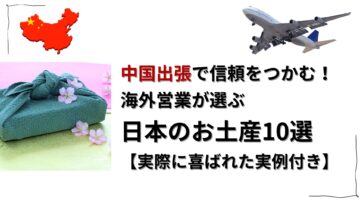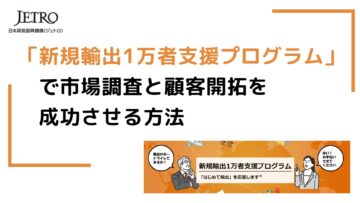新興国でどう攻める?BRICSサミット2025から読み解く海外営業戦略のヒント
目次
1.BRICSサミット2025が示す新興国市場の変化

なぜ今BRICSが注目されているのか?ブラジル開催の意義と背景
「これから狙うなら、どの新興国ですか?」—そんな問いに答えるヒントが、2025年7月に開催されたBRICSサミットに詰まっています。BRICS(ブリックス)は、 ブラジル・ロシア・インド・中国・南アフリカ の5か国の頭文字を取って名づけられたグループです。今回のサミットでは、従来の5か国に加えてサウジアラビアやエジプトなどが加わり、「BRICS+」として11か国体制での初会合が実現しました。世界人口の約半分、GDPの約4割を占める経済圏となった今、BRICSはもはや“新興国”という枠を超えた次世代の巨大マーケットと言えます。
開催国ブラジルは、グローバルサウスにおけるリーダーシップを強調し、特にインドとのデジタル・エネルギー分野での連携を深める姿勢を打ち出しました。一方、中国の国家主席は今回のサミットを欠席し、米中対立の影響が色濃く表れた形です。その結果、インド・ブラジル・南アフリカといった他の加盟国に注目が集まり、営業ターゲットとしての魅力がより鮮明になっています。BRICSを単なる“政治経済の枠組み”として見るのではなく、海外営業にとっての「優先すべき市場群」として捉える視点が、今後ますます重要になるでしょう。
中国首脳不在の波紋とインド・ブラジルの存在感
今回のBRICSサミットで特に話題となったのが、中国の国家主席の欠席です。米中関係の緊張が続く中で、中国の姿勢は従来に比べて内向きになっており、その空白を埋める形でインドとブラジルが存在感を強めています。インドは人口増加とデジタル技術を武器に世界の成長エンジンとして期待され、ブラジルは再生可能エネルギーや食糧生産の観点から注目度が急上昇中です。
海外営業の視点から見ると、これまで中国中心に組んでいた営業戦略を柔軟に見直すチャンスでもあります。特にインドは、LinkedIn営業のターゲットとしても有望で、現地の意思決定者が積極的にSNSを活用している点が強みです。また、ブラジル市場は文化的に「人とのつながり」を重視する傾向があり、関係構築型の営業スタイルがフィットしやすい土壌があります。従来の「中国=第一優先」から脱却し、次の主力市場をどう据えるかが、これからの海外営業戦略の再設計ポイントになるはずです。
日本企業にとっての“攻めどき”は今なのか?
日本企業にとってBRICS市場は「可能性があるが遠い市場」と捉えられがちでした。しかし、今回のサミットをきっかけに、その“遠さ”は戦略次第で大きく縮まると考えられます。インフレ対応や為替リスクを背景に、BRICS各国は外国企業との連携に積極的になっており、タイミングとしてはまさに“攻めどき”といえます。特に、エネルギー、製造業、インフラ分野では、日系企業の高品質な技術や製品へのニーズが高まっています。
ここで重要になるのが、現地市場の温度感を正確に掴む「海外市場調査」です。紙のレポートや政府統計に加え、実際に現地のキーマンが何に関心を持っているのかを把握するには、LinkedIn Sales Navigator(リンクトインセールスナビゲーター)を活用した情報収集が効果的です。投稿や反応を観察することで、営業タイミングの判断材料が得られるでしょう。今動き出すことで、ライバルより一歩先に新興国市場との接点を築けるかもしれません。
2.BRICS市場で成果を出す海外営業戦略とは?

従来の営業手法が通じない?商習慣・決裁構造のギャップ
新興国への海外営業では、日本の常識がそのまま通用しない場面が多くあります。特にBRICS諸国では、国ごとに商習慣や決裁構造が大きく異なります。例えば、ブラジルでは“人脈”が商談成立の決め手になることが多く、関係構築に時間をかける姿勢が重要です。一方、インドではスピード感のある交渉と価格交渉への柔軟性が求められるなど、商談の進め方にも個別対応が必要です。
また、官民の境界が曖昧な国も多く、意思決定者が複数いることも珍しくありません。海外BtoB営業においては、単純な“決裁者への接触”だけでは足りず、影響力のある周辺人物へのアプローチや、非公式なルートからの関係構築が成果につながる場合もあります。日本企業が得意とする“丁寧で誠実な提案”は強みになる一方で、スピード感と柔軟性を意識した対応が求められる市場だと理解しておく必要があります。
「代理店頼み」から「自社主導」へ転換する営業スタイル
これまで新興国市場では、言語や制度の壁を乗り越える手段として現地代理店を活用するケースが主流でした。しかし近年では、代理店任せでは商談の質やスピードに限界があると感じる企業が増えています。特にBRICS諸国のように経済成長が著しい市場では、変化への対応力や情報スピードが重視されるため、自社主導で動ける営業体制へのシフトが求められています。
自社で営業を行うメリットは、何より現地企業との直接的な関係構築ができることです。製品の強みや価値を正確に伝えられるほか、商談の主導権を握りやすくなります。また、LinkedIn営業をはじめとするオンラインチャネルの活用により、現地に常駐しなくても潜在顧客と接点を持つことが可能になってきました。海外営業戦略の中で、“代理店に頼らない体制”を検討することは、今後の競争優位を築くうえで不可欠と言えるでしょう。
成長国でBtoB営業を進めるための準備と注意点
海外btob営業をBRICS諸国で進める場合、いきなり商談に持ち込むのではなく、事前準備と市場理解が成功の鍵を握ります。特に注意すべきなのは、現地企業の課題やニーズが、日本国内の想定とは大きく異なるケースがあるという点です。製品やサービスの導入を考えてもらうには、“なぜ今この国に必要か”を明確に説明できる資料やストーリーが求められます。
また、信頼関係の構築には時間がかかる場合が多く、短期で成果を求めすぎないことも大切です。展示会やオンラインセミナー、SNS上の情報発信を通じて、徐々に接点を作っていく戦略が有効です。営業担当者自身がLinkedInを活用して現地キーパーソンと関係を築くのも効果的でしょう。事前にしっかりと海外市場調査を行い、文化や商習慣、競合動向を把握することで、提案内容の精度が高まり、結果としてBtoB営業の成功率も向上します。
3.現地の声と動向をつかむ「実践型リサーチ営業」のすすめ
公式データでは見えない“現地のリアル”をどう拾うか
BRICSのような新興国市場で営業活動を進める際、政府統計やレポートだけでは、現地の“今”を十分に把握することはできません。たとえば、現地企業が何に困っているのか、どんな製品に関心を持っているのかといった情報は、数字では捉えきれない部分です。ここで役立つのが、オンラインで拾える“動的な情報”です。LinkedInや現地メディア、SNS投稿などを活用することで、ターゲット企業の行動や発信からリアルなニーズが見えてきます。
こうした情報は、海外市場調査の一部として非常に有効です。展示会やセミナーで話を聞くことが難しい企業であっても、オンライン上では積極的に情報発信をしているケースも多くあります。特に新興国の若手経営層は、SNSを活用して自己表現や企業広報を行っており、営業ターゲットを絞り込むヒントになります。数字だけに頼らず、“声”を拾う視点が、これからの海外営業には不可欠です。
LinkedIn Sales Navigatorで反応型リサーチを行う方法
海外市場調査をより実践的な営業活動へとつなげるために、LinkedIn Sales Navigator(リンクトインセールスナビゲーター)の活用は欠かせません。単なるキーマン検索ツールではなく、企業や担当者の投稿頻度、関心トピック、反応パターンを“観察する”ためのリサーチツールとして非常に優秀です。営業ターゲットの選定だけでなく、アプローチのタイミングや切り口を判断するための情報源としても使えます。
たとえば、頻繁に投稿している相手であればInMailへの反応率も高く、逆に投稿が少ない場合は関係構築に時間を要するかもしれません。Navigatorでは企業の最新ニュースや人事異動も把握できるため、アプローチ時に相手の文脈を踏まえたメッセージが可能です。LinkedIn営業において、「誰に・いつ・どんな話をするか」を見極めることが成果を左右します。Sales Navigatorを“反応を見る営業センサー”として使うことで、質の高い商談につなげやすくなります。
調査→アプローチ→商談化を一連の“営業プロセス”に統合する
従来の海外市場調査は、マーケティング部門や外注先がレポートとしてまとめ、それを営業部門が参考にするという分業スタイルが一般的でした。しかしBRICSのような変化の激しい市場では、調査と営業が別々に動いていてはスピードに対応できません。現地の動向を知ったらすぐにアクションを起こす、そんな“調査即行動”の体制が必要です。
たとえば、LinkedIn Sales Navigator(リンクトインセールスナビゲーター)で収集した情報をもとに、営業担当自身がInMailで接点を持ち、そこから商談へと進めていく流れを日常業務に組み込むことが理想です。調査、分析、接触、提案までを一人の担当者が一気通貫で行うことで、情報の鮮度を保ちつつ柔軟な対応が可能になります。海外営業の現場においては、こうした統合的アプローチが、商談化のスピードと質の両立に直結するのです。

4.BRICS+αを見据えた今後の海外営業アプローチ
注目すべき業種・エリアと拡張BRICS諸国(エジプト・サウジ等)
2025年のBRICSサミット以降、新たに加わったエジプト、サウジアラビア、UAEなどの国々は、“BRICS+α”として今後の営業ターゲットとして大きな注目を集めています。特にサウジやUAEでは「Vision 2030」などの国家成長戦略が掲げられ、インフラ、再生可能エネルギー、スマートシティ分野での投資が急拡大しています。こうした分野では、日本の技術力や品質への信頼が強く、提案次第で高付加価値な商材も受け入れられやすい土壌があります。
一方、エジプトはアフリカ市場へのゲートウェイとしての役割も持っており、物流、通信、製造支援といったBtoBサービスへのニーズが高まっています。国ごとに求められる商材や価格帯は異なるため、営業戦略は汎用的ではなく、個別最適化が必要です。新興国といっても十把一絡げにせず、「どの国で、どの業種に、どのように攻めるか」を明確にすることが、今後の海外営業戦略の基盤となります。
中長期的に自社が攻めるべき国と営業計画の立て方
海外顧客開拓を成功させるためには、単発的な展示会参加やスポット提案だけでなく、中長期を見据えた営業計画が不可欠です。特にBRICS+αのように成長性と不確実性が共存する市場では、「今売れるか」よりも「今つながっておくべきか」の視点が求められます。経済状況や政策が変わりやすい国では、いまは商談に結びつかなくても、1~2年後にチャンスが訪れることも珍しくありません。
そのため、国ごとの市場成熟度や競合状況をふまえたうえで、リード獲得から育成、商談化までのステップを設計しておくことが重要です。LinkedInを活用すれば、営業先との“種まき”段階から接点を持つことができ、定期的な発信や反応の蓄積によって関係性を育てることができます。焦らず、段階を踏んで信頼を構築していく——それがBRICS諸国を対象とした海外営業戦略の基本と言えるでしょう。
社内稟議を通すための提案材料と調査リソースの整理
新興国への営業展開を進める際、多くの担当者が直面するのが「社内稟議が通らない」という壁です。売上予測が立てにくい、現地の信頼性が不透明、投資対効果が読みづらいといった理由から、経営層の理解を得られないケースも少なくありません。だからこそ、営業担当者自身が説得材料を準備し、戦略的に社内を巻き込む必要があります。
具体的には、海外市場調査の結果を資料化し、現地の成長性や競合状況、ニーズの明確化などを数字や実例で示すことが有効です。また、LinkedIn Sales Navigator(リンクトインセールスナビゲーター)などを活用して、すでに接触できそうな現地企業や意思決定者の存在を見せることで、「すぐに動ける市場」であることを伝えることができます。営業活動を単なる思いつきではなく、“根拠ある戦略”として見せることが、社内理解と支援につながります。
監修者紹介
中島 嘉一 代表取締役
SNSリンク:https://linktr.ee/nakajima
株式会社コスパ・テクノロジーズ 代表取締役。
愛媛大学情報工学部卒業後、船井電機にて中国駐在し5,000人規模の組織管理とウォルマート向け海外営業を担当。
上海で起業し通算10年の中国ビジネス経験を持つ。Web制作・デジタルマーケティング歴13年以上で現在は英語圏・中華圏を中心とした海外展開支援のスペシャリストとして活動。
多言語Webサイト構築、越境EC、SNS・広告運用を駆使して企業の海外顧客開拓から、国内向けWebサイト制作・ブランディングまで、戦略立案から実行まで一貫サポート。
海外ビジネスに関するセミナーやイベントに登壇するほか、SNS総フォロワー5万人以上、中小機構海外販路開拓アドバイザーとして中小企業から上場企業まで幅広く支援実績を持つ。