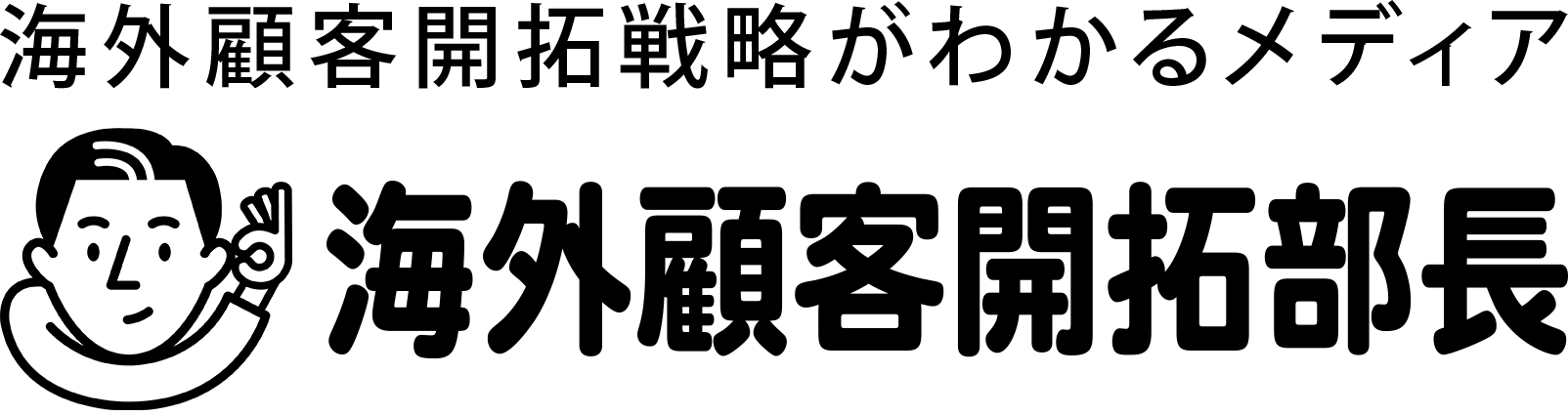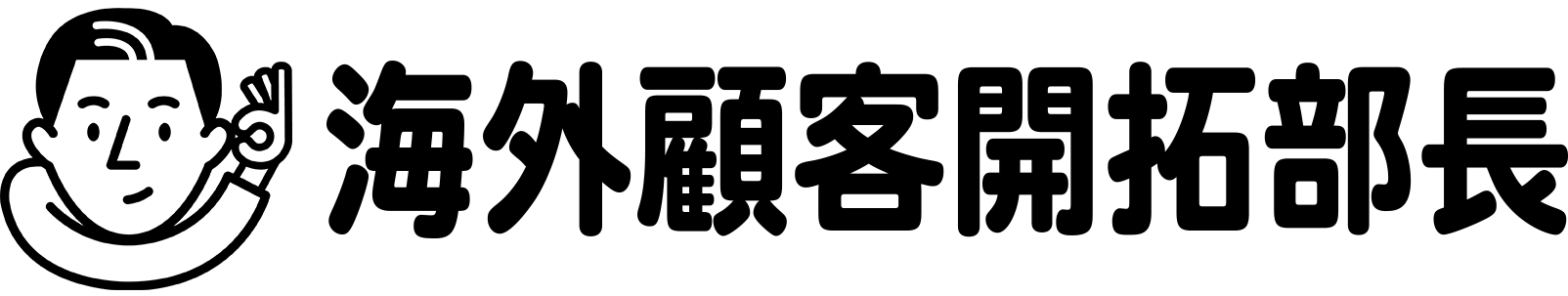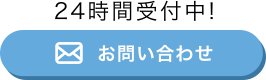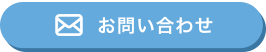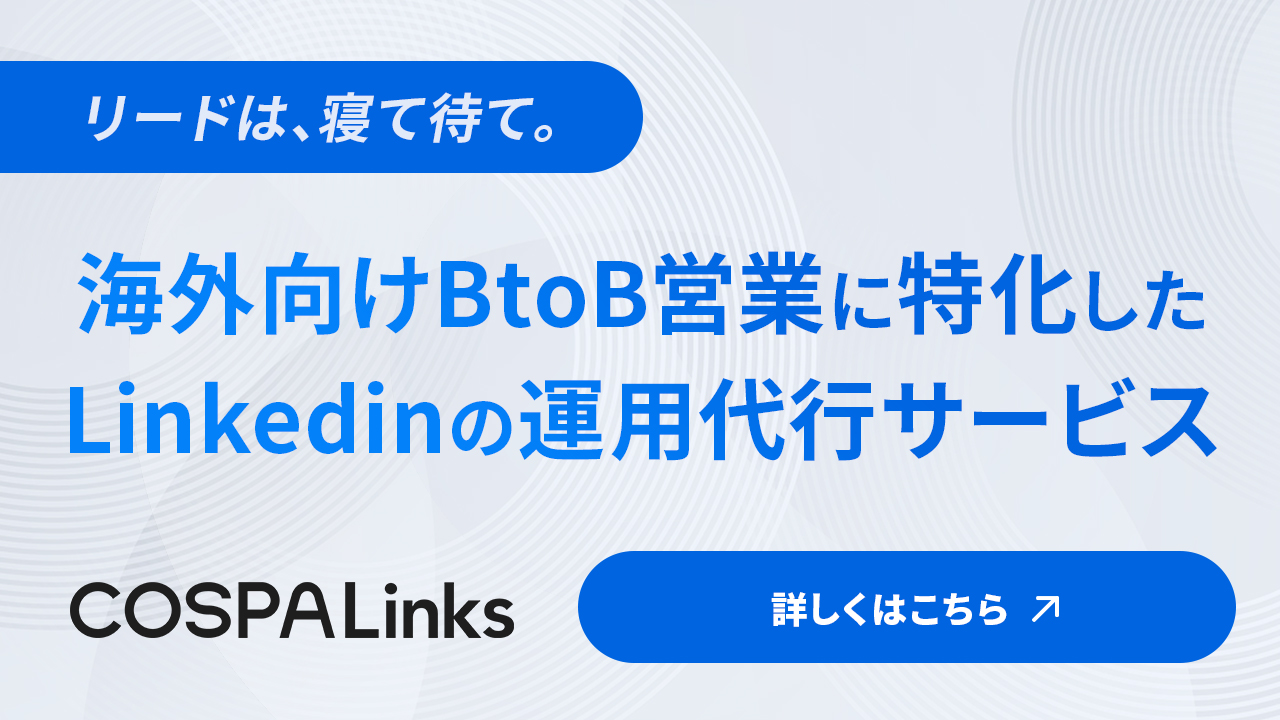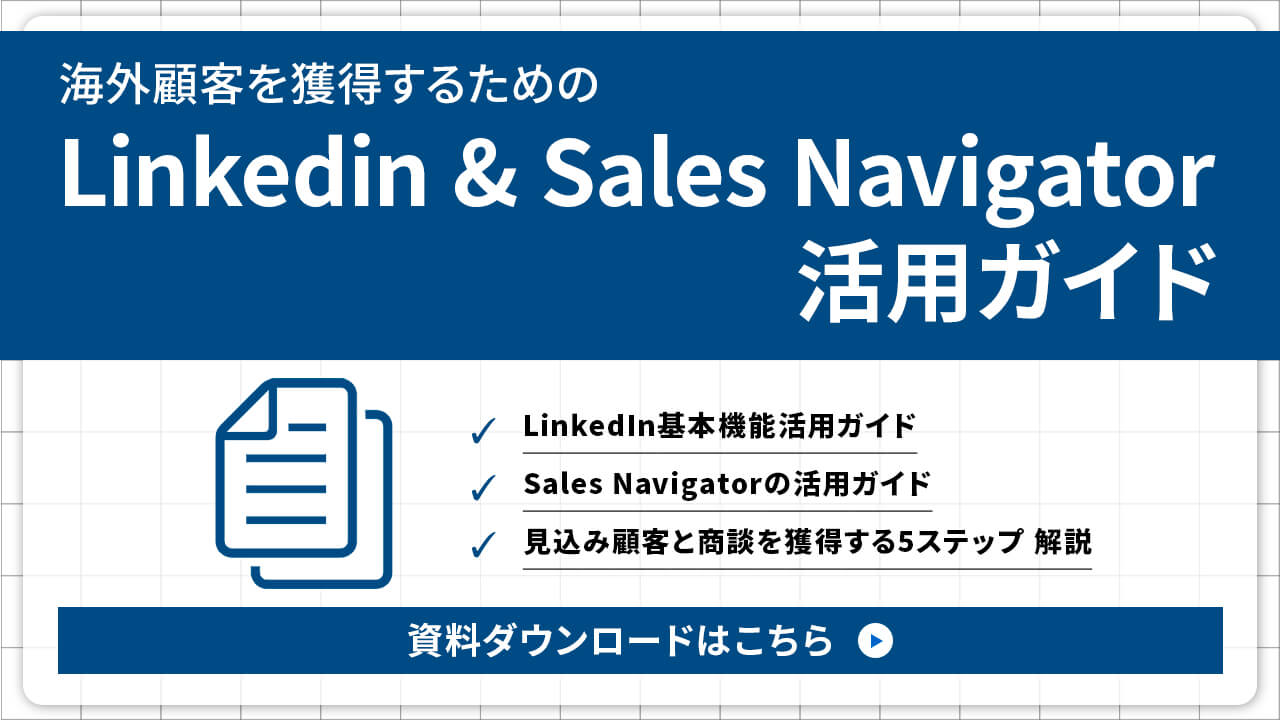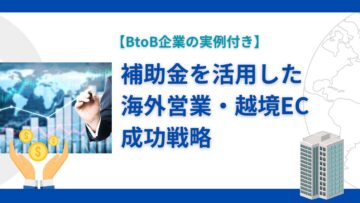“新規輸出1万者支援プログラム”で始める海外営業|製造業の成功事例と活用ガイド【2025年版】
1.「新規輸出1万者支援プログラム」とは?

中小製造業の輸出スタートを後押しする国の支援策
「新規輸出1万者支援プログラム」は、2022年12月に始まった中小企業向けの輸出支援施策です。経済産業省・中小企業庁・ジェトロ・中小機構などが連携し、初めて輸出に挑戦する企業に対して登録から支援メニューの提案、実行までをワンストップで支援します。対象は、製造業や食品、伝統産業など幅広く、特に地方の中小製造業が多く活用しています。特徴は、ジェトロの専門家による個別カウンセリングを起点とし、企業の状況や商材に合わせた多様な支援策(補助金、商社マッチング、越境EC支援など)を段階的に受けられる点です。輸出の準備から実行、改善までを伴走支援する体制が整っており、実績も着実に積み上がっています。
どんな支援が受けられる?専門家・補助金・商談サポートの全体像
本プログラムで提供される支援は、ジェトロによる輸出相談、商社・バイヤーとのマッチング、中小機構による補助金支援、越境ECモール出展支援など多岐にわたります。例えば、販促資料や海外向けパッケージ作成には「ものづくり補助金グローバル枠」が、販路開拓には「ジェトロの商談支援」や「地域展示会出展補助」などが用意されています。また、英語での商談練習や、貿易実務のサポートも実施。単に資金を支給するだけでなく、企業のフェーズに応じて伴走型で支援が設計されている点が大きな特長です。特に製造業では、BtoB型の営業活動や製品改良支援が現地展開の成否を分ける要素となります。
登録企業が“政策加点”の対象にも!他制度との連動効果
「新規輸出1万者支援プログラム」に登録した企業は、他の補助金制度でも“政策加点”が適用される可能性があります。たとえば「ものづくり補助金」や「持続化補助金」などの審査において、当プログラムの登録がプラス評価されるケースがあります。これは国が輸出志向の企業を重点的に支援していく方針を明確にしているためです。また、インボイス制度対応の支援や、中堅企業向けの海外展開加速補助金との併用も可能で、複数制度をまたいで活用することにより、輸出に向けた社内体制の整備と初期投資を同時に進められます。補助金単体よりも制度全体の組み合わせで成果が出やすい設計になっています。 </p>
2.支援対象と申請の流れをわかりやすく解説

対象は「輸出未経験または初心者」の中小企業
本制度の主な対象は、「これまで輸出の実績がない」「過去に輸出はあったが本格展開は初めて」といった中小企業です。業種は製造業を中心に、食品、伝統工芸、日用品など幅広く対応しており、特に地場産業を抱える地域の企業が多く利用しています。輸出先の国も自由に選定可能で、アジア圏や欧米など、企業の製品特性に合わせたターゲット設計ができます。また、輸出専任担当者がいなくても支援が受けられるため、営業や開発担当が兼任するような少人数体制の企業でも、制度を活用して一歩を踏み出すことが可能です。既に全国で5,000社以上が登録しており、製造業の参加比率も高いのが特徴です。
登録から支援メニュー提案までのステップとは?
支援を受けるには、まず専用ポータルサイトから企業情報を登録することから始まります。登録後、ジェトロの専門家が1対1で個別カウンセリングを実施し、製品や販路、課題などをヒアリング。その結果に基づき、企業ごとに最適な支援施策を複数提案されます。例えば「越境ECに挑戦したい」企業にはモール出展支援、「展示会に出たい」企業には補助付きの出展枠、「海外との商談が初めて」な企業には商社マッチングと事前トレーニング支援などが紹介されます。このように、単に登録するだけでなく、実行段階に移れるサポートまでがセットになっているのが本制度の大きな強みです。
相談・マッチングは無料!気軽に始められる理由
制度のもう一つの魅力は、登録から相談、メニュー提案までがすべて無料である点です。事前相談で費用が発生することはなく、輸出を検討している段階でも気軽に参加可能です。さらに、全国の商工会議所・商工会・中小機構の地域支援センターが相談窓口となっており、地元で支援を受けられる仕組みが整っています。マッチングにかかる商社の選定や、バイヤーとの商談会セッティングも支援対象に含まれており、1社では難しい営業活動をプロの力で効率化できます。初期投資のリスクを最小限に抑えながら海外営業を始めたい製造業にとって、非常に導入しやすい制度設計となっています。
3.実際の製造業の成功事例(公的資料ベース)
前田農産食品:電子レンジポップコーンが米国向け輸出へ

北海道十勝の前田農産食品(本別町)は、国産トウモロコシを使用した電子レンジ対応ポップコーンの製造販売を行う中小企業です。2023年に新規輸出1万者支援プログラムに登録し、ジェトロの支援を受けながら米国市場向けの展開を開始しました。特にAmazon.comへの越境EC出品支援を活用し、現地の食品安全規制への対応やパッケージ改良を行いました。また、北海道経済産業局の資料によると、地元自治体や他機関とも連携し、PR支援や商談練習も実施。結果として、米国販売を本格化する体制が整い、年間20万個の販売を目標とするプロジェクトが動き出しました。地方の農産加工業が、国の支援を活用して北米市場に挑戦した好例として紹介されています。
ひらかわ牧場:アイスクリームで初案件500万円超見込み

北海道のひらかわ牧場は、牛乳・乳製品の地産地消を重視した小規模酪農事業者で、自社製のアイスクリームを製造・販売しています。2023年2月に本プログラムへ登録し、ジェトロや中小機構の支援により輸出に初挑戦。輸出対象国はシンガポールで、現地バイヤーとのマッチングを通じて、初回輸出案件として約515万円の成約見込みを得ました。実際の商談に先立ち、専門家による輸出仕様の見直しや価格設計のアドバイスも実施され、品質や供給体制の信頼性が評価されたと報告されています。現在も継続して交渉が進められており、単発で終わらない長期的な輸出体制構築を目指しています。地方からでも地道な支援活用で海外に到達できることを証明した事例です。
成功の共通点は「支援メニューを掛け合わせた営業戦略」
上記の成功事例に共通して見られるのは、「単一の支援ではなく、複数の支援策を組み合わせて成果につなげている点」です。例えば、製品開発には補助金(ものづくり補助金)、商談準備には専門家の個別指導、販路開拓にはジェトロのマッチングや展示会支援を活用しています。また、単なる製品販売にとどまらず、現地ニーズに合わせたパッケージ変更や価格調整なども行っており、現場での柔軟な対応力が成功の決め手となっています。これにより、「テスト輸出」→「販路確保」→「事業としての確立」という段階的な成長が可能になっており、支援制度を最大限活用した営業戦略の好例といえます。
4.プログラムを活用した海外営業のはじめ方【製造業向け】

展示会頼みから脱却する“営業のデジタル化”の第一歩
これまで中小製造業の海外営業といえば、海外展示会や現地代理店への依存が一般的でした。しかしパンデミック以降、デジタルを活用した営業手法が急速に浸透しています。新規輸出1万者支援プログラムでは、ジェトロや中小機構の支援を通じて、越境ECモールへの出品支援や、Zoomを活用したオンライン商談、SNSを活用した情報発信方法まで幅広くカバー。地元にいながらにして、海外バイヤーとの接点を持てる仕組みが整っています。従来のように高額な渡航費をかけることなく、デジタル営業に慣れる機会を得られるのは、展示会偏重の脱却を考える製造業にとって大きな価値があります。特にニッチ製品やBtoB商材を扱う企業にとっては、ターゲット精度の高い営業が可能になります。
補助金×専門家支援×ツール活用のベストバランスとは
制度を活用するうえで最も効果的なのが、「補助金支援」「専門家の伴走」「デジタルツールの活用」という三要素を組み合わせたアプローチです。たとえば、ものづくり補助金のグローバル市場開拓枠を使えば、英語カタログやパッケージ、販促動画制作の費用を補助できます。そこに輸出支援専門家によるフィードバックを加えれば、より市場にフィットした改善が可能になります。また、LinkedInや越境ECモール(Amazon、Alibabaなど)を併用することで、海外の潜在顧客と継続的な接点を築くことができます。これらの支援を並列ではなく「掛け合わせて活用」することで、単なる資金支援にとどまらない、戦略的な海外営業が実現できるのです。
まずやるべきこと:登録・相談・ターゲット国の設定
制度をうまく活用するには、何よりもまず「登録」から始めることが重要です。ポータルに登録するだけで、輸出支援の第一歩が踏み出せます。次に、ジェトロのカウンセリングを通じて、自社の商材や体制に合った課題の洗い出しと支援策の提案を受けます。そして重要なのが、ターゲット国と顧客像の設定です。やみくもに海外に売るのではなく、「どの国の誰に、どうやって届けるか」を明確にすることで、支援メニューの選定や営業施策がより効果的になります。補助金申請やEC出展、商談会への応募などはその後のアクションとして整備されています。最初のステップを明確にし、段階的に取り組めば、中小製造業でも現実的に海外営業が実行可能です。
監修者紹介
中島 嘉一 代表取締役
SNSリンク:https://linktr.ee/nakajima
株式会社コスパ・テクノロジーズ 代表取締役。
愛媛大学情報工学部卒業後、船井電機にて中国駐在し5,000人規模の組織管理とウォルマート向け海外営業を担当。
上海で起業し通算10年の中国ビジネス経験を持つ。Web制作・デジタルマーケティング歴13年以上で現在は英語圏・中華圏を中心とした海外展開支援のスペシャリストとして活動。
多言語Webサイト構築、越境EC、SNS・広告運用を駆使して企業の海外顧客開拓から、国内向けWebサイト制作・ブランディングまで、戦略立案から実行まで一貫サポート。
海外ビジネスに関するセミナーやイベントに登壇するほか、SNS総フォロワー5万人以上、中小機構海外販路開拓アドバイザーとして中小企業から上場企業まで幅広く支援実績を持つ。