現地行かずに“脳内出張”!LinkedInと無料ツールで始める海外市場調査
目次
1. なぜ展示会だけではダメなのか?海外市場調査の見落としがちな落とし穴

展示会では“未来の市場”は見えにくい?
多くの日本企業が海外市場調査を展示会に頼っているのは、現地の反応を“肌で感じられる”という安心感があるからでしょう。けれども、展示会で得られる情報は基本的に「見せたい側」の情報であり、出展企業のマーケティング戦略や選定意図に左右されます。さらに、年に一度しか開催されないイベントでは、タイムラグも避けられません。市場は日々動いています。展示会だけに頼っていると、気づいたときには競合に先を越されていた、ということも起こり得るのです。現地に行かずともリアルタイムで情報収集できる手段を知っているかどうかが、今後の営業戦略を左右します。
“今”の声はどこで拾える?現地目線が抜けがちな落とし穴
日本から遠く離れた国や地域のニーズや変化を的確につかむには、現地にいる人たちの“今の声”を拾うことが不可欠です。たとえば、インドネシアで注目されている技術や、タイで起きている法規制の動きなどは、グローバルニュースやレポートには載っていないことが多いのが実情です。また、多くの企業が「現地代理店の声」に頼りがちですが、それも商業的バイアスがかかることが多く、客観的な視点とは限りません。大事なのは、生の声をできるだけ加工されずに拾うこと。LinkedInをはじめとするSNSでは、現地の担当者が投稿する悩みや提案内容に、ヒントが潜んでいます。
“足で稼ぐ”から“指で探す”時代へ
かつては営業も市場調査も「足で稼ぐ」ことが重要とされてきました。しかしデジタル環境が整った現在では、「指で探す」方が、圧倒的に早く、正確で、コストも抑えられるようになりました。特にLinkedInは、BtoB分野における実名・実業務ベースの情報が飛び交うため、観察しているだけで市場の構造や人材の動きが把握できます。展示会のように1回きりではなく、日常的に「現地の今」を観察し続けられるという点で、LinkedInは営業ツールであると同時に、優れた市場調査プラットフォームでもあります。調査の概念を更新すれば、あなたの営業活動も変わっていきます。
2. 無料でここまでできる!LinkedInとツールを使った海外市場調査の技術

LinkedInの検索機能で“誰が何をしているか”を炙り出す
LinkedIn(リンクトイン)の強力な点は、「実名・実職業」でユーザーが登録していることです。検索機能を使えば、ある業種の中で、どの企業に、どんな肩書の人がどれだけいるのか、簡単に可視化できます。例えば「ベトナム 医療機器」で検索すれば、現地の流通業者、調達担当者、営業責任者などが一覧で表示され、そこからトレンドや組織構造の特徴まで見えてきます。これを継続的に追うことで、「どの業界が採用を増やしているか」「どんなスキルが重視されているか」といった深い洞察も可能になります。検索は営業アプローチだけでなく、市場理解のための“データ収集”手段でもあるのです。
投稿とニュースレターで“現地の会話”に耳をすます
LinkedIn上での投稿やニュースレターは、まさに“現地のビジネスパーソンのつぶやき”です。たとえば、東南アジアの物流業界のキーマンが、「今月から輸入ルールが変わって混乱している」と投稿していれば、それはリアルタイムの市場の痛点です。これを日本にいながらにして拾えるというのは、大きなアドバンテージです。さらにニュースレターに登録しておけば、特定の業界や地域のトピックが定期的にメールで届くため、自動的に情報が集まってくる仕組みも構築できます。現地の言葉がわからなくても、英語や翻訳ツールを駆使することで、調査可能な範囲は大きく広がります。
他の無料ツールと組み合わせて“脳内出張”を加速する
LinkedInだけでなく、Google Trends、SimilarWeb、Statista、輸出入統計などの無料リサーチツールと組み合わせることで、より立体的な市場理解が可能になります。例えば、「某国で“脱プラ”が話題」とLinkedInで気づいたら、Google Trendsで検索数の推移をチェックし、Statistaで市場規模の推計を探し、さらにSimilarWebで競合の流入元を分析する、という流れが自然にできます。これらを自分で組み合わせていくことは、まさに“脳内出張”です。物理的に現地にいなくても、立体的に市場を“感じる”ことで、感度の高い仮説や提案に結びつけることができます。
3. 実際に声を聞く!LinkedInを活用したリサーチ型コミュニケーション術

“調査目的”と明かすことで、返信率が上がることもある
LinkedInで見つけた現地の専門家に直接DMを送るとき、「営業です」ではなく「市場調査のために知見を伺いたい」というスタンスを取ると、意外にも返信が得られやすくなります。これは、「売り込みではない」ことが明確だからです。リサーチ目的のメッセージは、相手にとっても負担が少なく、協力する心理的ハードルも低くなります。もちろん最初から売り込むことが目的ではない場合でも、結果的に会話の中でニーズが見えることもあります。つまり、リサーチ=営業の前段階という意識を持ち、慎重に信頼関係を築いていくアプローチが、海外営業には適しているのです。
声を聞くときは“背景理解”を示すことで信頼を得られる
海外の相手に質問する際は、「あなたの投稿を読みました」「御社のプロジェクトを拝見しました」といった一言を添えることで、相手の心証は大きく変わります。ただ質問をぶつけるのではなく、背景理解を示すことで、「この人はきちんと調べている」「単なるスパムではない」と思ってもらえるのです。さらに、LinkedInでは共通のつながりが表示されるため、「〇〇さんとつながっている方ですね」といった一言も距離感を縮める材料になります。つまり、リサーチメッセージは、情報収集の手段であると同時に、信頼構築の第一歩でもあるのです。
ヒアリングすべき“3つの質問”で得られるインサイトは想像以上
実際に返信が来て会話が始まった場合、どんな質問をすればよいか迷う方も多いかもしれません。おすすめは次の3つです。「1)現地で最近話題になっていることは何ですか?」「2)この業界で課題に感じていることは?」「3)御社の今後の注力分野は?」この3つの質問だけでも、現地での温度感、課題感、ニーズの方向性が見えてきます。そしてこの情報は、そのまま提案や営業トークに反映できます。つまり、ヒアリングは単なる調査ではなく、“売れる言葉”をつくるためのネタ収集でもあるのです。海外市場調査と営業は分断されるものではなく、むしろ繋がっているのだと意識することが重要です。
4. まとめ|“情報収集型営業”こそ海外展開の起点になる

“調べる力”は、現地に行かずとも成果を左右する武器になる
これまで「海外営業=現地に飛ぶ」が常識とされてきましたが、今ではその前に“調べる力”を身につけることの方が重要になっています。現地に行けば確かにリアルな空気感を得られますが、それは準備があってこそ活きるもの。調査なしに訪問しても、相手の課題や関心が見えず、結果的に「何しに来たの?」と思われてしまうケースもあります。今はLinkedInや各種無料ツールを駆使すれば、日本にいながらでもターゲット市場の構造やトレンドを把握できます。つまり、「行く前に知っておく」「話す前に調べておく」という姿勢が、これからの海外営業においては信頼を勝ち取るための大前提になるのです。
LinkedInは“観察”から使うのが海外市場調査の第一歩
多くの人がLinkedIn(リンクトイン)を「営業DMを送るツール」として見ていますが、最初からつながろうとするのではなく、まず“観察する”ことから始めるのが本当の活用法です。市場調査に役立つヒントは、投稿やプロフィール、企業ページなどあらゆる場所に散りばめられており、それらを読み込むことで、商談に至る前から仮説を立てることができます。たとえば、「この業界では〇〇という役職が意思決定権を持っている」「最近△△に注力する企業が増えている」といった情報は、調査しない限り見えてきません。LinkedInは“攻め”のツールであると同時に、“観察と戦略設計”のための基盤でもあるのです。
海外市場調査と営業活動はもう切り離せない時代へ
かつては「調査はマーケティング部門、営業は現場」と分けて考えられていましたが、海外営業ではこの境界が完全に崩れつつあります。むしろ、“調べながら売る”ことができる営業が、成果を上げています。なぜなら、海外の市場や文化、商習慣は日本と大きく異なるため、調査と営業が一体になっていないと、相手に刺さる提案ができないからです。LinkedInをはじめとするデジタルツールは、このギャップを埋める手段として非常に有効であり、今や武器を持たない営業は戦えません。情報収集と営業を分けて考えるのではなく、調査そのものが営業活動の一部であるという意識を持つことが、海外展開においての新常識です。
監修者紹介
中島 嘉一 代表取締役
SNSリンク:https://linktr.ee/nakajima
株式会社コスパ・テクノロジーズ 代表取締役。
愛媛大学情報工学部卒業後、船井電機にて中国駐在し5,000人規模の組織管理とウォルマート向け海外営業を担当。
上海で起業し通算10年の中国ビジネス経験を持つ。Web制作・デジタルマーケティング歴13年以上で現在は英語圏・中華圏を中心とした海外展開支援のスペシャリストとして活動。
多言語Webサイト構築、越境EC、SNS・広告運用を駆使して企業の海外顧客開拓から、国内向けWebサイト制作・ブランディングまで、戦略立案から実行まで一貫サポート。
海外ビジネスに関するセミナーやイベントに登壇するほか、SNS総フォロワー5万人以上、中小機構海外販路開拓アドバイザーとして中小企業から上場企業まで幅広く支援実績を持つ。
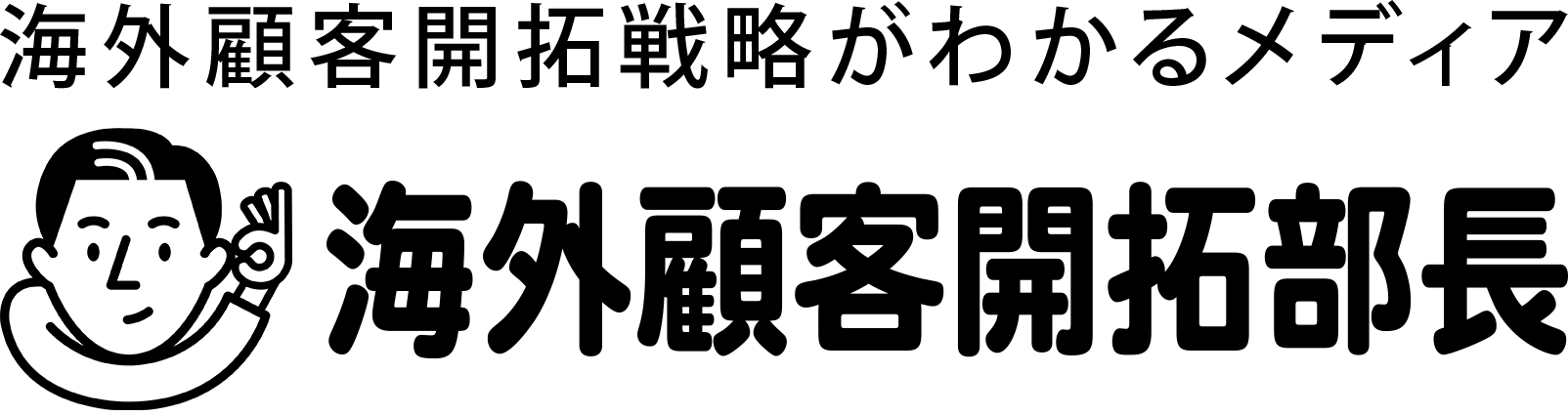
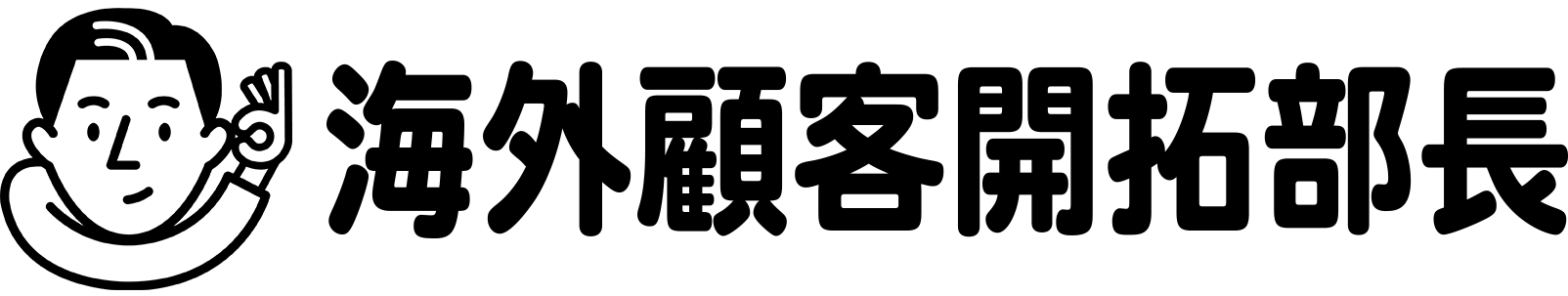
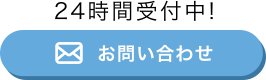
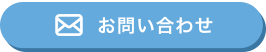


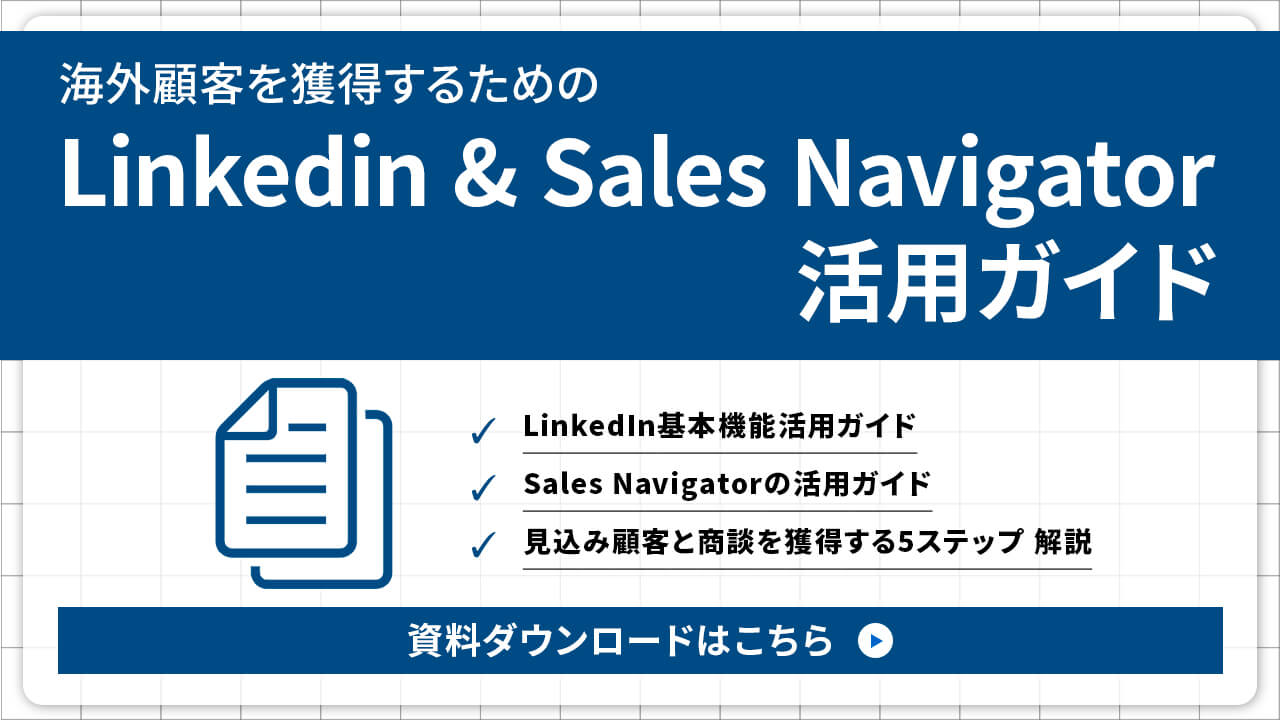

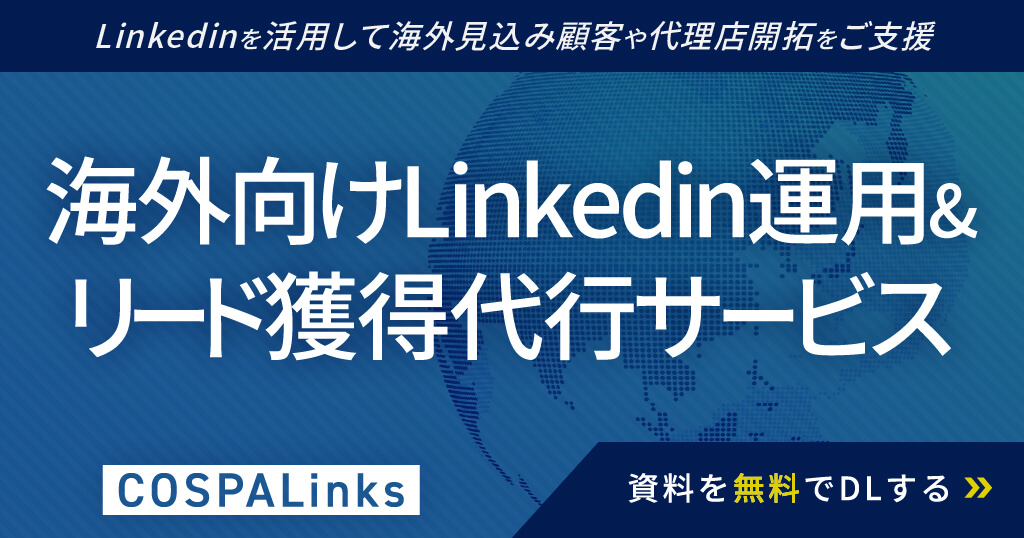
とWhatsApp(ワッツアップ)-60x60.jpg)







-360x203.jpg)




