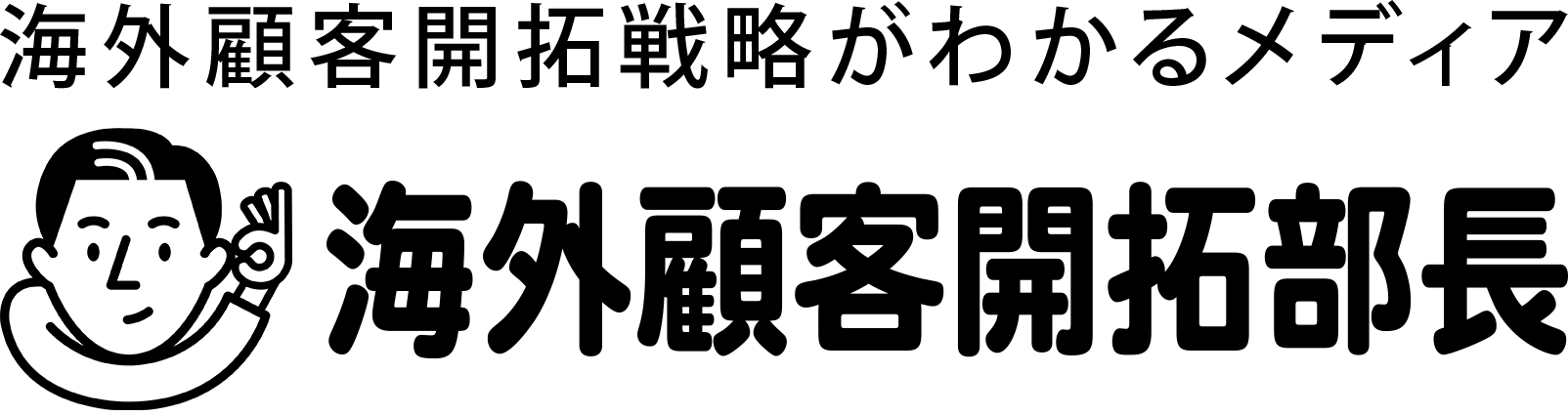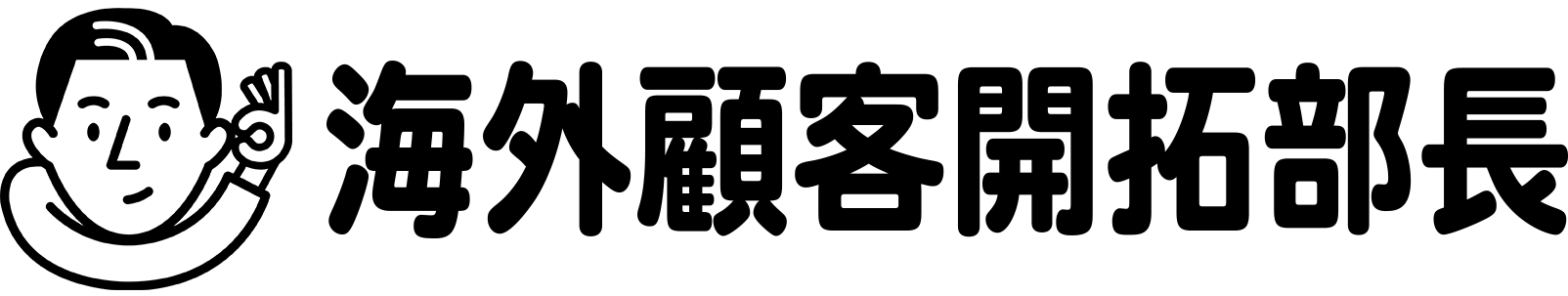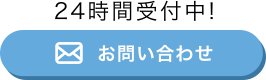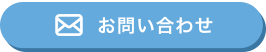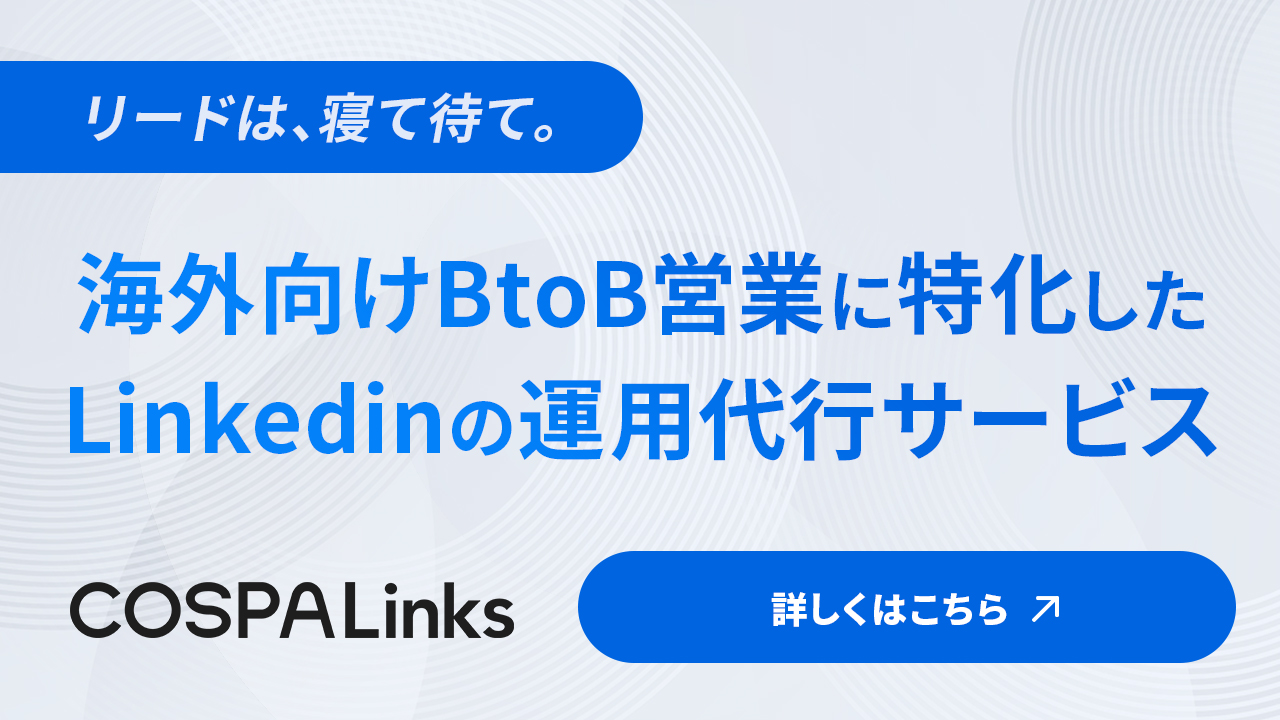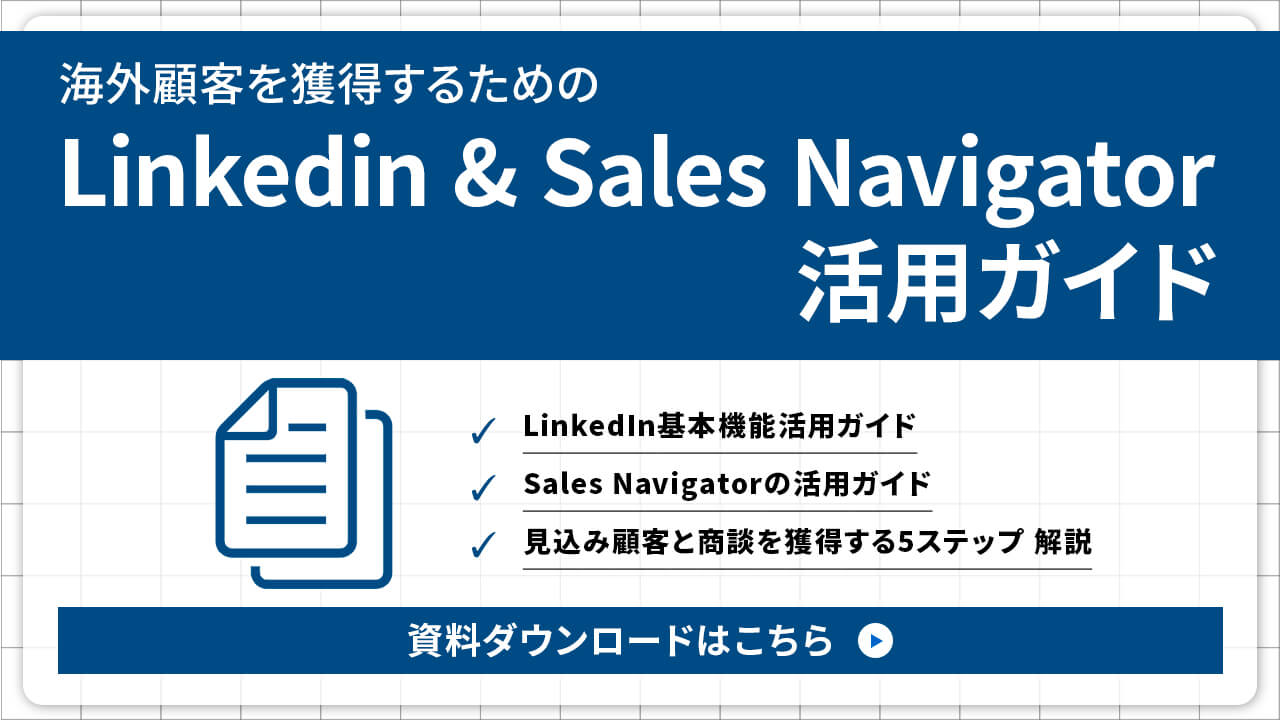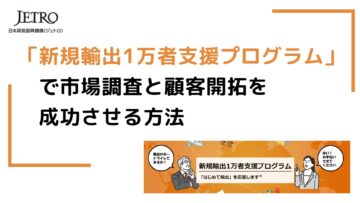なぜスシローは台湾で行列、日本では苦戦?文化ギャップ営業の教訓
目次
1. 実は“行列の名店”だった?スシローは台湾で大成功していた!
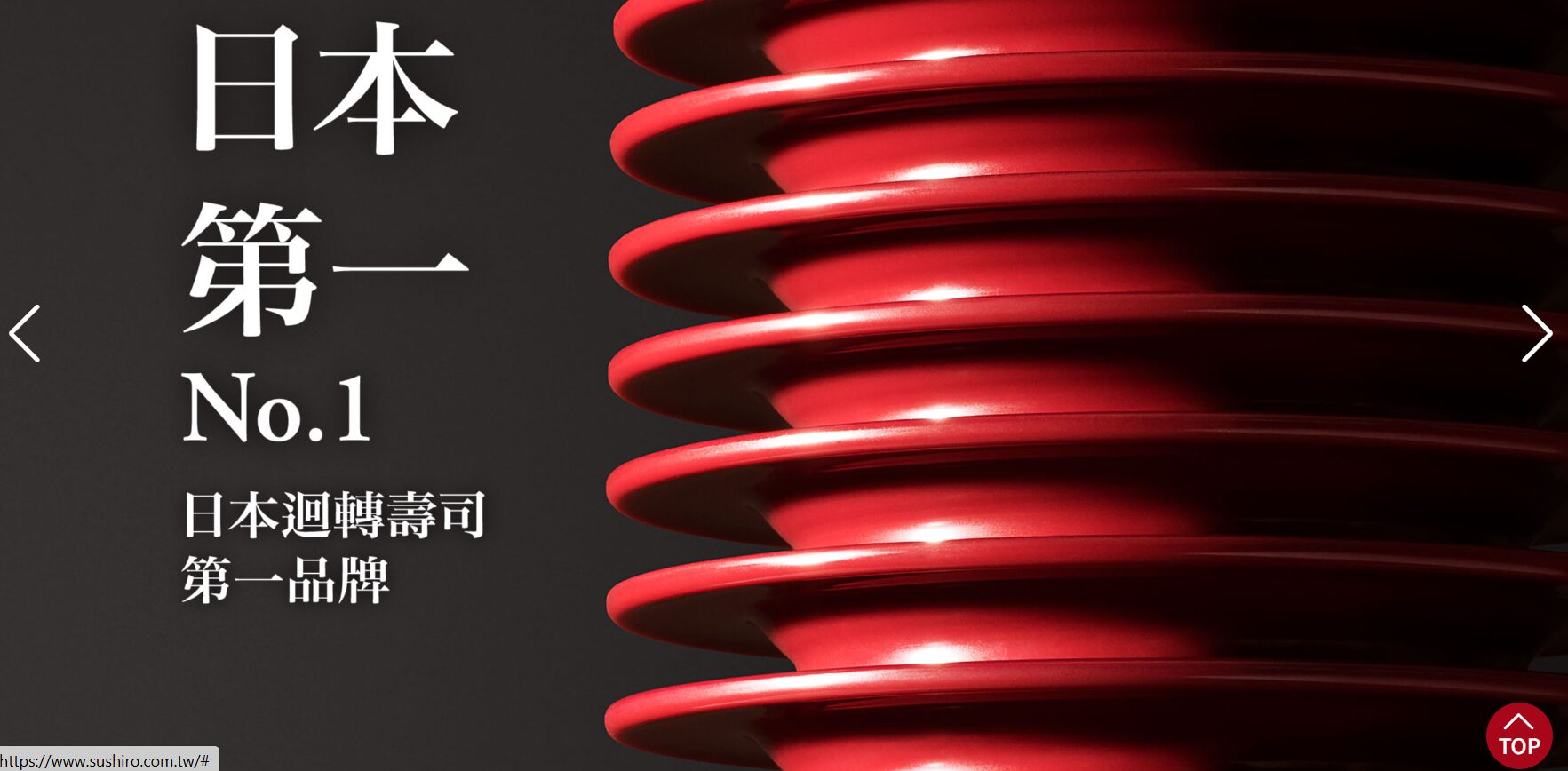
台湾ではなぜここまで人気?現地メディアも驚いたスシローブーム
台湾でのスシローの人気は、現地のメディアでも「行列が絶えない日系レストラン」としてたびたび取り上げられるほど。2018年に1号店を開業して以降、台北・新北を中心に積極的に出店し、開店初日から数時間待ちの長蛇の列ができることも珍しくありません。台湾の消費者にとって、スシローは“高級感のある日常的な体験”として受け入れられています。日本での回転寿司の印象とは異なり、ブランドがもつ「日本品質」「寿司専門店」のイメージが強く、また店内のインテリアや接客も“日本らしさ”を意識して設計されており、ちょっとした観光感覚で楽しめる存在になっているのです。
リーズナブル+エンタメ性が“体験価値”として支持された
台湾のスシローでは、価格帯は現地水準でみれば中価格帯ですが、「この品質でこの価格なら満足度が高い」という評価を得ています。さらに、注文タブレットやレーン演出、当たり付きのキャンペーンなど、“楽しめる仕掛け”が豊富で、食事がエンタメ体験に昇華されているのも人気の理由です。台湾は外食文化が根強く、日常的に食事をSNSでシェアする習慣があるため、「映える」「話題になる」要素が強い店舗ほど拡散されやすい傾向にあります。スシローはまさにこのニーズに合致し、自然とクチコミが広がっていった結果、“行列してでも行きたい店”としてのブランドポジションを確立しています。
日本企業の“空気営業”と違う、現地目線での売り方とは
スシロー台湾の成功には、現地パートナー企業との密な連携と、徹底したマーケットイン志向がありました。つまり、日本本社の売り方をそのまま押し付けるのではなく、「台湾の消費者が何を求めているのか?」という視点から企画や接客が組み立てられているのです。たとえば味付けの微調整や人気メニューのローカライズ、店舗での顧客動線の最適化など、“現場発”の改善が日常的に行われています。海外営業においても、この「現地起点の発想」は極めて重要です。日本の企業が陥りがちな「売りたいものをそのまま持っていく」スタイルではなく、相手の期待に応える姿勢が、現地での信頼とブランド構築につながる好例といえるでしょう。
2. 日本での苦戦に見る、営業戦略の落とし穴

国内市場での“価格競争”とブランド疲弊
一方の日本市場では、スシローは長年業界トップを走るものの、近年は「価格勝負」に巻き込まれ、ブランド価値の維持に苦しんでいます。競合との値下げ合戦、原材料高騰、顧客の飽きなどが重なり、経営も迷走気味に。ここから見える海外営業への教訓は、単なる価格訴求だけでは“選ばれ続けるブランド”にはなれないという点です。海外顧客開拓でも、値段の安さで初回購入されても、価値が伝わらなければ継続取引にはつながりません。日本でのスシローの状況は、「価値訴求を後回しにした営業の末路」という、海外営業にも通じる教訓を示しているのです。
同じ商品でも「伝え方」で印象は変わる
スシローの寿司は、台湾でも日本でも同じ品質・同じネタを使っています。ではなぜ評価が大きく分かれるのでしょうか。その理由は、“どう伝えたか”にあります。台湾では「日本文化体験」として演出された寿司が、日本では「安い・早い・回る寿司」として処理されている。この差はそのまま海外営業の方法論に置き換えることができます。営業が商品のスペックだけを語っても、顧客は魅力を感じません。相手が価値を感じる言葉で伝えること、つまりローカライズされた営業資料や文化に配慮した営業トークが不可欠なのです。同じ製品でも、見せ方・語り方ひとつで全く違う結果を生むことがあるのです。
外国人観光客と日本人顧客の“期待値ギャップ”
インバウンド観光客の間では、日本のスシローも“本場の寿司体験”として人気です。ところが日本人消費者は、日常使いで“コスパ”を重視するため、同じサービスにも厳しい目を向けます。この“期待値ギャップ”は、海外営業においても軽視できません。ターゲット国の期待値と現地文化を把握せずに営業をかけると、せっかくの商談もミスマッチで終わる可能性があるのです。海外顧客開拓では、現地の競合製品との比較、商習慣、購買決定プロセスなどの調査を事前に行い、“相手が求めている基準”を理解することが極めて重要です。スシローの日本と台湾での評価の違いは、その期待値の把握がいかに営業戦略を左右するかを物語っています。
3. スシローから学ぶ海外営業のコツと教訓
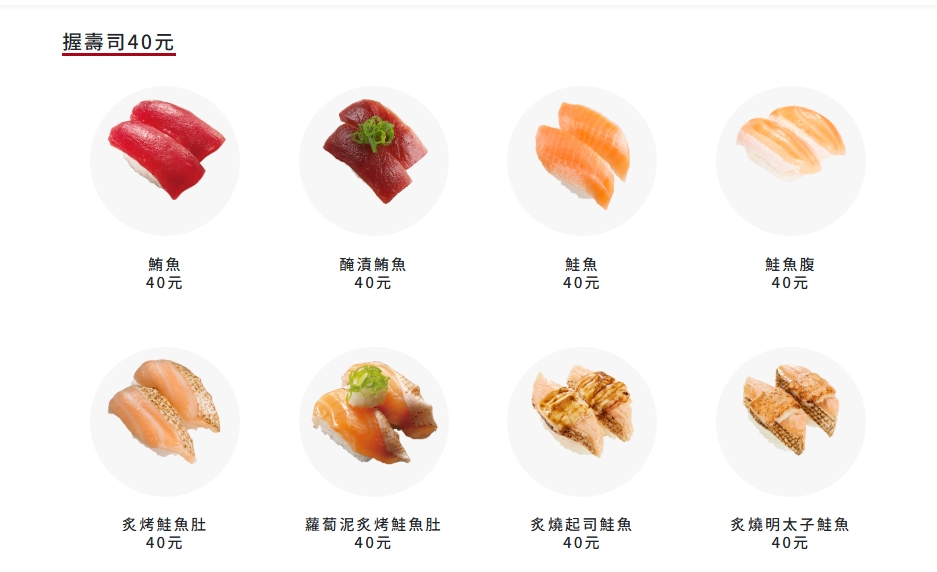
海外営業で必要な“文化視点”の重要性
スシローが台湾市場で成功を収めた背景には、「文化の違いを理解し、それに合わせた営業戦略を取った」ことが挙げられます。これはまさに、海外営業戦略を立てる上での基本中の基本です。たとえば、日本の「早くて安い」を武器にした回転寿司文化は、台湾では「日本体験」「信頼のブランド」として求められます。このように、同じ製品でも文化背景によって評価軸は変わるため、営業担当者は「何が価値とされるか」を国ごとに再定義しなければなりません。文化視点を欠いた海外営業は、相手に刺さらないどころか、誤解や信頼損失を招くリスクもあるのです。成功する海外営業のコツは、製品ではなく「価値の再翻訳」にあると言えるでしょう。
商品ではなく“体験”を売るBtoB営業とは
台湾のスシローは、ただ寿司を売るのではなく「日本の食文化を体験できる場」を提供してきました。これはBtoBの海外営業でも応用できる発想です。たとえば製造業が海外に設備を売る際、単にスペックや価格を伝えるだけでなく、「どう活用すれば現地企業の生産性が上がるか」「自社の技術が現地の課題をどう解決するか」といった、体験ベースの提案が重要になります。海外顧客は、製品そのものではなく、「導入後の変化」を見ています。つまり、営業の仕事は“製品のスペック紹介”ではなく、“未来のストーリーを語ること”。体験価値を設計・言語化することが、海外営業の方法として差がつくポイントになります。
現地ユーザーの声を営業戦略に活かす方法
スシロー台湾では、開店後も継続的に現地ユーザーの声を拾い、商品の味付けや接客スタイル、キャンペーン施策を柔軟に変えています。これは海外顧客開拓においても非常に有効なアプローチです。特にBtoBの世界では、一度の受注で終わらず、継続的な関係構築がカギとなります。そのためには、納品後のフィードバックをきちんと収集し、次の提案や改善に活かす姿勢が求められます。海外営業のコツは「売るまで」ではなく「売った後」を見据えること。顧客の声を営業戦略のサイクルに組み込むことで、他社には真似できない信頼関係を築くことができ、次の紹介や大型契約につながっていきます。
4. まとめ:文化ギャップをチャンスに変える海外営業戦略へ

「違い」を活かす営業アプローチの設計
文化の違いは、しばしば「障壁」として捉えられがちです。しかし、視点を変えればそれは営業戦略上の“差別化ポイント”になり得ます。たとえば、スシローは台湾市場において、日本と台湾の食文化や購買行動の違いを理解し、それを逆手に取って価値提供の仕方を変えました。これは海外営業戦略にもそのまま応用できます。国ごとに文化や商習慣が異なるのは当たり前。だからこそ、違いに敏感である営業チームが、相手国の課題や期待を深く理解し、それに沿った提案を行うことで、他社との差別化が可能になります。「違いに合わせる」のではなく、「違いを活かす」視点を持つことが、現代の海外営業では重要なのです。
営業とマーケティングの“現地化”を進めるには
スシロー台湾の成功は、商品だけでなく「売り方」と「伝え方」まで現地化したことが要因です。海外営業においても、商品パンフレットや営業資料をただ英訳するのではなく、現地文化や業界トレンドを反映させたメッセージに“翻訳”する必要があります。これはマーケティングと営業の連携が不可欠であり、情報共有や現地の声を反映した施策設計が鍵となります。特にBtoB領域では、営業部門が集めたフィードバックをもとに、次のアプローチやプロモーションを共同で構築していくスタイルが有効です。「現地の課題をどう解決するか」を軸に据えた海外営業の方法こそ、継続的な信頼と成果を生む基本戦略になります。
海外営業の成否は「翻訳力」より“翻心力”
最後に、スシローの台湾展開から最も学べることは、言葉やパンフレットの翻訳ではなく、「心を翻訳する力」が営業には求められているということです。たとえば同じ製品でも、なぜ必要なのか、どんな課題を解決するのか、それを現地の言葉で、現地の立場から語る“翻心力”があって初めて信頼は生まれます。これは、単に語学力ではなく、相手の文化や価値観への共感力、そしてリサーチ力の結晶です。今後、海外顧客開拓で成果を上げるには、この翻心力を育てることが必須となるでしょう。海外営業のコツは、“売る力”ではなく“伝える力”。文化の壁を越えるのではなく、その壁を使って橋をかける発想が、成果を左右する時代です。
監修者紹介
中島 嘉一 代表取締役
SNSリンク:https://linktr.ee/nakajima
株式会社コスパ・テクノロジーズ 代表取締役。
愛媛大学情報工学部卒業後、船井電機にて中国駐在し5,000人規模の組織管理とウォルマート向け海外営業を担当。
上海で起業し通算10年の中国ビジネス経験を持つ。Web制作・デジタルマーケティング歴13年以上で現在は英語圏・中華圏を中心とした海外展開支援のスペシャリストとして活動。
多言語Webサイト構築、越境EC、SNS・広告運用を駆使して企業の海外顧客開拓から、国内向けWebサイト制作・ブランディングまで、戦略立案から実行まで一貫サポート。
海外ビジネスに関するセミナーやイベントに登壇するほか、SNS総フォロワー5万人以上、中小機構海外販路開拓アドバイザーとして中小企業から上場企業まで幅広く支援実績を持つ。