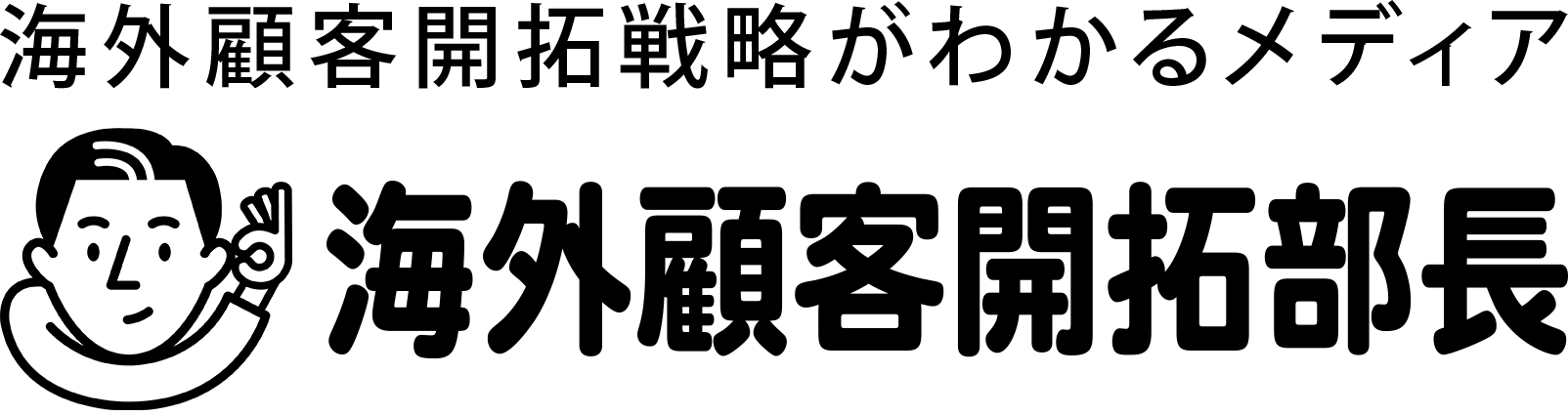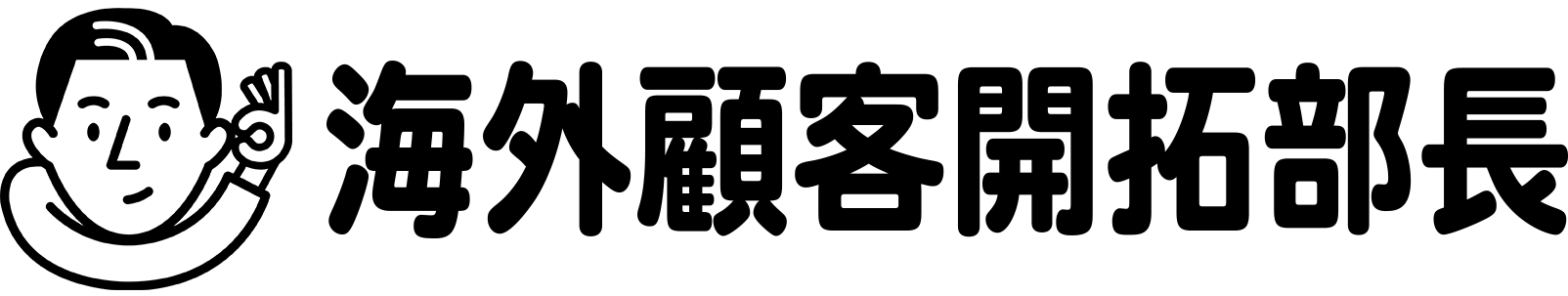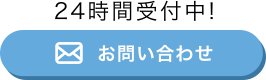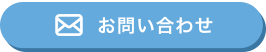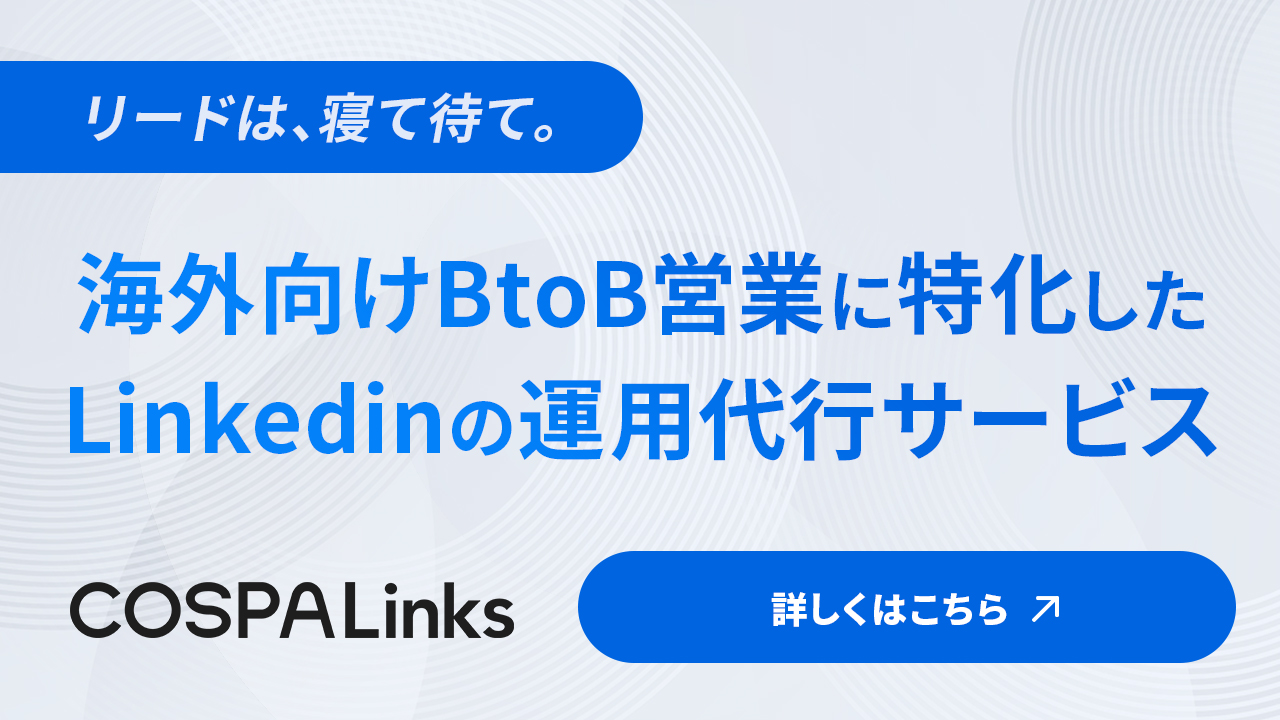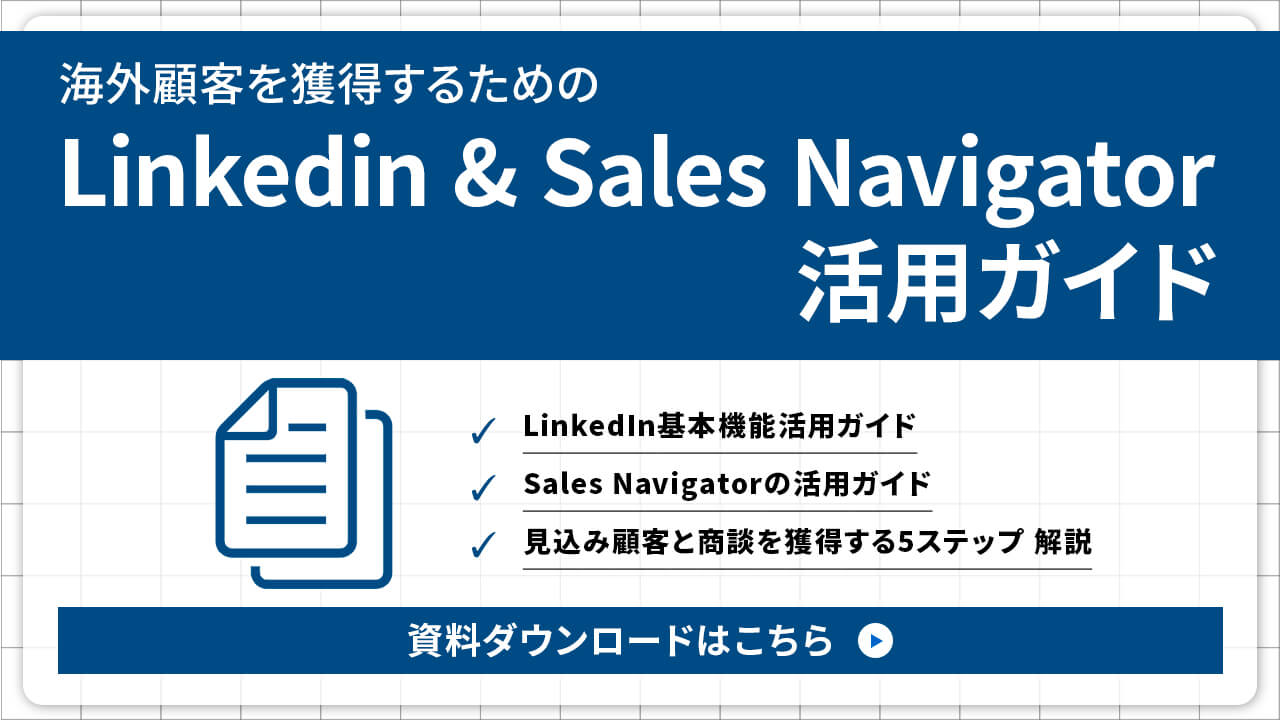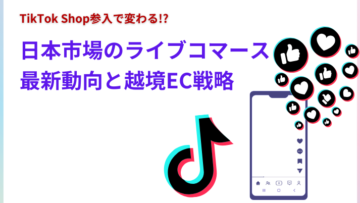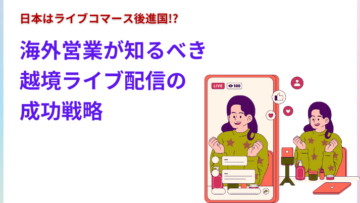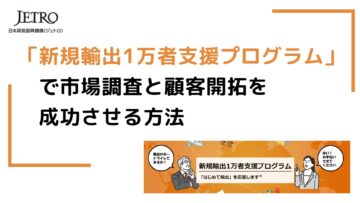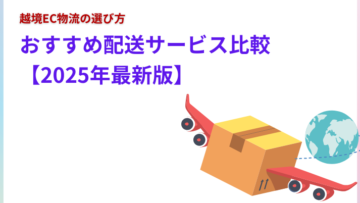【実例で解説】越境EC成功事例5選|海外営業担当者が知るべき勝ちパターンとは
目次
はじめに|なぜ今、越境ECの成功事例を知るべきなのか

円安・物価高騰と国内市場縮小リスク
近年、円安や物価高騰の影響を受け、日本国内市場は縮小傾向にあります。消費者の購買力低下により、内需依存型ビジネスは成長が難しくなりつつあります。こうした環境下で、成長機会を求めて海外市場へ目を向ける企業が増えています。特に初期投資を抑え、手軽に海外市場にチャレンジできる越境ECは、中小企業にとって非常に有効な選択肢となっています。円安による価格競争力の向上も追い風となり、今こそ国内依存から脱却し、新たな成長市場へ挑戦すべきタイミングです。
越境ECの需要増加と海外営業の重要性
世界的にEC市場は拡大を続けており、特にアジア圏や北米では日本製品に対する需要も高まっています。こうした追い風の中、越境ECを活用する企業が急増しており、海外営業の重要性も一段と高まっています。単に製品を売るだけではなく、現地ニーズに合わせた戦略、文化理解、迅速な顧客対応が求められます。越境ECと海外営業を連携させることで、持続的な売上拡大が可能になります。海外営業担当者にとって、今、越境ECを軸に据えた戦略構築が急務になっています。
成功事例に学ぶメリットとは
成功企業の越境EC事例には、再現可能な「勝ちパターン」が多く存在します。先行事例を学ぶことで、自社展開時の失敗リスクを減らし、成功確率を高めることができます。また、具体的な施策や運営方法を知ることで、自社の強みをどう生かすかのヒントを得ることができます。越境ECの世界では、スピード感と柔軟な対応力が成否を分けます。成功事例を研究し、自社に最適な越境EC戦略を描くことが、これからの海外営業活動のカギを握ります。
1. ヤーマン|ライブコマース活用で中国市場を席巻

ライブコマース戦略のポイント
ヤーマンは、中国市場攻略にあたり、Tmall Globalを中心とした越境EC展開にライブコマースを戦略的に組み込みました。リアルな商品紹介を通じて、ターゲット層とのエンゲージメントを深め、商品理解を高めることに成功しています。ライブ配信は単なる宣伝ではなく、商品の使い方や効果を体験的に伝える手法として活用され、顧客の信頼獲得に大きく貢献しました。越境ECでは、いかに現地消費者とリアルタイムで接点を持つかが鍵となります。ヤーマンの取り組みは、海外営業活動にも応用できる貴重な事例です。
KOL(インフルエンサー)との連携方法
ヤーマンは、現地中国で影響力を持つKOL(キーオピニオンリーダー)と積極的に連携し、ライブ配信を通じて商品の魅力を効果的に訴求しました。単独で発信するのではなく、消費者に身近な存在を通じて情報発信することで、親近感と信頼感を高めることに成功しています。これにより、単なる広告よりも高い成約率を実現しました。海外営業担当者にとって、現地に影響力を持つパートナーを巻き込む戦略は、越境EC成功の大きなヒントになります。
中国市場での売上拡大につながった要因
ヤーマンの中国市場成功の背景には、単なる販売活動だけではない、現地市場の徹底した理解があります。中国特有の美容トレンドを把握し、それに合わせた製品ラインナップを展開。また、アフターサービスの現地化にも力を入れ、顧客満足度向上を図りました。これにより、ライブコマース経由の売上だけでなく、リピーター獲得にも成功。海外営業では、単なる「売る」だけでなく、顧客体験全体を設計する重要性が示されています。
2. Fake Food Japan|食品サンプルを世界へ

ニッチ商品の越境EC成功パターン
Fake Food Japanは、日本独自の文化である食品サンプルを活かして、越境EC市場に成功しました。海外では食品サンプルがレストラン装飾やユニークギフトとして需要があり、特に欧米市場で人気を獲得しています。単なる製品販売にとどまらず、「日本のリアルさ」「クラフトマンシップ」というストーリーを発信。越境ECでは、ニッチ市場に特化し、文化的背景をコンテンツとして訴求することが、差別化とファン獲得につながることを示しています。海外営業担当者にとって、商品の「ストーリー化」は不可欠な視点です。
海外マーケット向け商品展開の工夫
Fake Food Japanは、海外顧客向けに製品サイズや価格帯を細かく最適化しました。ギフト用途を意識した小型サンプルの開発や、パッケージデザインの多言語対応も徹底。単なる日本市場向け商品の輸出ではなく、「現地市場に合わせた商品リニューアル」を実践しました。さらに、ターゲット国ごとの消費文化や贈答習慣をリサーチし、マーケティング施策をカスタマイズ。海外営業担当にとっては、現地ニーズへの柔軟な適応が、越境EC成功への鍵であると改めて気づかされる事例です。
SNS活用による認知度向上施策
Fake Food Japanは、InstagramやPinterestなど、ビジュアル重視のSNSを活用して商品の拡散を図りました。食品サンプルのリアルな見た目は、SNS映えしやすく、オーガニックリーチを自然に増やす効果がありました。広告に頼らず、ユーザー投稿型の拡散を促したことで、海外でのブランド認知を効率よく拡大。SNS運用においても、国別にハッシュタグや投稿時間を最適化する細かな工夫を怠らず、成果につなげています。海外営業でも「SNSでの世界観構築」は重要な武器となります。
3. GLOKEN|けん玉で世界に広がるコミュニティ戦略
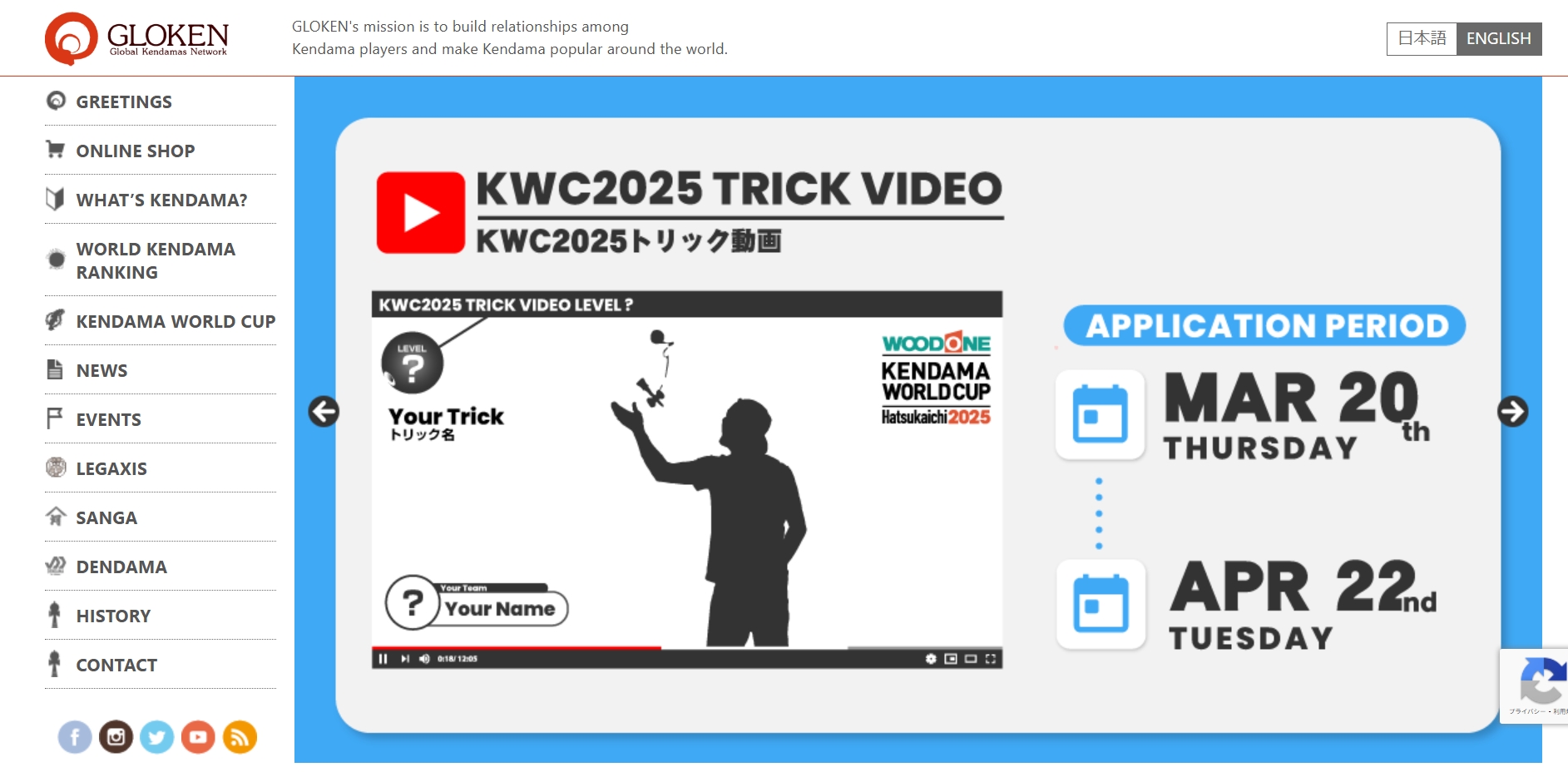
物販+体験型イベントの融合モデル
GLOKENは、けん玉の普及と越境EC販売を連動させた独自モデルを構築しました。越境ECサイトで販売するだけでなく、けん玉ワールドカップ(KWC)を主催し、世界中のファン同士が交流できるイベントを開催。商品単体ではなく「体験」としてけん玉を届けることで、エモーショナルなブランド構築に成功しました。このように、単なる物販に留まらず、体験設計を重視する姿勢は、今後の海外営業においても非常に重要な視点と言えます。ファンベース作りが越境EC成功のカギとなります。
Shopify活用による越境ECサイト運営
GLOKENは、世界対応に優れたShopifyを活用し、多言語・多通貨に対応した越境ECサイトを運営しています。サイト設計では、商品情報だけでなく、けん玉の歴史や遊び方に関するコンテンツも充実させ、顧客の興味を喚起。さらに、SEO対策にも注力し、国別に最適化されたコンテンツを提供することで、自然検索流入を拡大しました。海外営業担当者にとって、ただモノを売るのではなく、コンテンツとストーリーを掛け合わせたサイト運営が成否を分けることを示しています。
コミュニティ形成が売上拡大に貢献した理由
GLOKENの越境EC成功には、コミュニティ戦略が大きな役割を果たしました。世界中のけん玉ファンをオンライン・オフラインイベントで結び付けることで、リピート率とLTV(顧客生涯価値)を飛躍的に高めました。単発販売ではなく「仲間意識」を醸成することで、自然な口コミ拡大やリピーター獲得につながっています。海外営業でも、単なるBtoB取引だけでなく「エモーショナルな関係性づくり」を重視する時代に入っています。GLOKENの事例はその最前線を示しています。
4. 多慶屋|訪日外国人から越境ECリピーターへ
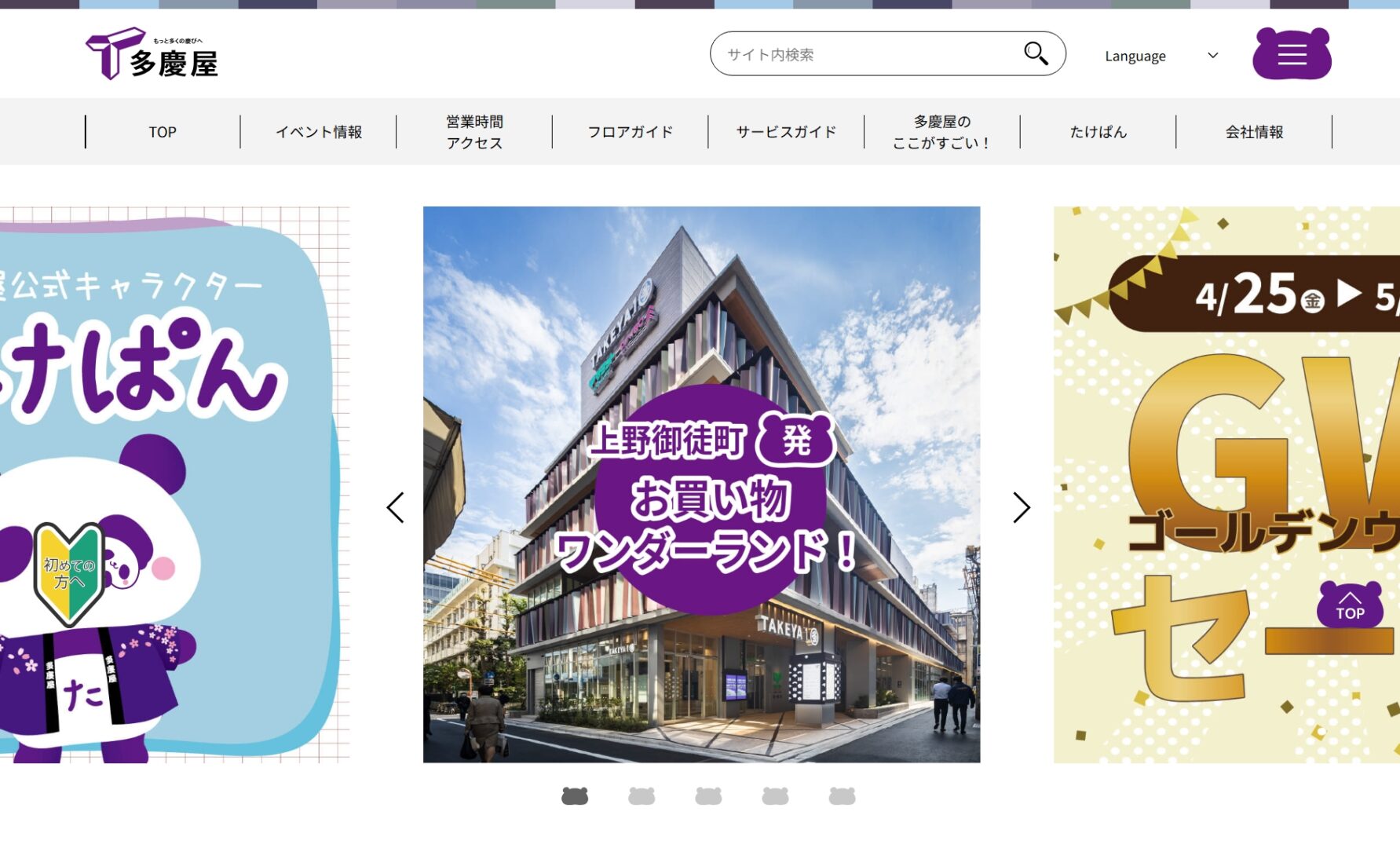
実店舗と越境ECの連携モデル
多慶屋は、訪日外国人観光客を対象に、実店舗と越境ECを連携させる新しいビジネスモデルを構築しました。実店舗で購入した顧客に、帰国後も専用ECサイトから同商品を簡単にリピート購入できる仕組みを提供。これにより、訪日中の購入体験を起点に、越境EC売上の持続的な拡大に成功しました。海外営業担当者にとって、オフライン接点を越境ECに引き継ぐ導線設計の重要性がわかる実践例です。リアルとデジタルの融合が今後の営業活動に欠かせません。
訪日中に種まき、帰国後に収穫する仕組み
多慶屋では、店頭でQRコード入りの越境EC案内チラシを配布し、顧客に自然な形で帰国後利用を促しています。訪日中に種まき(購入体験とブランド印象形成)を行い、帰国後に収穫(ECでのリピート購入)する設計思想が見事に機能しています。さらに、決済手段や配送サービスも国別に最適化し、顧客満足度向上を徹底。海外営業でも、現地顧客の行動変容を見越したアフターフォロー体制を整えることが、リピーター育成に直結します。
QRコード活用施策とその効果
多慶屋は、店舗で配布するチラシにQRコードを組み込み、スマホ一つで越境ECサイトにアクセスできる導線を設計しました。この手軽さが、帰国後のリピート購買率を大きく押し上げる要因となりました。特に中国市場では、QRコード決済やAlipay対応により、スムーズな購入体験を提供。こうしたデジタル導線最適化は、越境ECだけでなく、海外営業活動全体に応用可能な成功パターンです。現地文化に合わせた「使いやすさ設計」は成果を大きく左右します。
5. SAMURAI STORE|日本文化を武器に世界展開

甲冑・刀剣という独自商品を武器に
SAMURAI STOREは、日本独自の文化財である甲冑・刀剣を世界に向けて販売し、越境ECで大きな成功を収めました。海外顧客にとっての「本物の日本文化」への憧れに応える商品構成と、ストーリー性の強いブランディング戦略が鍵です。単なるプロダクト売りではなく、「サムライ精神」や「伝統工芸」という文脈で商品価値を高めました。海外営業担当にとって、文化資産をビジネスに昇華する発想の重要性を示す好例です。
ECサイト設計と多言語・多通貨対応の工夫
SAMURAI STOREは、英語サイトだけでなく多言語対応を進め、各国通貨での決済にも柔軟に対応しました。GooglePayやPayPalなど、世界標準の決済手段を整備し、顧客の購入ハードルを徹底的に下げています。さらに、サイト自体のデザインも、日本らしさを演出しながらも海外ユーザーにとって操作性の良い設計を心がけました。越境ECでは、文化的コンテンツとグローバル標準の利便性を両立させることが成功への近道です。
海外メディア露出を活かしたブランド戦略
SAMURAI STOREは、ロサンゼルス・エンゼルスへの兜提供などを通じて、積極的に海外メディア露出を行いました。広告とは違い、文化交流の文脈で取り上げられることで、ブランド価値が自然に向上。これは単なるマーケティング活動ではなく、日本文化を世界に伝える「文化外交」に近い効果を生みました。海外営業担当者にとって、広告だけに頼らず、文化文脈でブランドを語る戦略の重要性を改めて認識できる事例です。
まとめ|越境EC成功事例に学び、海外営業を強化する

成功企業に共通する3つのポイント
今回紹介した越境EC成功事例には、いくつか共通点があります。第一に、現地市場のニーズに徹底的に適応していること。ヤーマンやFake Food Japanのように、単なる輸出ではなく、現地文化や購買行動に合わせた商品・プロモーションを展開しています。第二に、オンラインとリアル施策の連携です。多慶屋は訪日体験を越境ECリピートへつなげ、GLOKENは体験イベントと物販を融合。第三に、自社独自の文化資産をブランド価値に変換している点。SAMURAI STOREが好例で、日本文化を武器に世界市場で存在感を示しました。これらの共通点は、今後海外営業を強化するうえで極めて参考になります。
越境EC×海外営業のこれから
これからの越境ECと海外営業活動は、単なる「商品販売」から「市場開拓型営業」への進化が求められます。越境ECで市場ニーズを把握し、現地に合わせたプロモーションやカスタマーサクセス施策を展開することが重要です。さらに、リード獲得後はリアル営業との連携を強め、BtoBのパートナーシップ構築や代理店契約など多角展開を視野に入れるべきです。デジタル×リアルのハイブリッド戦略が、持続的成長の鍵となります。海外営業担当者は、越境ECを単なる販売チャネルと捉えず、「市場テスト」と「関係構築」の両面から活用する思考にシフトしていく必要があります。
小さな一歩がグローバル市場への扉を開く
越境ECは、大規模な投資を伴わずに世界市場にチャレンジできる手段です。しかし、最初から完璧な展開を目指す必要はありません。小さなターゲット市場、小ロットの商品からスタートし、トライ&エラーを重ねながら成長していく姿勢が重要です。実際に現地の声を拾い、柔軟に対応していくことで、競争力の高い海外営業体制を築くことが可能になります。リスクを恐れず、まずは小さな一歩を踏み出すこと。それが、将来のグローバル市場への大きな扉を開く第一歩となります。越境ECの可能性を信じて、一歩踏み出しましょう。
監修者紹介
中島 嘉一 代表取締役
SNSリンク:https://linktr.ee/nakajima
株式会社コスパ・テクノロジーズ 代表取締役。
愛媛大学情報工学部卒業後、船井電機にて中国駐在し5,000人規模の組織管理とウォルマート向け海外営業を担当。
上海で起業し通算10年の中国ビジネス経験を持つ。Web制作・デジタルマーケティング歴13年以上で現在は英語圏・中華圏を中心とした海外展開支援のスペシャリストとして活動。
多言語Webサイト構築、越境EC、SNS・広告運用を駆使して企業の海外顧客開拓から、国内向けWebサイト制作・ブランディングまで、戦略立案から実行まで一貫サポート。
海外ビジネスに関するセミナーやイベントに登壇するほか、SNS総フォロワー5万人以上、中小機構海外販路開拓アドバイザーとして中小企業から上場企業まで幅広く支援実績を持つ。