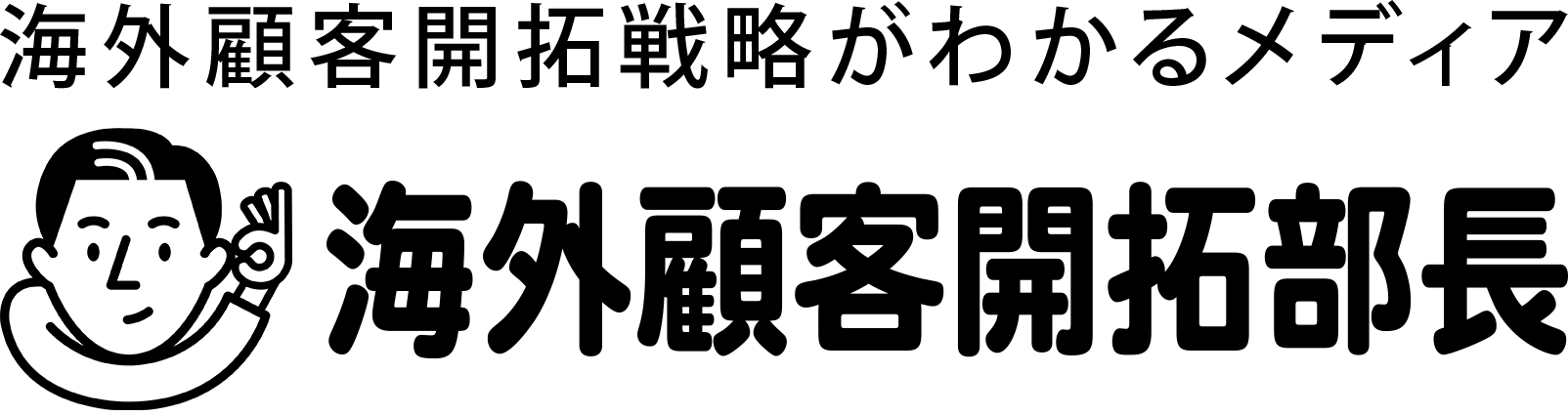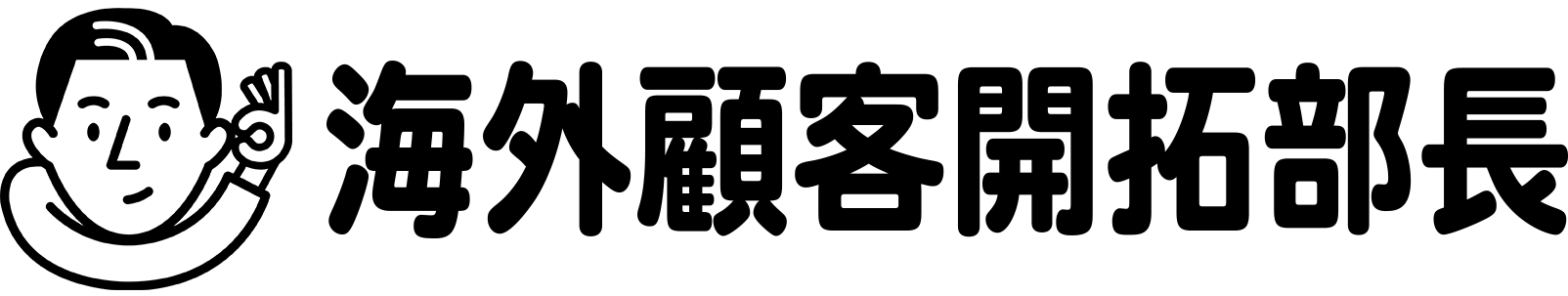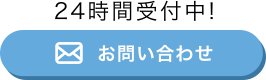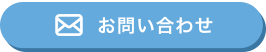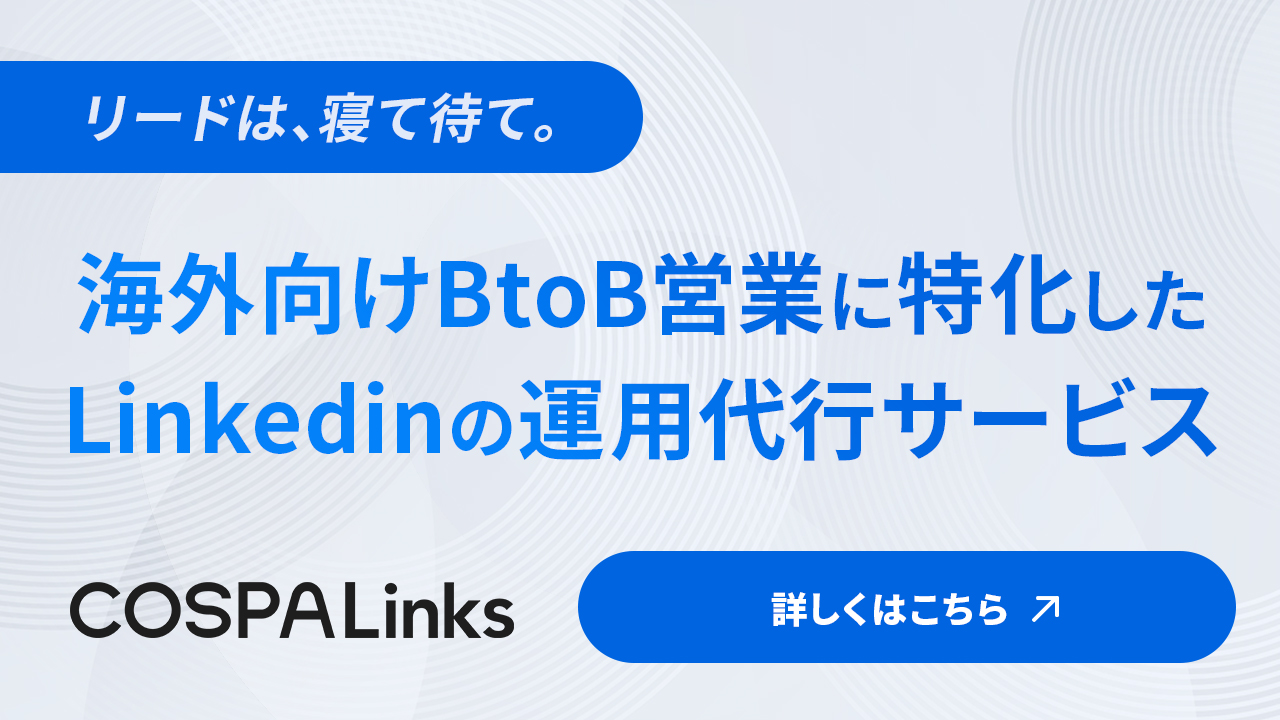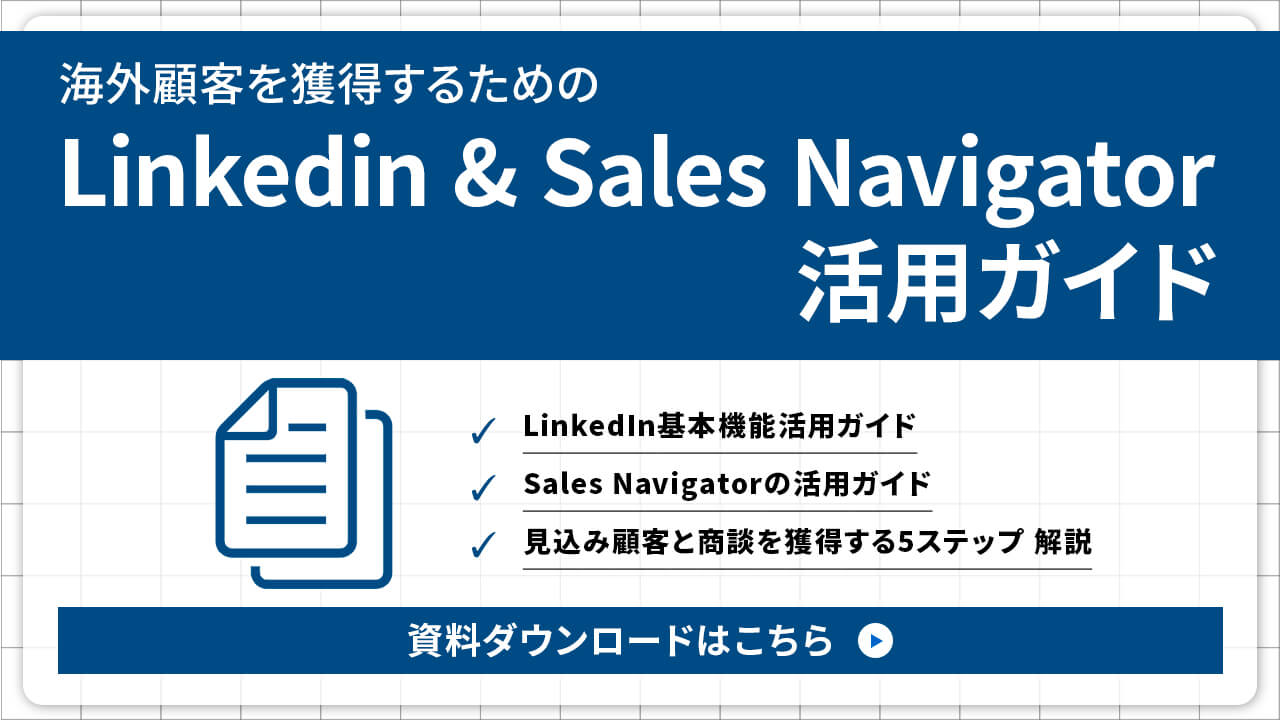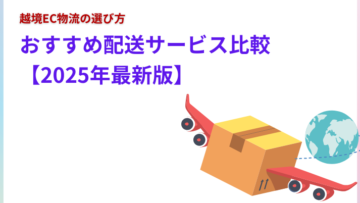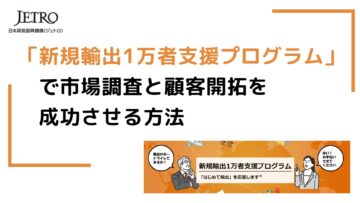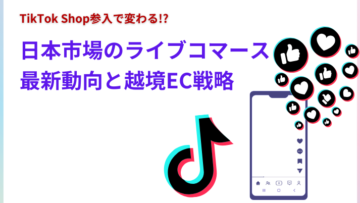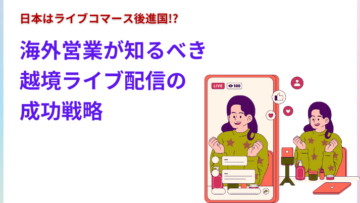越境ECは展示会より効果的?海外営業の成果を変える新常識とは
目次
1. なぜ今、展示会依存の海外営業に限界があるのか?

展示会=成功とは限らない?コストと成果のバランスを見直そう
多くのBtoB企業が海外営業の方法として展示会を重視してきました。しかし、出展コスト、渡航費、人件費などを総合すると、1回の出展で数百万円以上の投資が必要になることも珍しくありません。それに対し、得られるリードが「名刺交換だけ」で終わるケースも多く、費用対効果に疑問を抱く声が増えています。今求められているのは、投資対効果が明確で、継続的に改善可能な海外営業戦略への見直しです。
商談につながらない名刺はもう要らない?
展示会で獲得した名刺リストをもとに営業活動を行っても、なかなか商談につながらないと感じたことはありませんか?これは「その場のノリ」で交換された名刺が多く、真剣度の高い顧客が少ないことが原因のひとつです。海外営業における最大のコツは、興味・関心を持った見込み客とだけ向き合うこと。見込み度の低いリードに時間をかけるよりも、本気度の高いユーザーが集まるチャネルに注力すべき時代です。
コロナ以降、営業現場に起きた本当の変化とは?
パンデミックによって海外渡航が制限された数年間、多くの企業が「展示会なしでも営業ができる」ことに気づきました。それは、Web会議やオンラインマーケティングの活用、そして越境ECの導入です。この流れはコロナ明けの今も継続しており、展示会一辺倒だった営業方法を見直すきっかけとなりました。時代はすでに変わっています。今こそ、海外営業の手段を再定義する必要があります。
2. 越境ECが“営業成果を変える新常識”と言われる理由

越境ECは24時間働く“デジタル営業部隊”です
越境ECは単なる販売チャネルではなく、情報発信・信頼構築・問い合わせ獲得までを自動で行う「営業の仕組み」として機能します。製品情報や技術資料をきちんと整えておけば、営業担当が眠っている間にも海外の顧客がアクセスし、検討してくれます。これは展示会では不可能なアプローチであり、限られた営業リソースでも最大限の成果を出したい企業にとって、非常に理にかなった営業戦略の一部といえます。
買い手主導の時代に、越境ECはフィットしている
今や海外顧客は展示会で情報を得るよりも、検索やSNSで自ら情報収集を行う時代です。つまり「売り込み」よりも「探してもらう」設計が重要になっており、越境ECはまさにその受け皿として機能します。顧客が検索したときに出てくる商品ページ、丁寧に翻訳された導入事例、わかりやすい技術説明…これらが購買判断を促進します。海外営業戦略において、顧客の行動変化に合わせたチャネル設計は不可欠です。
リードを獲得し、商談へつなげる企業が増えています
越境ECを通じて、実際に新規の法人顧客と商談を始めているBtoB企業が増えています。特に日本の部品メーカーや加工業では、製品を丁寧に紹介し、問い合わせ対応を早めるだけで、海外企業から直接発注が入るケースも。リードの質も高く、検索を経てページにたどり着いたユーザーはニーズが明確なことが多いため、商談化率も高めです。これは従来の展示会や代理店営業では得られなかった成果です。
3. 越境ECと展示会、それぞれのメリット・デメリット比較

コスト・リーチ・継続性で見る両者の違いとは?
展示会は短期間で数百名と接点が持てる即効性が魅力ですが、費用が高額かつ一過性で終わりがちです。一方、越境ECは立ち上げに多少の準備は必要ですが、初期コストを抑えつつ長期的にリードを獲得できる点が強みです。また、展示会では地理的制約がありますが、越境ECでは世界中の顧客にアプローチ可能です。継続的な成果と営業効率を考えると、越境ECのほうが営業戦略として柔軟性が高いと言えるでしょう。
目的で使い分ける、展示会と越境ECの役割
展示会は新製品発表や現物を見せたい商材、または既存顧客への挨拶などに適しています。一方で越境ECは、ニッチなBtoB商材やスペック重視の商品を、ターゲットを絞ってじっくり届けたい場合に効果的です。つまり、営業手段としては二者択一ではなく「目的で使い分ける」のが正解です。今後の海外営業戦略では、展示会と越境ECをどのように組み合わせて活用するかが成果の分かれ目になります。
“掛け算型”戦略が成果を最大化させる
越境ECと展示会を連動させることで、相乗効果を生むことも可能です。たとえば展示会での名刺獲得後、フォローとして越境ECサイトのURLを案内すれば、後追いでの理解促進や見積もりにつながります。また、越境EC経由で得た問い合わせをリアル商談に転換することで、クロージングの確度を高めることもできます。デジタルとリアルを「分断」するのではなく、組み合わせることが新しい海外営業の常識です。
4. 越境ECを営業成果につなげるために必要な設計とは

営業視点で“売れるECサイト”を設計する
越境ECを運営する際、重要なのはマーケティング視点だけでなく「営業視点」を持つことです。単なる製品カタログではなく、「この商品で何が解決できるのか」「誰に向いているのか」といった提案型のコンテンツが必要です。さらに、導入事例やFAQの掲載、チャット対応など、見込み客の不安を解消する設計が、問い合わせ→商談化につながります。営業部門との連携こそ、成果を生む越境ECサイトの土台です。
問い合わせ対応こそが営業成果の分かれ道
海外からの問い合わせをどう対応するかで、その後の成果は大きく変わります。まず重要なのは、初回返信のスピード。24時間以内に返信することで、信頼感を得やすくなります。さらに、ただ情報を送るだけでなく、相手の目的をヒアリングし、課題に合わせた提案を行うことで商談につながります。海外営業の方法として、越境ECは“入り口”にすぎません。そこからの対応力が、成約率を左右します。
展示会にはない“改善できる営業チャネル”として活用を
越境ECの最大の強みは、すべての顧客接点が「数値」で見えることです。どのページに何人来たか、どの国からアクセスが多いか、どの商品がクリックされたか――こうしたデータを基に、改善を繰り返すことができます。これは展示会にはない利点です。つまり、越境ECは「試して、改善して、成果を伸ばす」営業チャネル。今後の海外営業戦略では、PDCAを回せる営業基盤があるかが成否を分けます。
5. まとめ|海外営業を“展示会だけ”にしない時代

海外営業の手段はもっと自由に、柔軟に
今や海外営業は展示会だけに頼る時代ではありません。越境ECをはじめ、Webサイト、SNS、ウェビナーなど、デジタルを活用した方法が次々と生まれています。だからこそ、自社にとって最適な“営業ポートフォリオ”を再設計することが求められています。重要なのは、すべてを入れ替えるのではなく、目的とコスト、リーチに応じて手段を組み合わせる柔軟さです。それがこれからの海外営業戦略の基本です。
小さく始めて、確実に成果を出す“営業設計”へ
越境ECは初期投資を抑えてスタートできるため、展示会に比べてリスクが低く、スモールスタートに最適です。最初は1商材・1国から始め、問い合わせ対応やアクセス分析を通じて、徐々に戦略を磨いていく形がおすすめです。社内の営業リソースと連携しながら、ECを“育てていく”という発想が、成果の出る運用につながります。まずはやってみる、そして改善する。その繰り返しが海外顧客開拓の近道です。
展示会と越境ECは、対立ではなく“補完関係”
越境ECと展示会、どちらか一方を選ぶ必要はありません。むしろ、どちらも営業活動の中で機能する「手段」であり、補完し合える関係です。展示会で得た名刺を越境ECでフォローし、越境ECで得た関心を展示会で深掘りする。そんな連携ができれば、海外営業はもっと成果が見える活動になります。今こそ、自社の営業活動を再設計するタイミング。越境ECという選択肢を、前向きに取り入れてみませんか?
監修者紹介
中島 嘉一 代表取締役
SNSリンク:https://linktr.ee/nakajima
株式会社コスパ・テクノロジーズ 代表取締役。
愛媛大学情報工学部卒業後、船井電機にて中国駐在し5,000人規模の組織管理とウォルマート向け海外営業を担当。
上海で起業し通算10年の中国ビジネス経験を持つ。Web制作・デジタルマーケティング歴13年以上で現在は英語圏・中華圏を中心とした海外展開支援のスペシャリストとして活動。
多言語Webサイト構築、越境EC、SNS・広告運用を駆使して企業の海外顧客開拓から、国内向けWebサイト制作・ブランディングまで、戦略立案から実行まで一貫サポート。
海外ビジネスに関するセミナーやイベントに登壇するほか、SNS総フォロワー5万人以上、中小機構海外販路開拓アドバイザーとして中小企業から上場企業まで幅広く支援実績を持つ。