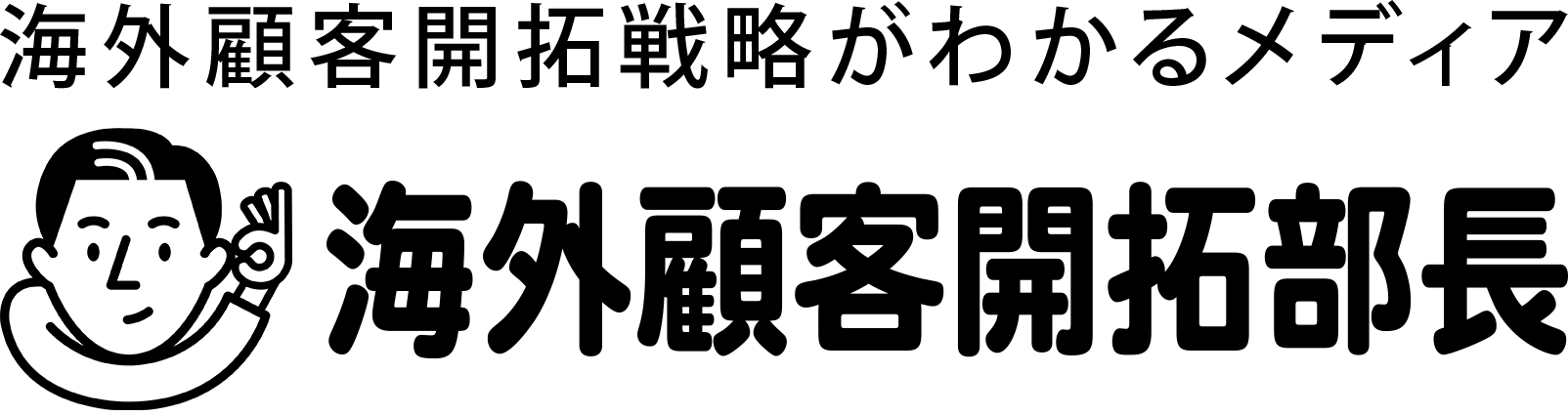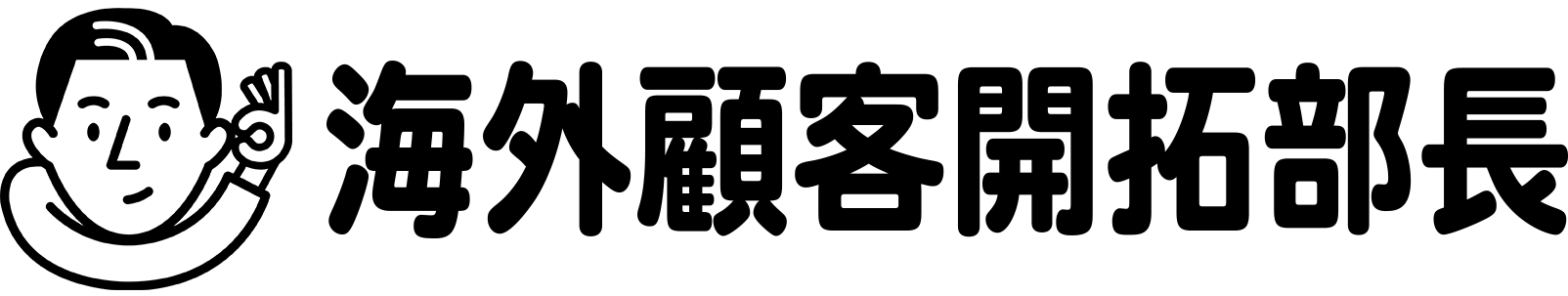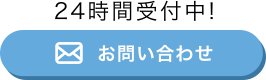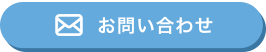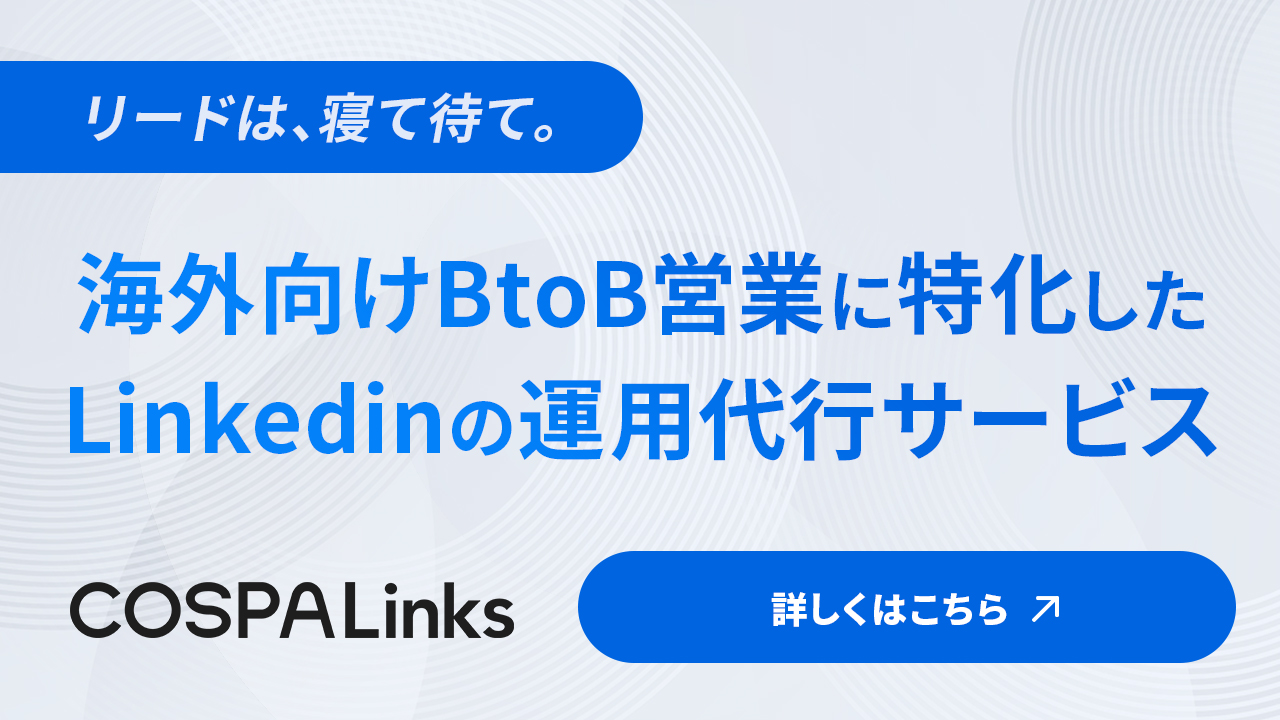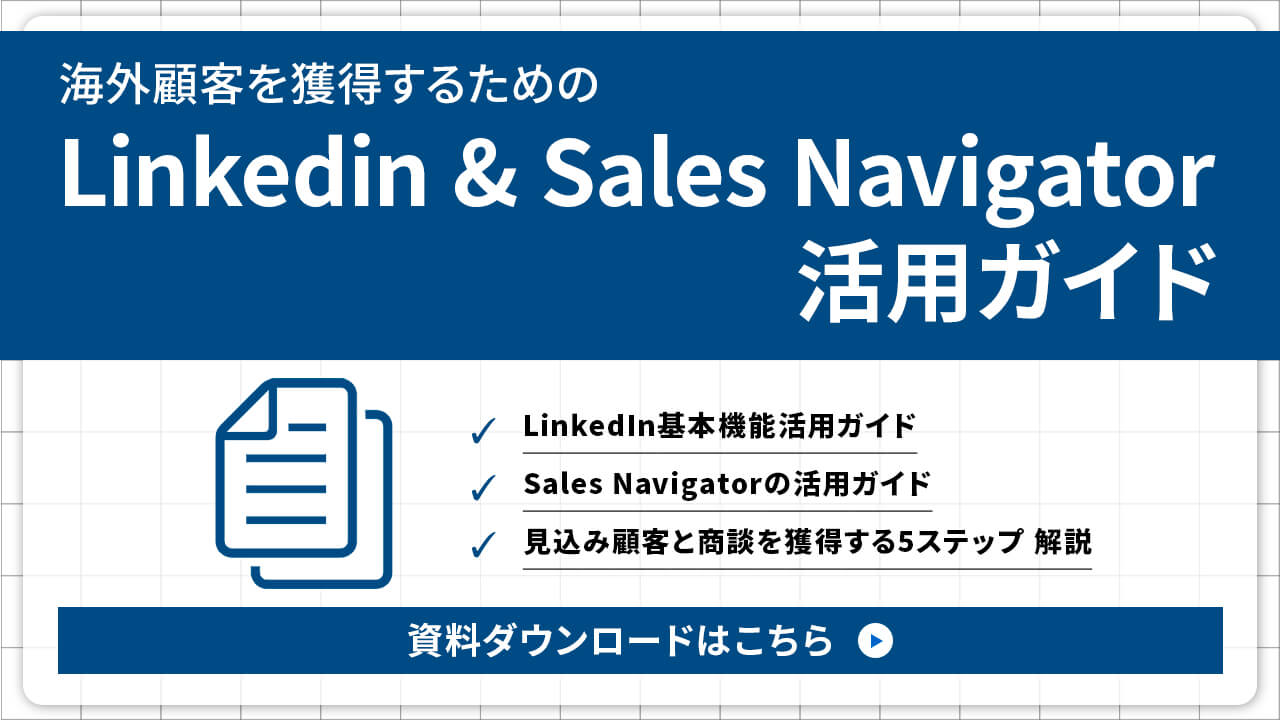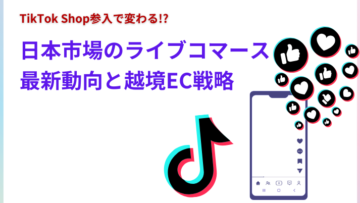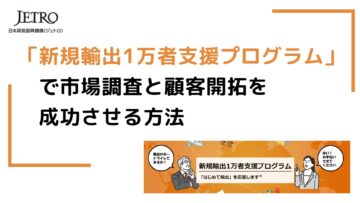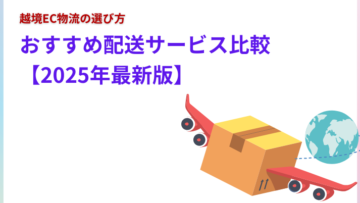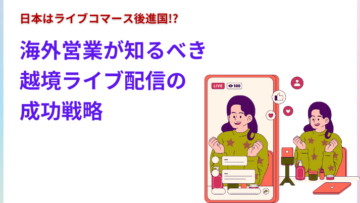越境ECの始め方を徹底解説!BtoB企業が海外販路を広げるための第一歩
目次
1. なぜ今、BtoB企業に越境ECが必要なのか?
展示会・代理店任せに限界。海外営業の新たな打ち手とは?
これまで多くのBtoB企業が海外販路の開拓手段として活用してきたのが、展示会出展や代理店営業です。しかしコストの高さや情報の属人化、時代に合わない営業スピードの遅さに課題を感じている企業も少なくありません。そんな中、注目されているのが越境ECです。越境ECは「見込み客に商品を探してもらう仕組み」であり、営業活動の効率化を実現します。特に人手不足や営業リソースに限界を感じている企業にとって、次の一手となり得ます。
越境ECで“非対面”でも信頼される営業ができる理由
BtoBの商談には信頼関係が欠かせません。だからこそ「ECで売れるのか?」と疑問を持つ方もいます。しかし、実際には技術情報の丁寧な掲載や導入事例の提示、問い合わせ対応の工夫により、“非対面”でも信用を得ることが可能です。むしろ情報の可視化が進む今の時代では、オンライン上でしっかりと価値を伝えられることが営業力の一部です。越境ECは営業担当者の代わりに、商品力と提案力を発信する営業チャネルとして機能します。
実際に成果を出す中小製造業のリアルな声
実際に越境ECで成果を上げている中小企業の多くは、ニッチな技術や独自性の高い部品を扱っています。「海外の展示会には出せないが、自社製品に合った市場は必ずある」と信じ、英語での商品紹介や問い合わせ対応を丁寧に行うことで、新規顧客との関係構築に成功しています。越境ECは、大企業だけのものではありません。むしろ“世界で通用する強み”を持ったBtoB企業こそ、着実に成果を出しやすい土壌が整っています。
2. 越境ECの基本|BtoBでも使える始め方とは?

自社サイト or モール出店?越境ECには2つの道があります
越境ECを始めるには、大きく「自社ECサイト型」と「モール出店型」の2つの選択肢があります。Shopifyなどで独自に越境対応のサイトを構築する方法は、ブランド構築や価格設定の自由度が高くなります。一方で、AmazonやAlibabaなどのモール型は、集客力があり、スピーディにテスト販売ができる利点があります。BtoBであっても、販路開拓の初期段階ではモールを活用し、後に自社サイトへ誘導する“ハイブリッド型”の運用が効果的です。
Shopee、Amazon、Shopify…どれを使うべきか?
海外向けの越境ECでよく使われているのがShopee(東南アジア向け)、Amazon(北米・欧州)、そして自社構築に強いShopifyです。BtoB企業が海外展開をする際には、対象となる国やターゲット顧客に合わせて選ぶことが大切です。例えば、東南アジアに多い小ロット法人向けにはShopeeが、アメリカの企業担当者向けにはAmazonが強みを発揮します。Shopifyは自由度が高く、見込み客との関係構築や導線設計に最適です。
越境ECのコスト構造と社内の準備ポイント
越境ECでは、初期費用よりも「翻訳対応」「物流設計」「問い合わせ体制」など、運用の部分にコストと工数が発生します。例えば、プラットフォーム利用料や決済手数料、広告費、通関や輸送コストが主な経費となります。また、社内で担当者を決め、社内で誰がどこまで対応するかを明確にすることで、継続的な運用が可能になります。越境ECは始めたあとが本番。長期的な視点で体制づくりを行うことが重要です。
3. 商材・ターゲット国の選び方|成功率を上げる第一歩

越境ECに向いているBtoB商材の特徴とは?
越境ECで成果を出すBtoB商材にはいくつかの共通点があります。それは「ニッチ」「差別化されている」「品質に信頼がある」ということです。たとえば、日本独自の規格品や、高精度を求められる部品、OEM供給が可能な汎用部材などは、海外企業にとっても貴重な選択肢となります。大量流通が前提の商品よりも、課題解決型の商材や小ロット対応できる製品が、海外顧客のニーズと一致しやすい傾向があります。
ターゲット国の選定は“ニーズ×実現性”で考える
どの国をターゲットにするかは、「自社商材にニーズがある国」かつ「販売・配送が実現可能な国」から絞るのが基本です。東南アジアや北米、台湾などは日本製品への信頼が高く、BtoB商材の受け入れ土壌もあります。まずはGoogleトレンドや現地のECモール、問い合わせ実績などから仮説を立て、市場規模だけでなく、関税・物流・言語対応などの現実的なハードルも含めて判断することが、失敗しない海外営業戦略につながります。
市場調査のコツは“検索されるかどうか”を確認すること
BtoB企業にとっての市場調査は「誰が・何を探しているのか」を把握することが鍵です。特に越境ECでは、検索エンジンやモール内検索が主な顧客導線になるため、自社製品に関連するキーワードで検索されているかを確認しましょう。GoogleトレンドやUbersuggestなどのツールを使えば、検索ボリュームや競合の有無もチェックできます。売れるかどうかの判断材料は、現場の勘ではなく“データ”です。
4. 越境ECを成果につなげる運用ノウハウ

商品ページは“営業資料”だと考えるべきです
BtoB越境ECにおいて、商品ページはまさに「非対面営業の資料」です。単なるスペックの羅列ではなく、「この製品で何ができるか」「なぜ選ばれるのか」をしっかり伝えることが重要です。導入事例や使用例、製品の強みや他社との違いを丁寧に記載することで、顧客の意思決定を後押しできます。また、翻訳は機械任せにせず、業界用語を意識したネイティブチェックを入れることが、信頼感の差を生みます。
物流・決済・返品の設計で“信頼される企業”に
海外との取引では「ちゃんと届くか」「返金できるか」といった安心感が重要です。発送方法はEMSやDHLなどのトラッキング付きにし、到着日数や送料を明確に提示しましょう。関税負担のルールや返品条件も事前に記載することで、トラブルの防止になります。さらに、複数の決済手段(PayPalやクレカなど)に対応することで、BtoB顧客の利用ハードルも下がります。これらの整備が“取引したくなる企業”への第一歩です。
問合せ対応から商談化する営業スキルも重要です
越境ECを通じて得られる問い合わせは、まさに営業チャンスです。ただし、対応を誤ると商談に至らず終わってしまいます。初動の返信は24時間以内に行い、テンプレートではなく相手の質問に的確に答えることが基本です。また、興味を持ってくれた理由を逆質問しながら、ニーズの深掘りを行いましょう。商談に発展させるには、メール対応力と提案力がカギ。BtoB営業経験を活かせるフェーズでもあります。
5. 越境EC×営業のハイブリッド戦略とは?

越境ECは“営業の入口”として機能する時代
今の時代、Web経由で商談が始まるのは当たり前になっています。越境ECで製品を知った企業が問い合わせをしてきて、そこからZoom商談につながる――そんな流れが実際に増えています。つまり、越境ECは「営業の補完」ではなく「商談の起点」として活用できるのです。特に新規開拓が課題になっている企業にとっては、海外営業の仕組みの中にECを組み込むことで、リード獲得数が大きく変わります。
展示会や既存営業と連動させた“攻めの設計”を
越境ECとリアル営業は、どちらか一方ではなく両立が可能です。たとえば展示会で名刺交換した相手に「越境ECサイトで製品一覧をご覧ください」と誘導したり、ECで商品に関心を示した相手を営業がフォローアップしたりすることで、接点の幅が広がります。既存の営業フローに越境ECを“組み込む”発想があれば、無理なく運用でき、かつ成果も出やすくなります。両者を連携させた設計が理想です。
成功企業の共通点は“社内で回せる仕組み化”にあり
越境ECで成功している企業の多くは、「仕組み」で営業活動を支えています。たとえば商品登録のマニュアル化、問い合わせ対応のルール整備、定期的なデータ分析による改善など、属人化を避ける体制ができています。営業担当が1人退職しても回る、部署をまたいで連携できる、そんな運用体制こそが“再現性ある営業活動”を生み出します。仕組み化こそが、成果の継続と拡張のカギとなります。
6. まとめ|今こそ、越境ECでBtoB営業を進化させよう

越境ECはBtoB営業の“最前線”になり得ます
今までは「ECはBtoCだけ」と思われがちでしたが、実はBtoBの海外営業にこそ向いているのが越境ECです。理由はシンプルで、「探している人が自分から見つけてくれる」から。高機能・高品質・ニッチな商材ほど、Webを通じて効率的に見つけてもらう価値があります。BtoB営業のスタイルを刷新し、オンラインを武器に変える。そんな攻めの戦略こそ、今まさに求められています。
まずは小さく始めて“試して学ぶ”スタンスで
越境ECは完璧を目指さなくても始められます。まずは1商品・1国に絞り、小さくスタートしてデータを取りながら改善していくスタンスがベストです。予算も数十万円からスタートできるため、展示会や海外出張に比べて圧倒的に低コスト。特に初期投資を抑えたい企業にとっては、リスクを最小限に抑えつつ“実戦から学べる営業チャネル”として優秀です。PDCAを回しながら継続すれば、確実に成果へとつながります。
「売る」だけでなく「営業の仕組み」を整えることが大切
越境ECを導入しても、商品が並んでいるだけでは売れません。大切なのは、売れる仕組み=営業の仕組みをどう作るかという視点です。商品ページ、広告導線、問い合わせ対応、商談フォローなど、一連の営業プロセスを“オンライン化”する意識が重要です。リアル営業のノウハウを活かしながら、デジタルで再構築することで、海外販路の拡大と営業活動の効率化を同時に実現することができます。
監修者紹介
中島 嘉一 代表取締役
SNSリンク:https://linktr.ee/nakajima
株式会社コスパ・テクノロジーズ 代表取締役。
愛媛大学情報工学部卒業後、船井電機にて中国駐在し5,000人規模の組織管理とウォルマート向け海外営業を担当。
上海で起業し通算10年の中国ビジネス経験を持つ。Web制作・デジタルマーケティング歴13年以上で現在は英語圏・中華圏を中心とした海外展開支援のスペシャリストとして活動。
多言語Webサイト構築、越境EC、SNS・広告運用を駆使して企業の海外顧客開拓から、国内向けWebサイト制作・ブランディングまで、戦略立案から実行まで一貫サポート。
海外ビジネスに関するセミナーやイベントに登壇するほか、SNS総フォロワー5万人以上、中小機構海外販路開拓アドバイザーとして中小企業から上場企業まで幅広く支援実績を持つ。