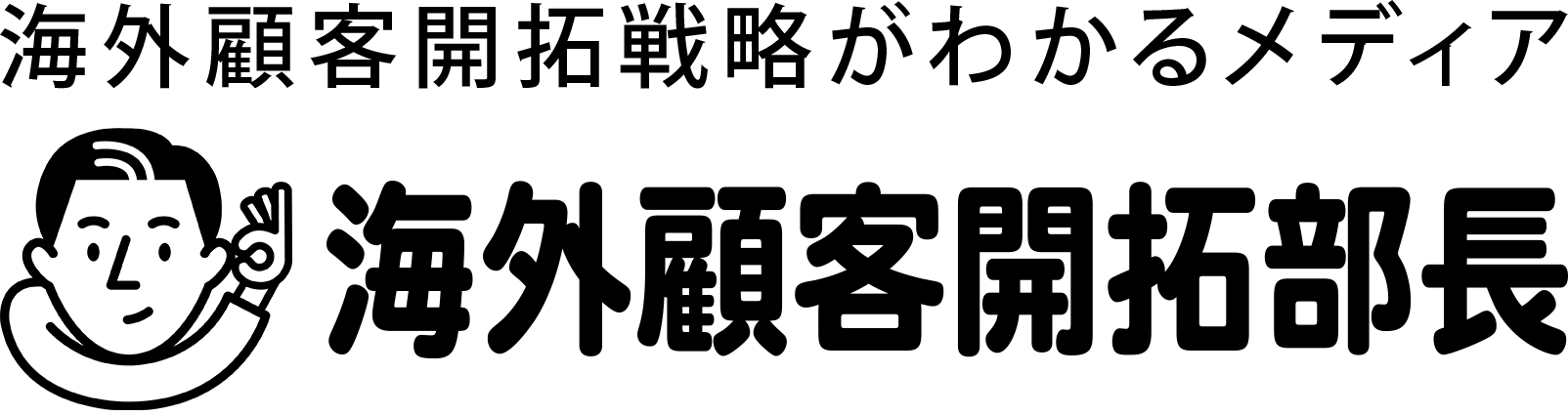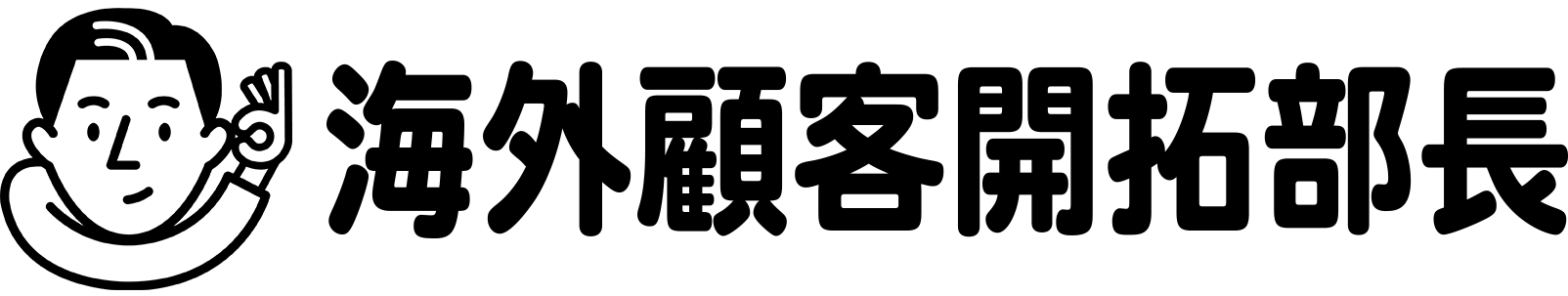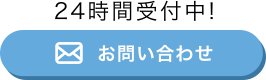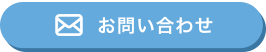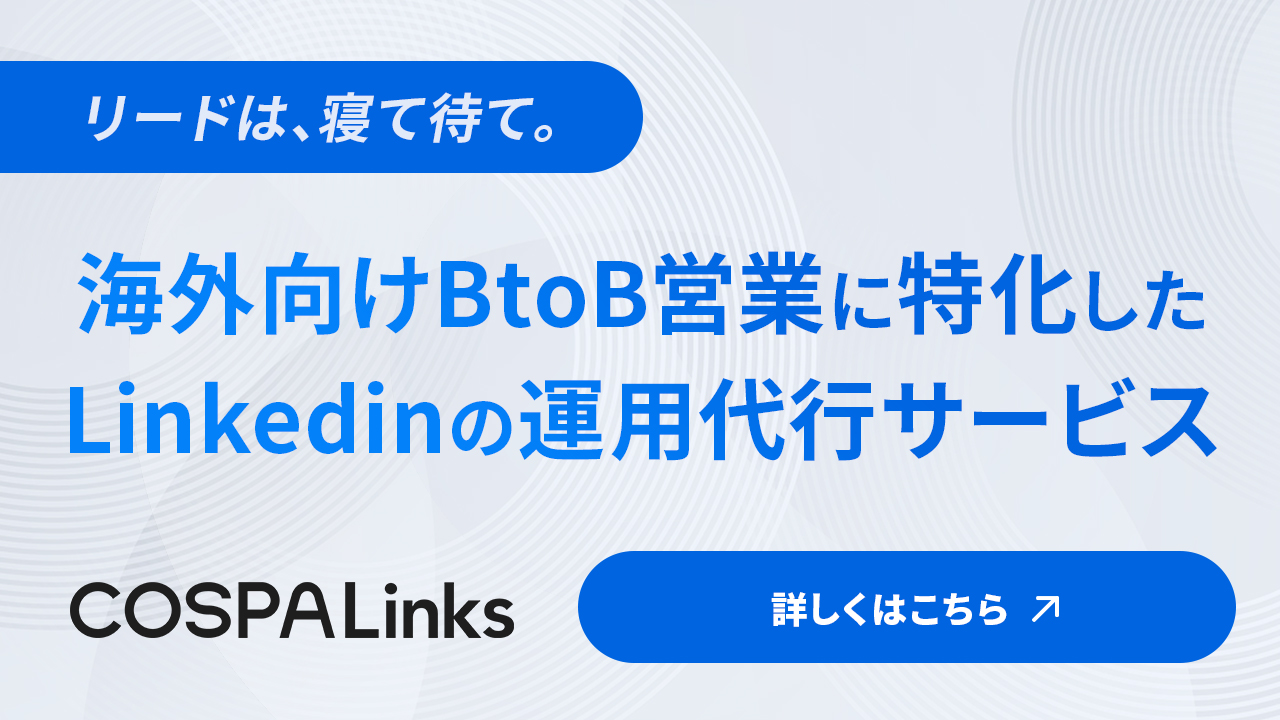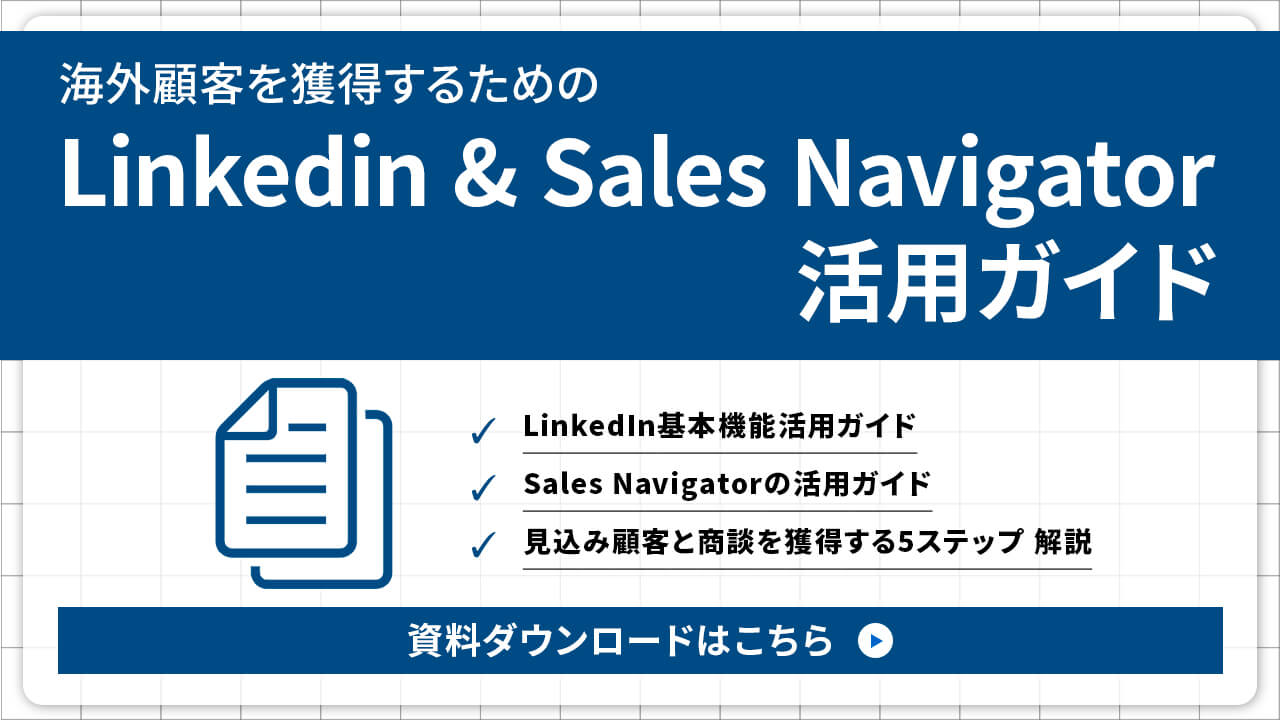海外顧客開拓は“無料支援”から!海外営業の頼れる味方、公的機関まとめ
目次
1.なぜ今、公的機関を使った海外営業支援が注目されているのか?

展示会依存からの脱却と海外営業戦略の再構築
海外営業において、日本企業の多くが長年頼ってきたのが海外展示会の出展です。実際に現地のバイヤーと直接接点を持てる貴重な機会である一方、展示会は出展費・渡航費などのコストが高く、年に数回しか実施されないという制約もあります。特にコロナ禍を機に、展示会に依存しない海外営業戦略の必要性が明確になりました。こうした背景の中、公的機関の支援を活用することで、オンライン商談やデジタルマーケティング、越境ECを通じた新たな海外営業手法が中小企業にも広がっています。低予算でも活用できる支援策が豊富に揃っていることから、海外営業の再構築を図る企業にとって公的機関は強力なパートナーとなっています。
中小企業が直面する「海外顧客開拓の壁」
中小企業にとって、海外顧客の開拓は大きな壁です。言語の違い、商習慣の違い、契約や輸出入に関する法的手続きの煩雑さなど、国内営業とは異なる課題が山積しています。また、海外市場の需要や競合状況についての情報が不足していることから、どこから手をつければよいのか分からず、踏み出せない企業も少なくありません。こうした中で注目されているのが、公的機関によるサポートです。ジェトロや中小機構、自治体などは、市場調査のサポートや、商談先の紹介、専門家の派遣など、顧客開拓の初期段階から丁寧に伴走してくれる存在です。公的支援を活用することで、海外営業の第一歩を自信を持って踏み出すことが可能になります。
公的機関支援を使えば、海外営業のハードルは下がる
海外営業と聞くと「自社には無理」「大手しかできない」と感じる中小企業も多いですが、公的機関の支援を活用することで、そのハードルは大きく下がります。例えば、展示会に出展したことがない企業でも、ジェトロの「ジャパンブース」枠を活用すれば、手厚いサポートのもとで海外展示会に参加できます。また、商談先のリストアップや現地通訳の手配、輸出手続きに関するアドバイスなど、海外営業に必要な実務を支援してくれる制度も充実しています。補助金や助成金を活用すれば、初期コストの負担も抑えられます。これまで海外営業に踏み切れなかった企業でも、公的機関のサポートを活用すれば、現実的かつ戦略的に海外市場へアプローチできるのです。
2.海外営業を支援する主要な公的機関とは?
ジェトロ:海外展示会、商談マッチング、現地支援の中核機関

ジェトロ(日本貿易振興機構)は、海外営業支援における代表的な公的機関であり、世界各国に拠点を持つネットワークを活かして日本企業の海外進出を総合的にサポートしています。特に注目すべきは、海外見本市への「ジャパンブース」出展支援です。ジェトロが選定した展示会において、ブースの手配から商談の事前準備、現地でのフォローアップまで一貫して支援が行われます。さらに、オンライン商談のマッチングイベントや「Japan Street」といったバイヤー向けEC型カタログサイトの活用により、コロナ以降も継続的な海外顧客開拓が可能になっています。初めての海外営業でも、ジェトロの伴走支援があれば安心して挑戦できるのが大きな魅力です。
中小機構:専門家派遣とBtoBマッチング「J-GoodTech」

中小企業基盤整備機構(中小機構)は、特に中小企業に特化した海外展開支援を行っており、その中心的な施策の一つが「ハンズオン支援」です。この支援では、海外営業に精通した専門家が企業に寄り添い、戦略設計から実行までを一貫して支援します。また、国内外の企業とのビジネスマッチングを促進する「J-GoodTech(ジェグテック)」というプラットフォームを運営しており、登録企業は技術や製品情報を公開しながら、相手先企業と直接コンタクトを取ることができます。実際にJ-GoodTech経由で大手電子部品メーカーとの取引に成功した中小企業も存在しており、現場での成果も確認されています。地に足のついた支援体制で、着実な海外営業を後押ししてくれるのが中小機構の特徴です。
地方自治体・商工会議所のきめ細かな支援策

地方自治体や商工会議所・商工会も、地域に根差した視点から中小企業の海外営業を支援しています。例えば東京都中小企業振興公社や神奈川県産業振興センターでは、独自の助成金制度や展示会出展支援、現地駐在員による商談サポートなどを展開しています。また、商工会議所は全国にネットワークを持ち、在外日本人商工会議所と連携した現地情報の提供や、輸出入に関する実務的な相談対応も行っています。特に地方都市においては、これらの公的機関が「最初に相談すべき窓口」としての役割を果たしており、地域企業のリソース不足を補完する存在となっています。大都市圏だけでなく、地方でも活用可能な海外営業支援として、見逃せない存在です。
3.公的支援を活用して海外市場調査と営業戦略を強化する

無料・低コストで使える海外市場調査支援
海外営業に乗り出す際、まず必要になるのが「市場の見極め」です。自社製品が現地で受け入れられるか、競合製品はどのような価格帯か、現地のニーズや文化的背景はどうかといった点は、販売戦略を考える上で非常に重要です。公的機関では、そうした情報を無料もしくは低コストで提供しています。たとえばジェトロの「国・地域別ビジネス情報」では、各国の経済動向、制度、消費傾向に関する詳細なレポートが閲覧可能です。また、中小機構や自治体も、専門家によるヒアリングや業界別の調査支援を実施しており、現地企業へのアンケートやバイヤーの声をもとにリアルな市場情報を入手することが可能です。限られた予算でも、精度の高い市場調査ができる点が大きな魅力です。
公的機関の専門家相談・調査レポート活用術
市場調査を進めるにあたっては、情報を読むだけでなく、専門家との相談を通じて理解を深めることがカギとなります。公的機関では、海外ビジネス経験豊富な専門アドバイザーが常駐しており、自社の業種や進出予定国に応じてアドバイスをもらうことができます。例えば、ジェトロの「貿易投資相談」では、個別の課題や疑問に対して無料で専門家が対応してくれます。また、地方自治体の産業振興センターでも、地域企業向けに専門家派遣制度を設け、実際に現地調査や視察を同行してもらうことも可能です。相談を通じて、自社が活用すべき支援メニューや補助金制度も明確になるため、効率的かつ効果的な営業戦略の設計が期待できます。
海外営業のための市場選定とターゲティング
海外営業を成功させるには、全世界を対象に漠然と動くのではなく、「どの市場を攻めるのか」を明確に絞り込む必要があります。特に中小企業にとっては、人的・資金的リソースが限られているため、選定と集中が非常に重要です。公的機関では、過去の支援実績や各国の産業動向に基づき、業種ごとに相性のよい国や地域を提案してくれるケースもあります。さらに、競合分析や現地の消費者インサイトをもとに、どのような訴求ポイントが刺さるのかといった具体的な営業メッセージまで落とし込むサポートも可能です。ターゲティングが明確になれば、展示会の選定から販促資料の制作、営業人材の配置に至るまで、一貫した戦略立案が可能になります。
4.海外営業に使える具体的な支援施策・ツールまとめ

補助金・助成金:展示会・販促・翻訳費用などをカバー
海外営業を行ううえでネックになりやすいのが、初期費用の負担です。展示会出展費、翻訳費用、パンフレット作成費、渡航費など、さまざまなコストが発生します。公的機関では、こうした経費をカバーするための補助金・助成制度を数多く用意しています。たとえば、東京都や大阪府などの自治体では、海外展示会への出展経費の一部を助成する制度が整備されています。ジェトロもまた、選定された企業に対して出展料の補助や、現地通訳費の一部補助などを行っています。これらの制度を活用すれば、限られた予算でも海外営業に踏み出しやすくなり、チャレンジのハードルが大きく下がります。制度には応募期間や条件があるため、事前に情報収集しておくことが重要です。
越境EC・現地拠点支援などの実践的サポート
デジタルシフトが進む中、越境ECを通じた海外営業も有効な手段として注目されています。ジェトロでは「JAPAN MALL事業」などを通じて、AmazonやShopeeといった海外ECモールへの出店を支援しており、商品掲載から販促、物流まで一貫したサポートを受けることが可能です。また、中小機構や自治体では、現地駐在員事務所や連携機関を通じて、現地市場でのテスト販売やパートナー企業との連携構築を支援しています。さらに、法人設立やオフィス開設を伴う本格進出に対しても、専門家派遣や現地行政との調整支援が提供される場合があります。こうした施策を活用することで、段階的かつ現実的な海外市場参入が可能となります。
公的機関×営業代行を組み合わせたハイブリッド戦略
公的支援だけで海外営業を完結させるのではなく、営業代行や現地パートナーと組み合わせることで、より実効性のある営業体制を構築する企業も増えています。公的機関は、初期調査・戦略設計・展示会出展といった「起点づくり」に強みがあり、一方、営業代行会社は「現地での顧客獲得」や「販売活動の継続運用」に力を発揮します。たとえば、ジェトロの商談会で出会った現地企業との継続的な商談フォローを営業代行に任せる、あるいは中小機構の専門家にアドバイスを受けながら営業代行会社と連携を組む、といった使い方が可能です。公的支援と民間支援を併用することで、低コストと実行力のバランスを取った、持続可能な海外営業体制が実現できます。
5.公的支援を活用して海外展開に成功した企業事例

株式会社新美鐵工所:つながり重視で海外展開に成功
愛知県の新美鐵工所は、長年にわたり高品質な金属加工を提供してきた町工場ですが、ジェトロの支援を受けて海外営業に踏み出しました。同社は「現地の声を聞きながら関係を築く」ことを重視し、まずはジェトロ主催のオンライン商談会に参加。バイヤーとの信頼関係を構築した上で、欧州市場向けの提案型営業を開始しました。その後もジェトロの担当者と連携しながら、輸出の手続きや現地のニーズに合わせた製品改良を実施。結果として、初めての海外取引を成約にまでつなげることができました。大手ではない中小製造業でも、地道な営業と公的支援を組み合わせることで、着実に海外展開が実現できる好例といえます。
パイフォトニクス株式会社:展示会同行支援で米国パートナー獲得
静岡県の光技術系ベンチャー、パイフォトニクス株式会社は、ジェトロの「新輸出大国コンソーシアム」の一環で、専門家の同行支援を受けながら米国の展示会に出展。展示会前には専門家とともにプレゼン内容やブースの訴求ポイントを徹底的にブラッシュアップし、現地での反応も高評価を得ました。展示会終了後には、ジェトロのフォローにより商談が継続され、現地企業とのパートナーシップ契約につながりました。単なる展示会出展に終わらず、事前準備・現地対応・事後フォローまで一貫して支援が入ったことで、実利のある成果に結びついた事例です。こうした「伴走型支援」の威力が最大限に発揮された成功例といえるでしょう。
株式会社エッチ・アイ・シー:J-GoodTechで大手案件を受注
大阪のIT企業、エッチ・アイ・シーは、中小機構が運営するBtoBマッチングプラットフォーム「J-GoodTech」を通じて、大手電子部品メーカーからの受注に成功しました。同社は、IoT分野のソフトウェア開発を得意としており、自社の技術情報をJ-GoodTechに掲載。その内容に興味を示した企業からアプローチを受け、オンライン商談を経て、共同開発案件がスタートしました。当初は海外営業経験の少ない企業でしたが、中小機構の専門家によるアドバイスや、マッチング後の交渉支援を受けることで、信頼性の高い取引へと発展しました。オンラインを活用した公的支援の好例であり、地方IT企業の新たな活路を示す事例です。
6.まとめ:海外営業の第一歩は「公的支援を使い倒す」ことから
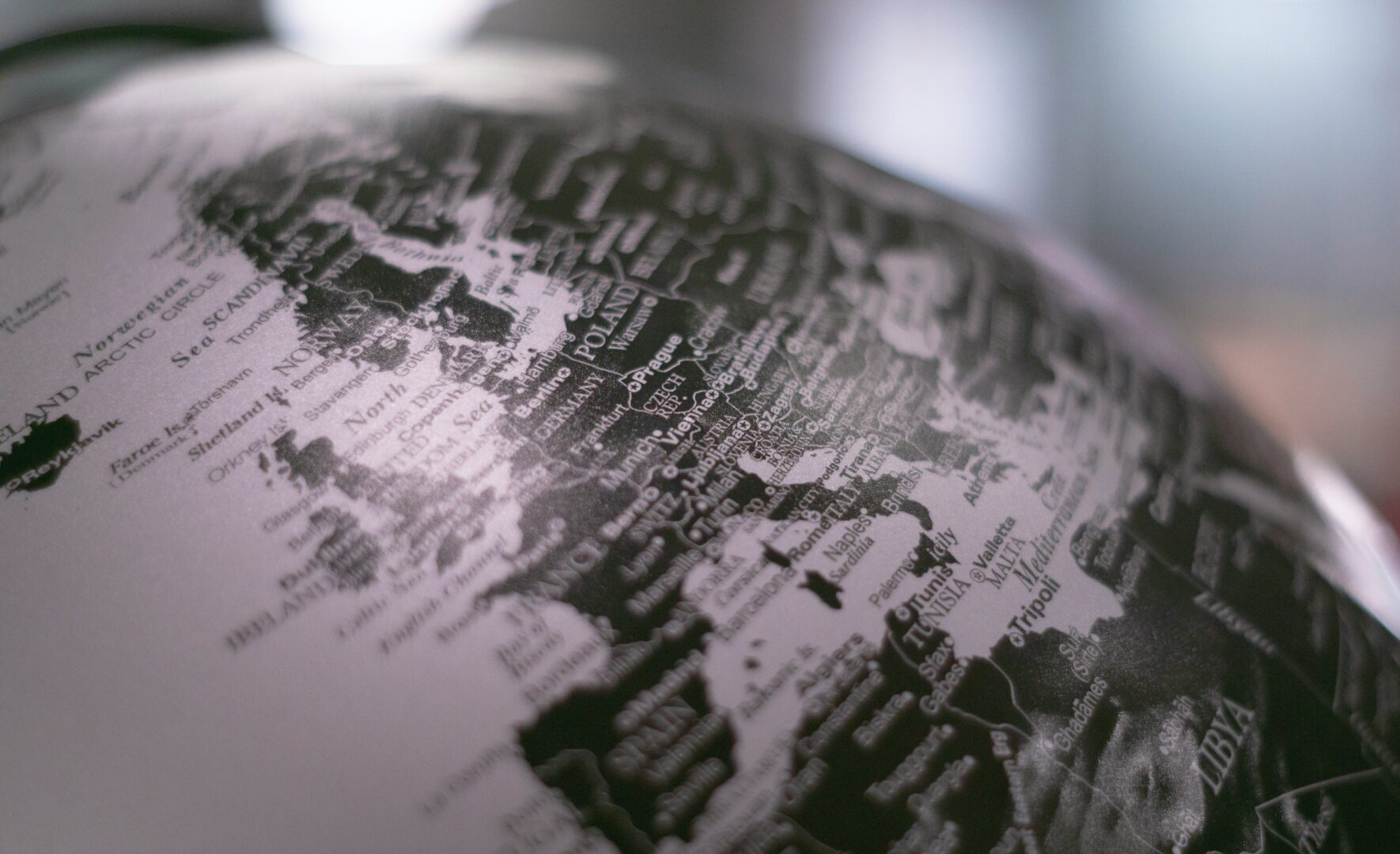
自社だけで抱え込まず、公的機関をフル活用しよう
海外営業を始める際、多くの企業が「社内リソースが足りない」「海外経験がない」といった不安を抱えがちです。しかし、全国には豊富な実績とネットワークを持つ公的支援機関が数多く存在し、無料または低コストで活用することができます。ジェトロや中小機構、自治体の振興センターや商工会議所など、それぞれ特色ある支援策を持っており、目的やステージに応じて最適な機関を選ぶことが重要です。「まずは相談」から始めることができる点も、忙しい中小企業にとっては大きなメリットです。
営業代行や民間サービスとの組み合わせも有効
公的支援には制度や期間の制約もあるため、必要に応じて営業代行や現地パートナーなど、民間サービスとの組み合わせを検討することも効果的です。たとえば、補助金で出展した展示会の後の営業フォローを営業代行会社に依頼する、あるいは越境ECの運営を外部に任せるなど、リソース配分を工夫することで継続的な成果を得やすくなります。公的支援は「入口支援」に強く、民間は「実行支援」に強いという役割分担を意識すれば、理想的な海外営業体制を構築できます。
海外営業成功の鍵は“知る→相談する→動く”の循環
公的支援の最大の強みは、「情報」「人材」「機会」が揃っていることです。知らなければ活用できませんが、知ることで道は開けます。まずは情報収集を行い、自社の現状に照らして適切な支援を探し、必要であれば公的機関の相談窓口にアプローチしてみましょう。そして実行に移すことで、成果が生まれます。この“知る→相談する→動く”の循環こそが、海外営業成功の王道であり、公的支援はそのすべての段階で力になってくれる存在です。
監修者紹介
中島 嘉一 代表取締役
SNSリンク:https://linktr.ee/nakajima
株式会社コスパ・テクノロジーズ 代表取締役。
愛媛大学情報工学部卒業後、船井電機にて中国駐在し5,000人規模の組織管理とウォルマート向け海外営業を担当。
上海で起業し通算10年の中国ビジネス経験を持つ。Web制作・デジタルマーケティング歴13年以上で現在は英語圏・中華圏を中心とした海外展開支援のスペシャリストとして活動。
多言語Webサイト構築、越境EC、SNS・広告運用を駆使して企業の海外顧客開拓から、国内向けWebサイト制作・ブランディングまで、戦略立案から実行まで一貫サポート。
海外ビジネスに関するセミナーやイベントに登壇するほか、SNS総フォロワー5万人以上、中小機構海外販路開拓アドバイザーとして中小企業から上場企業まで幅広く支援実績を持つ。